- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2039 宗教・精神世界 『聖書、コーラン、仏典』 中村圭志著(中公新書)
2021.05.24
『聖書、コーラン、仏典』中村圭志著(中公新書)を再読しました。「原典から宗教の本質をさぐる」というサブタイトルがついています。著者は1958年、北海道生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程満期退学(宗教学・宗教史学)。宗教研究者、翻訳家、昭和女子大学非常勤講師。一条真也の読書館『教養としてよむ世界の教典』で紹介した本をはじめ、著書多数。
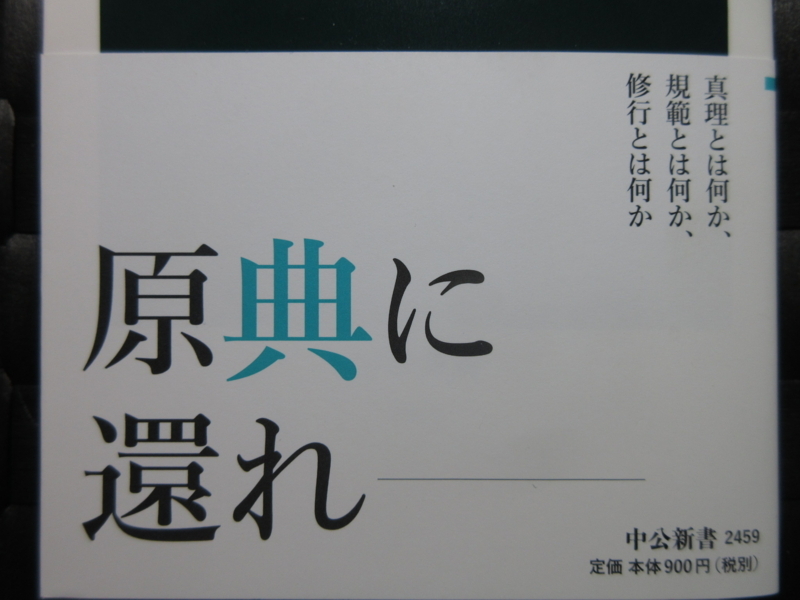 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「真理とは何か、規範とは何か、修行とは何か」と書かれ、「原典に還れ」と大書されています。帯の裏およびカバー前そでには、内容紹介があります。
「宗教にはそれぞれ教典がある。開祖やその弟子たち、あるいは教団によって書かれ、編まれ、受け継がれた『教えの原点』だ。時代が変わり、教義が揺れる時に、人々が立ち返る場所としての原典ともいえよう。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教から、ヒンドゥー教や神道、儒教・道教まで。歴史を超えて受け継がれてきた教典はどのように生まれ、何を私たちに伝えようとしているのか。信仰の核心に迫る新しい宗教ガイド」
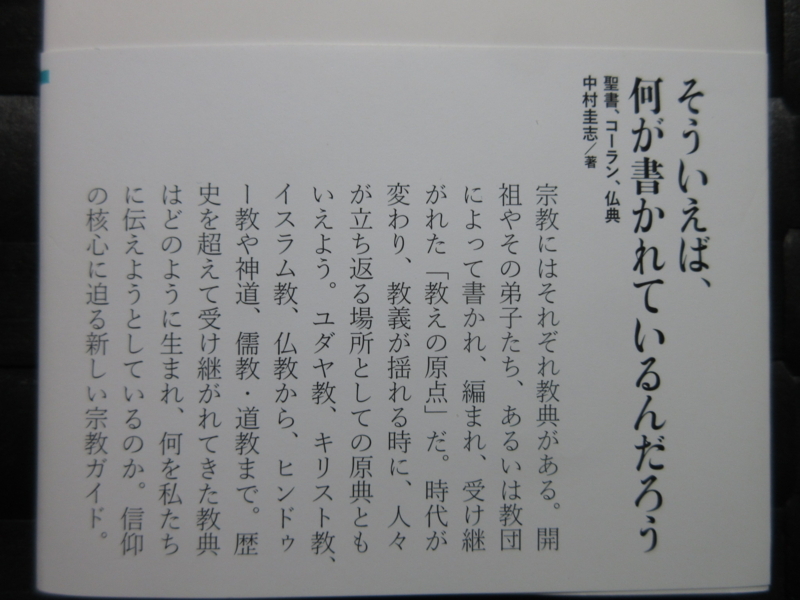 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
序章 小教典としての祈りと念仏
第1章 旧約聖書――イスラエル民族と神との約束
Ⅰ 創世記
Ⅱ 出エジプト記
Ⅲ 「律法」の中の戒律
Ⅳ 「預言者」と「諸書」
第2章 新約聖書――救世主の物語
Ⅰ 共観福音書
Ⅱ ヨハネによる福音書
Ⅲ 受難物語
Ⅳ パウロ書簡その他
第3章 コーラン――正しい社会の建設
第4章 パーリ仏典――ブッダの修行マニュアル
Ⅰ 釈迦の生涯
Ⅱ 教団の伝える教え
Ⅲ パーリ仏典を読む
第5章 大乗仏典――諸仏の救済ビジョン
Ⅰ 般若経典
Ⅱ 法華経
Ⅲ 浄土三部経
第6章 東ユーラシアの多神教の教典
Ⅰ ヒンドゥー教典
Ⅱ 儒教・道教の教典
Ⅲ 神道の祝詞と神話
終章 教典のエコロジー
「おわりに」
「はじめに」で、著者は以下のように述べています。
「宗教が真理と規範の典拠としている文献が教典であるが、その性格も形態も使い方もさまざまである。聖書やコーランは『天地創造の神』からの倫理的なメッセージだとされるが、仏典は人間釈迦が到達したという『悟り』に人々を導き入れるための修行マニュアルだ。聖書やコーランは小型六法全書くらいの大きさにまとまっているが、東南アジアの仏典も漢訳の大乗仏典も、それぞれ百科事典並みの分量がある。紀元前からの歴史的背景をもつ聖書も仏典も1000年以上にわたって編纂され続けたものだが、大宗教の中では最も新しく成立したコーランは短時日に一挙に編集されたものである。コーランはアラビア語の原典で読むべきものとされているが、聖書や仏典は翻訳に対して鷹揚であった。日本仏教は漢訳仏典を典拠としており、明治になるまでインドの原典まで遡って論じることは基本的に無かった」
また、「注意していただきたいことがある」として、著者は「昔の社会は識字率が低かった。だからほとんどの信者は教典に直接接することができなかった。昔の人は信心深かったから、みな聖なるテキストを読んでいたと思うのは、現代人の抱きがちな誤解である。聖書を持ち歩いている新宗教の勧誘者なども勘違いしている気配がある。昔の宗教で重視されたのは、儀礼であり、社会生活上の戒律であり、集団で行なう修行であった。教典はそうした共同体的な営みを運営するための指導員向けツールのような性格を持っていた。そういう社会的な実体抜きで、教典のデキストの中に神秘的な『霊性』を探そうとしてもあまり意味はないだろう。誰でも教典にアプローチできるようになった個人主義の現代、もはや昔の人のような教典の使い方はできないのかもしれない。文化遺産としての教典に対するニュートラルで批判的なアプローチが、ますます必要になっていくだろう」と述べます。
序章「小教典としての祈りと念仏」で、著者は「聖職者や修行者、あるいは神学者はともかく、一般信徒が教典をきちんと読み込むことは、そう多いことではない。昔は識字率が低いのでまして稀であった。一般信徒の多くは、教典のエッセンスとされる部分や、教典のパワーが込められているとされる聖句を唱えて済ます場合が多い。それがいわゆる祈りであり、読経であり、また呪文のような念仏や題目である」と述べています。
序章の最後では、「賢治の『雨ニモマケズ』」として、著者は「『雨ニモマケズ』は、仏教教理の重要ポイントを分かりやすい言葉で整理した信仰箇条、さらには一種の祈りのような性格をもっている。賢治は学生時代にキリスト教会にも通っていたので、主の祈りのことを知っていただろう。もしかしたら、賢治はこれを真似て、分かりやすい言葉で説かれた仏教式の祈りの言葉を私的に案出してみたのかもしれない」と述べます。
続けて、著者は「雨ニモマケズ」について述べます。
「『雨ニモマケズ』が日本人の心に強く訴えるところがあるのは、単に『デクノボー』のあたりが日本人好みの自虐的表現になっているからというだけではなく、この短かい宣誓の文句が、仏教の深い教えを分かりやすく、ほとんどキリスト教の『主の祈り』に似た形でクリアにシンプルに提示している点にあると思う。このように文芸と信仰が交錯し、伝統の教えと西洋の影響がハイブリッドに融合している点に、現代日本人のスピリチュアリティの本質的な部分が現われているように、私には思われてならない。無数にある長い長い仏典も、現代風にアレンジすると、結局は『雨ニモマケズ』のようなものに結晶化するのではないだろうか」
第1章「旧約聖書――イスラエル民族と神との約束」のⅢ「『律法』の中の戒律」では、「穢れの意識と掟の不合理性」として、著者は「今日のユダヤ教徒は戒律のすべてを守っているわけではない。613もある戒律のうち、古代の神殿儀礼などに関するものは現代では行ないたくても行なえない。また、正統派、保守派、改革派とある3つの主流宗派のうち、改革派は戒律に関しては緩やかに解釈している。正統派はなるべく守ろうとする。保守派はその中間である。ユダヤ人の全人口1500万人のうち500万人はアメリカに、500万人はイスラエル国に住んでいるが、アメリカには改革派が多く、イスラエルには正統派が多いという。ちなみに近年欧米諸国で合法化されるようになった同性婚であるが、ユダヤ教の保守派と改革派はOK、正統派は駄目という見解をとっている」と述べます。
また、「預言の例――イザヤ書から」では、「本来、孤児や寡婦などの社会的弱者は社会のリーダーが守るべき存在であったのだが、社会が不安定化した時代には打ち捨てられていたようである。一神教の神の掟の要点はこうした弱者を守るところにある。後世、キリスト教の開祖(キリスト)の説いた『神の国』も、イスラム教の開祖(ムハンマド)が告げたアッラーの教えの要点も、やはり社会的弱者の保護にあった」と述べています。
さらに、「キリストを予告するもの」として、「後世にキリストが出現して、裁判にかけられ十字架刑死したとき、イザヤの預言通りのことが起きたとイエスの信奉者たちは解釈した。イザヤがキリストを予言したのか、キリストがイザヤの言葉に添うように行動したのか、福音書の書き手がイザヤにあわせて伝記の内容を調整したのかは分からないが、しかし、世の常識に逆らっても世のための正義を貫いて犠牲となる英雄というのは、物語パターンとしてはどこにでも現われ得ると言えるだろう」と述べています。
第2章「新約聖書――救世主の物語」では、著者は「パウロ書簡」として、イエス・キリストについて、「キリストの伝記映画を見ると、ナザレのイエスが生前から有名人であったかのような印象を受けるが、実際には極めてマイナーで超ローカルな存在であっただろう。イエス信仰は死後の復活の噂を契機として人々の間に広まり、パウロの意味づけによって安定軌道に入ったのだ。そういう意味で、キリスト教を造ったのはパウロだと言われることがある」と述べています。
また、「正典に含まれなかった文書」として、著者は「外典の中には『グノーシス主義』と呼ばれる思想に属するものが多く含まれている。グノーシス主義については、1945年にエジプトのナグ・ハマディという町の近くで古代の数十点の文書が発見されたことによって大きく研究が進んだ。これは、当時ローマ帝国から中東にかけて流行した宗教思想で、一部のキリスト教もこの思想を取り込んでいたのだが、正統派教会からは『異端』とされるに至った。さまざまな形態をもち、神話なども種々雑多なものを含んでいるのだが、概ね共通しているのは、この世界を偽りの神が創造した悪しき世界と捉え、個人の魂の本質部分が世界の外部にある真の神とつながっているという世界観である。個人は世界の外部から啓示される正しい認識(グノーシス)を得ることで救済される。キリスト教バージョンでは、世界を創造した旧約の神が悪しき神、キリストは善なる救済者ということになる」と述べています。
第3章「コーラン――正しい社会の建設」では、「ユダヤ教、キリスト教、イスラム教」として、著者は「イスラム教は、ユダヤ教やキリスト教の影響下に生まれた一神教である。イスラム教徒(ムスリムという)自身の理解では、これはアブラハム(アラビア語でイブラーヒーム)に啓示された一神教を今日純粋な形で伝える宗教である。つまり――ムスリムの理解によれば――天地創造の神は、メッカの交易商人ムハンマドの口を通じて、最終的な啓示を人類に下したのであった。その神の言葉を記録した書がコーラン(アラビア語の発音はむしろクルアーン)なのである」と述べています。ちなみに、わたしはユダヤ・キリスト・イスラムの三大一神教を「三姉妹宗教」としてとらえ、『ユダヤ教vsキリスト教vsイスラム教』(だいわ書房)を書きました。
 『ユダヤ教vsキリスト教vsイスラム教』
『ユダヤ教vsキリスト教vsイスラム教』
(だいわ書房)
また、「平等の正義と信仰の基本」として、著者はイスラム教について、「一神教は、神の高みから人間世界を見下ろすような思考であるから、人間どうしの地位や身分のでこぼこは相対化される。イスラム教では、あらゆる人間を神の奴隷(アブド)と見なす。奴隷どうしだと思えば人類はみな兄弟だと思えるだろう。(中略)地上のいかなるものも礼拝してはいけないのであるから、国王、大統領、映画スターやスポーツ選手などのセレブやアイドルを崇拝してはいけない。地上に崇拝の対象がないというからには、人類はみな兄弟として助け合わなければならない。というわけで、弱者に手を差し伸べることが一神教、そしてイスラム教の基本的な教えとなっている」と述べています。
第4章「パーリ仏典――ブッダの修行マニュアル」では、「悟り中心の宗教」として、著者は「仏教の歴史は長い。そして非常に多様な宗派を派生させた。今日、東南アジアのテーラワーダ仏教では、出家者が戒律を厳格に守ることで自己を律する毎日を送っている。日本・中国・チベットなどの大乗仏教の場合、たとえば密教系の宗派では、マジカルな儀礼を通じて修行者自身が象徴的にブッダと合一できるのだという。禅宗では、ひたすら坐禅することで自らの根底にあるブッダの本性を表わす。浄土信仰では、ひたすら念仏(「南無阿弥陀仏」)を唱えるうちに絶対者である阿弥陀ブッダに救われている自己を発見する。法華信仰では、題目(「南無妙法蓮華経」)を唱えることで、地獄の亡者から悟りのブッダまでの全生命との連帯の世界への扉を開く。こうした宗派ごとの方法論の差は非常に大きく、見ようによっては、宗派と宗派の違いはユダヤ教とキリスト教とイスラム教との差に近いとも言えるだろう。それにもかかわらず、仏教が同一の宗教だと認定できるのは、いずれの宗派も悟りや安心といった人間の心の状態に焦点を当てており、いずれの宗派の信者も自らは開祖釈迦以来の伝統を守っていると考えているからである」と述べています。
また、Ⅰ「釈迦の生涯」では、「誕生から出家まで」として、「釈迦は紀元前463年頃に北インドの王家に生まれた。生まれてすぐの王子が7歩歩んで右手を上げて『天上天下唯我独尊(私は世界で一番すぐれている)』と言ったとよく言われているが、これは釈迦よりも過去に出現したとされる別のブッダについての神話が伝承の過程で紛れ込んだものである(仏教では究極の悟りを得ればブッダになれるので、原理的にはブッダは釈迦人とは限らない)」と書かれています。
「教団の繁栄と釈迦の入滅」として、著者は「釈迦の教団は、当時のガンジス川流域の二大国、マガダ国とコーサラ国のそれぞれの首都において、竹林精舎と祇園精舎という2つの修行キャンプを寄進される。これが寺院の始まりである。修行者たちは無一物のまま村々をゆるやかに歩き回っていたようだが、初夏の雨期には精舎に定住して集中コースに入るという習慣が生まれた。これを雨安居という。なお、教団すなわち修行者の集まりをサンガ(僧伽、僧)という」と述べています。
Ⅲ「パーリ仏典を読む」では、「スッタニパータから」として、釈迦はマジカルな儀礼を否定し、心の修行に目標を切り替えたことが紹介されます。階級制度を無意味と見なし、心を修めた者をこそ「婆羅門」と呼ぶべきだと言いました。
第5章「大乗仏典――諸仏の救済マニュアル」では、「大乗仏教の誕生」として、著者は「仏教は本来、たくさんの戒律によって身を律する修行の宗教であった。釈迦より5世紀ほど後の時代に台頭してきた大乗仏教は、この禁欲的な出家宗教に対する『応用編』であり、大衆性をもち、教えは多様化と複雑化によって彩られている。『大乗』とは広く民衆を救済できる『大きな乗り物』を意味している。同じ頃、中東・地中海地方ではキリスト教が誕生している。キリスト教もまたその母体となったユダヤ教に比べて、教済の間口が広く、かつ神学的な複雑度の高い宗教である。キリスト教では従来の律法に代えて生きて世に出現した神であるキリストを信仰する。大乗仏教では、釈迦の他に阿弥陀や大日如来など、さまざまなブッダに対する信仰が説かれ、神学の多様化が進んでいる。初期仏教であろうが、大乗仏教であろうが、仏教の基本的な世界観は、輪廻と解脱とを対照するものだ」と述べています。
また、「密教経典と曼荼羅」として、著者は「仏教は出家修行を中心とするかなりエリート性の高い宗教であり、農村の民衆の多くは古来の神々を信仰し婆羅門の儀礼や呪術を頼りとする土俗的な宗教を奉じていた。婆羅門教などと呼ばれるこの宗教を再組織化して5世紀以降大々的に復興を遂げた民族的な宗教体系がヒンドゥー教である。大乗仏教は輪廻世界を肯定的に捉え、自利の悟りよりも利他の救いを重んじたとはいえ、民衆的に分かりやすいヒンドゥー教の前には衰退を余儀なくされた。そうした中でヒンドゥー教的な儀礼や呪術の力を取り込んで、壮麗な諸仏諸菩薩のパンテオン(万神廟)的な瞑想のビジョンを打ち立てたのが、5世紀以降台頭した密教だ。これは大乗仏教としては後期ということになる」と述べます。
続けて、著者は「宗教というのは人生哲学のようなものでもあるが、本質的なところにマジックと儀礼がある。慈悲や愛の実践だけでは宗教の実態を尽くせるものではない。キリスト教でも正教会やカトリックは壮麗なる教会の儀礼を信仰の鍵としており、ルルドの泉のような病気治しの奇跡の伝承もたっぷりとある。インド仏教の歴史的発展の最終形が呪術的儀礼に彩られた密教であったことは、それほど不思議なことではないだろう」と述べています。
Ⅱ「法華経」では、「結局、法華経のメッセージは、次の3つに要約できる。第1はあらゆる衆生の成仏可能性、第2はそれを応援する久遠の釈迦の存在、第3は釈迦の恩義に応えて菩薩道を歩むべきこと、である。キリスト教になぞらえれば、万人が潜在的に天国に行けること、それを神キリストが応援していること、そしてキリストの恩義に応えて神に忠実であるべきこと、となるだろう」と書かれています。
第6章「東ユーラシアの多神教の教典」のⅠ「ヒンドゥー教典」では、「最重要の教典ヴェーダ」として、「ヴェーダは紀元前1200年頃から漸次的に成立した文献群である。ヴェーダというサンスクリット語は『(宗教的な)知識』を意味する。ヴェーダは総称であり、祭場に神々を招く際に誦する1000首あまりの讃歌を集めたものがリグ・ヴェーダ、祭儀において旋律をつけて歌う讃歌を集めたもの(多くはリグ・ヴェーダと同じ)がサーマ・ヴェダ、さらに供物を捧げるなど祭儀の際に唱える祭詞を集めたものがヤジュル・ヴェーダ、そして招福除災の呪文を集めたのがアタルヴァ・ヴェーダである。この4種のヴェーダのそれぞれがサンヒター(本集)、祭儀の具体的方法を記したブラーフマナ(祭儀書)、森林の中で伝えられるべき秘義を記したアーラニヤカ(森林書)、神秘哲学的な文献であるウパニシャッド(奥義書)の4つのパートに分かれている」と書かれています。
また、「ウパニシャッドと梵我一如」として、著者は「ウパニシャッドの哲学において重要な概念はブラフマンとアートマンである。もともと呪力のようなものを意味していたブラフマンは、神々をも支配する宇宙の根本原理にまで高められた。他方、もともと気息を意味していたアートマンは、個人の自己の本体の意味にまで高められた。この2つは大宇宙と小宇宙、世界と個人という2つの極限を表わす本質概念だ。どちらも日常的な表層の次元を飛び越えた霊的な概念であるが、この両者を『同一』と見なすのが、ウパニシャッド哲学の中核的思想であるとされる」と述べています。
さらには、「二元的な教典・準教典」として、著者は「インドの古典期にはヴェーダないしウパニシャッド哲学からの展開として、サーンキヤ学派(精神的原理と物質的原理の二元論を説く)、ヨーガ学派(サーンキヤに準じ、最高神を認め、ヨーガを実践する)、ニヤーヤ学派(認識論と論理学を展開)、ヴァイシェーシカ学派(宇宙を6つの原理で説明する)、ミーマーンサー学派(ヴェーダの体系的研究から展開)、ヴェーダーンタ学派(梵我一如による解脱を説く正統派学派)の六派哲学が開花し、それぞれが基本の教典をもっている」と述べます。
続けて、著者は「インドでは5世紀頃に現在の形になったとされる『マハーバーラタ』と3世紀頃に成立した『ラーマーヤナ』の2つの叙事詩も、教典的な扱いを受けている。前者は、はるか太古に起きたバラダ族の王位継承戦争を歌ったものであり、その一部に組み込まれた『バガヴァッド・ギーター』という哲学詩には、自らの本分を尽くすこと(王族階級であれば戦うこと)が解脱の道であると説く神クリシュナ(ヴィシュヌ神の化身)の教えが記されている。後者は、やはりヴィシュヌ神の化身である王子ラーマが、魔王によってランカー島に幽閉された妻シータを救い出す物語である。ここには猿の将軍ハヌマーンが登場するが、これは中国の『西遊記』の孫悟空の元ネタなのだそうだ。ヴィシュヌ神に10の化身があることなどが書かれている『プラーナ聖典』は『ブラフマ・プラーナ』『バーガヴァタ・プラーナ』など5世紀以降に作られた教典群の総称である」と述べています。
Ⅱ「儒教・道教の教典」では、『論語』について、著者は「中国第一の書と言えば、何といっても『論語』だ。紀元前6~5世紀の孔子の言葉を死後に弟子たちが集めたものだが、編纂が完了したのは漢代であるという。ともあれ、成立の出発点の時期はスッタニパータやダンマパダなどの初期仏典に近く、重要度においてはキリスト教世界の福音書に相当する」と述べています。
Ⅲ「神道の祝詞と神話」では、『古事記』について、「冒頭は世界の始まりの描写である。いわば日本神話版創世記だ。天地の創生は最初の神々の発生プロセスと同時である。つまり神が天地を創造したのではない。アメノミナカヌシ(天之御中主)、タカミムスヒ(高御産巣日)、カムムスヒ(神産巣日)という三神が自然に『成』ったのである。ムスヒ(ムスビ)は産霊などとも書かれるが、生成の原理のようなものだ。後世これが縁結びなどの『結び』と合流した。アニメ『君の名は。』で神秘な働きをムスビと呼んでいるが、生命パワーと縁結びのイメージが交錯したもののようである」と述べます。なお、各種の仏典や『論語』『古事記』については、わたしも
「神道&仏教&儒教」の副題を持つ『知ってビックリ! 日本三大宗教のご利益』(だいわ文庫)で詳しく紹介しました。
 『神道&仏教&儒教』(だいわ文庫)
『神道&仏教&儒教』(だいわ文庫)
終章「教典のエコロジー」では、「聖書・コーラン・仏典は並び立つか」として、著者は「聖書とコーラン、と我々は並べて呼ぶが、そもそもこの二書は地位的に異なる位置にあると言うこともできる。イスラム教のコーランに相当するのはキリスト教ではむしろキリストそのものであり、コーランを告げた媒体としてのムハンマドに相当するのが、キリストについて証言している聖書である、という見方もあるくらいだ」と述べています。
また、著者は「聖書などは物語性・歴史性が豊富で、しばしば楽しい読み物の様相を呈しているが、仏典の中核部分はたくさんの概念の抽象的列挙であり、歌のリフレーンのように類似の長い表現を幾度も幾度も繰り返している。『聖書を読もう』という感じで『お経を読もう』と人々に勧めることがなかなかできない所以である。もっとも、仏典にも物語性の強い部分はある。釈迦の成道のプロセスや前世の説話(ジャータカ、本生譚)、法華経の『三車火宅』『長者窮子』の譬喩などである。それでもルカ福音書の放蕩息子の物語に比べたら、長者窮子の譬喩は冗長すぎて今日の読者にはなかなか趣意がつかめないだろう」とも述べています。
さらに、「教典の曖昧な外延」として、著者は「そもそもユダヤ教典=旧約聖書は古代イスラエル民族の文学全集とでもいった性格をもっており、歴史書、教訓詩、恋愛詩、説話の類を取り込んでいる。旧約でも新約でも『外典』や『偽典』と呼ばれる周辺文書があるし、キリスト教では古代の哲学的な指導者が記した書物――アウグスティヌスの『神の国』など――や戒律書――修道院の開祖聖ベネディクトゥスの書など――もある。ユダヤ教では、『律法』(旧約の中のモーセ五書)やそれに付加されたさまざまな口伝の訓戒や規則について、古代の学者たちがさまざまに論じた結果をとりまとめた百科事典並みに大きいタルムードと呼ばれる書物があり、ラビたちはこれをひもといて聖書を解釈し、人々の指導に役立てている」と述べます。
最後に、著者は「教典・準教典のこうした広がりを見ていると、『聖書』『コーラン』『仏典』『ヴェーダ』といった教典と名指された文書はただそれだけで成立しているものではなく、周辺の文脈込みで機能してきたことが分かってくる。そうした文脈の中には教団組織もあれば歴史的環境もある。生物が周辺環境から切り離せないというエコロジー(生態学)に例えて、『教典のエコロジー』のようなものを語ることもできるだろう」と述べるのでした。
 「サンデー毎日」2017年10月8日号
「サンデー毎日」2017年10月8日号
わたしは、世界の聖典や教典とは「こころの世界遺産」であると考えています。2017年の7月9日、福岡県宗像市の沖ノ島が「神宿る島、宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産の1つとして、ユネスコにより世界遺産に登録されました。地元ではかなり盛り上がりました。地元といえば、わたしは、北九州市の門司港にある日本唯一のミャンマー式寺院「世界平和パゴダ」が世界遺産になることを願っています。今年、国の登録有形文化財(建造物)にはなりましたが、本当は世界遺産に登録されるべきだと考えています。世界遺産には、遺蹟や聖地などの「場所」、寺院や神殿などの「建物」のイメージが強いですが、わたしは「こころの世界遺産」というものがあってもいいのではないかと思っています。というのも、人類の歴史において、多くの人々の「こころ」に対して大きな影響を与え、現在も続けている人物や書物に深い関心があるのです。
 『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)
『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)
以前、『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)という本を書いた。同書ではブッダ、孔子、老子、ソクラテス、モーセ、イエス、ムハンマド、聖徳太子の8人を取り上げ、その生き様、考え方、そして共通点などについて詳しく述べました。人類に影響を与えた人物には、8人の聖人以外にも、古今東西の英雄がいます。しかし、彼らの築いた帝国や王国や王朝や幕府は今では存在しません。彼ら英雄の影響力は現在進行形ではないのです。聖人たちの教えは、仏典、『旧約聖書』『新約聖書』『コーラン』『論語』『老子』などに残され、世界中の人々の「こころ」に良き影響を与え続けます。
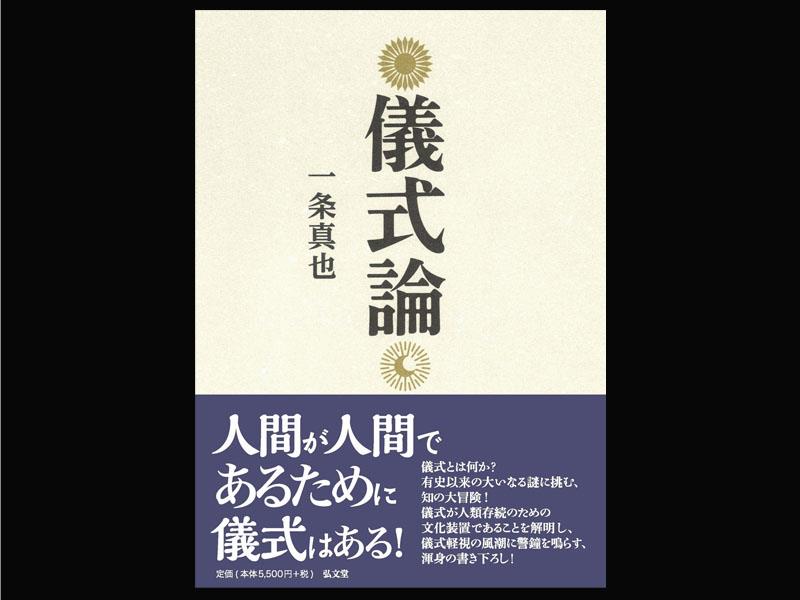 『儀式論』(弘文堂)
『儀式論』(弘文堂)
これらの書物は「こころの世界遺産」と呼べる人類の宝であり、世界平和に通じる「教養」を育みます。「こころの世界遺産」を読むことは大切です。わたしは、これからも「こころの世界遺産」に広く目配りすることを心掛け、いずれは『儀式論』(弘文堂)の姉妹本となる大著『聖典論』を書きたいです。その意味でも、本書『聖書、コーラン、仏典』は非常に参考になりました。著者は上智大学グリーフケア研究所の島薗進所長とも懇意であり、『はじめて学ぶ宗教』(有斐閣)という共著も出されているそうですので、ぜひ一度お会いして、聖典や教典について語り合ってみたいです。