- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2068 プロレス・格闘技・武道 『わが心のプロレス』 高木恭三著(東京図書出版)
2021.09.08
7日の朝、会社の健康診断を受けました。最後に受けた胃の検診の技師の方が当ブログを愛読されているそうで、「プロレスの記事、良かったです!」と言われました。やはり嬉しいものですね。ということで、今回はとっておきのプロレス本を紹介したいと思います。その本は、『わが心のプロレス』高木恭三著(東京図書出版)。いわゆる昭和プロレスへの愛について語った本ですが、素晴らしい内容でした。昭和プロレスの本を読み尽くしたと自負しているわたしも気づかなかった視点が多く書かれており、勉強になりました。著者は、愛媛県津島町(現宇和島市)生まれ。宇和島東高校、京都府立大学文学部卒業。愛媛県の公立中学校の社会科教員として35年間勤務。2019年定年退職。現在は塾の講師や中学校の教育活動支援員として活動。趣味はプロレスの他に釣り、畑仕事、書道、酒場放浪だとか。これまで、その存在をまったく知らなかった「プロレスの語り部」の出現に、わが胸は高鳴りました。
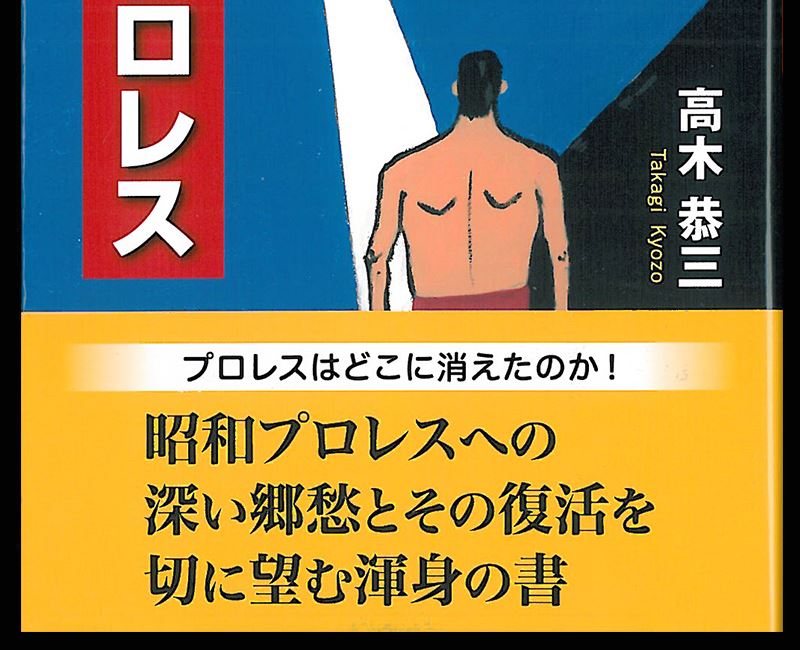 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には、「三菱洗濯機」や「三菱冷蔵庫」と側面にかかれたリングぬ向かう長身のプロレスラー(明らかにジャイアント馬場)の後ろ姿のイラストが描かれています。帯には、「プロレスはどこに消えたのか!」「昭和プロレスへの深い郷愁とその復活を切に望む渾身の書」と書かれています。
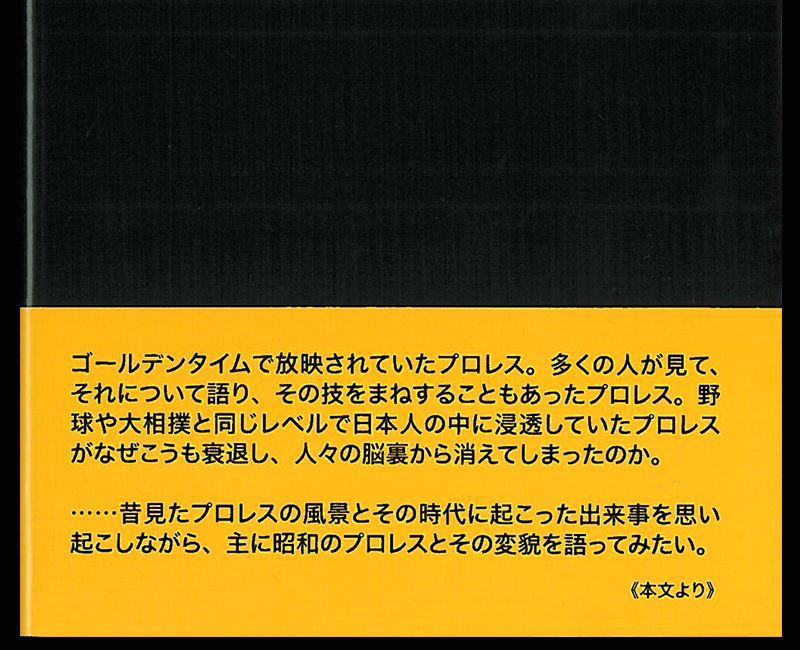 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「ゴールデンタイムで放映されていたプロレス。多くの人が見て、それについて語り、その技をまねすることもあったプロレス。野球や大相撲と同じレベルで日本人の中に浸透していたプロレスがなぜこうも衰退し、人々の脳裏から消えてしまったのか。……昔見たプロレスの風景とその時代に起こった出来事を思い起こしながら、主に昭和のプロレスとその変貌を語ってみたい」と書かれています。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「はじめに」
第1章 日本プロレス
第2章 国際プロレス
第3章 新日本プロレス
第4章 全日本プロレス
第5章 UWF系
第6章 PRIDE(プライド)
「おわりに」
第1章「日本プロレス」では、プロレスラーの年齢について、著者は「種目によっても違うが、スポーツ選手の年齢は30代までだと思う。正式な意味でスポーツとは呼べないプロレスもまた、そのピークは30代まででそれを過ぎれば引退し、後進に道を譲るというのが正しい形ではないか。実際の年齢はもう少し上だったという説もあるが、力道山は30代後半で亡くなったことで選手生命を絶たれた。力道山亡き後、日本のプロレスはなくなっていくのではないかと言われたこともあったが、豊登を経て、馬場、猪木と継承され、昭和40年代前半は人気を継続した。ほぼ馬場と同じ時代に全盛期を誇った大相撲の大鵬やプロ野球の長嶋茂雄は、僕が中学生から高校生にかけての頃、30代で引退している」と述べています。
しかし、馬場は60歳まで、猪木は50代を過ぎてまで現役を続けたとして、著者は「肉体的にはとうにピークを過ぎた後も、老いた姿を僕らに見せ、悲しい気持ちにさせていった。潔く、30代末か40代初めに引退していたならば、プロレスはその後衰退の道を歩まなかったかもしれない」と述べます。また、著者は今も前田日明のファンだそうですが、それは彼が衰えたとはいえ、まだ前田日明の姿をかろうじて保っていた時にスパッとやめたことにあり、そしてその後復帰のオファーを断り今に至っていることにあるとして、レスラーの正常な新陳代謝をしていかなかったことが、結果的にプロレスというジャンルの凋落を招いたと分析しています。わたしも、まったく同感です。
プロレスは、お互いの了解があるゆえに、繰り出す技が決定的なダメージを与えないようにしています。中には、寸止めで本当には当たっていないという人もいますが、そうは思わないという著者は、「映画やドラマのようにもし寸止めであるならば、プロレスが日本に輸入された初期の段階で人々は見限っていただろうと思う。ある程度の力で、急所ではない鍛えた場所を打つ、受け身がとれるように投げるということが基本ルールとしてある。演出効果を高めるため、流血することも多々あるが、前田対藤波戦のような偶然にキックが当たり大量の出血をした場合を除いて、出血してもそれほど問題ではないところ(額など)を傷つけることも基本ルールだ」と述べます。
第2章「国際プロレス」では、国際プロレスの新旧エース対決としてのストロング小林対ラッシャー木村戦に言及した著者は、「プロレスは相手の技を受けることを前提としてはいるが、いつもそうではなくて、時には相手の技をすかしたり、受けることを拒んだり、うまく技がかからなかったりする場面が必要だ。僕はそれを両者間の『摩擦』と呼んでいる。きれいに技が決まる爽快感がプロレスの魅力だが、格闘技のようにそう簡単には技が決まらない困難さを時には見せてくれる場面があることで、プロレスの魅力はさらに強くなると僕は思っている。僕が現在のプロレスに興味がないのは、『摩擦』がないからだ。その意味で、小林対木村戦は、エースの座を争う闘いにしては『摩擦』が少なかったように思う」と述べています。
第3章「新日本プロレス」では、アントニオ猪木について、著者は「その言動は大変興味深く、時に哲学的であるとさえ思う。彼がこれまで語ってきた言葉は実践や経験に裏付けられたもので、他の著名な文化人たちの言葉と同レベルの輝きや重さをもって、僕の心に響いていた。馬場と比べて、自分を強くアピールしようとする点や大風呂敷を広げるような面は鼻につくところもあるが、世俗的でないことは強く感じる。金とか物とかにこだわるところなく、凡人の理解の範疇を超えている面がある。一時、政治家であったが、委員会での答弁等を見ても、他の政治家と比べて経験値が格段に上だという印象をもっていた。バラエティ番組での対応を見ても、人を惹きつける何かを持っている稀有な人物である。最近、元気がなくなっているので長生きしてほしいと心から思っている」
新日本プロレスを代表するセメントマッチとして、”新格闘王”前田日明と”大巨人”アンドレ・ザ・ジャイアントのノーコンテストになった一戦があります。この試合について、著者は「後に行われる総合格闘技の試合において、身長が高かったり、体重があったりする選手が必ずしも強いとはいえないという事実を僕らに教えてくれた。2メートル以上あったり、体重が150キロ以上あったりする選手はスタミナがなかったり、動きがどうしても緩慢になったりして、結果を残せないいくつかの例を見てきた」と述べています。
続けて、著者は「プロレスラーのルー・テーズにしてもダニー・ホッジにしても、総合格闘家のヒョードルにしてもアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラにしても身長は180センチから190センチくらいで体重は100キロ前後のサイズである。レスラーの中でも並外れて大きなアンドレが強いというのは、ある意味プロレス的発想で、それは馬場にもいえる。寝かせてしまえば大きさは関係ないというのが本当のところではないか」と述べるのでした。
新日本プロレスの最後の黄金期を支えたレスラーに「闘魂三銃士」の武藤敬司がいますが、著者は「猪木だったか、誰かも言っていたが、武藤によって、それまでの日本のプロレスの形は変えられ、今のプロレス、WWE的な完全にショー化したプロレスに変わっていった。狭い範囲のファンには受け入れられるが、日本人の多くの大衆を引きつけて、ある影響力を持っていたプロレスはすたれていった。今のプロレスを見ると、武藤が披露していたプロレスのスタイルをさらに進化させて、より軽く、格闘技色を薄く、さらりとさせて、人間の持つ情念みたいなものをなくし、マンガチックにしているように見える」と述べています。
続けて、著者は「そうした中で、無骨ながら、昔のように道場での強さを追求しながら、まっすぐにプロレスに向き合っていたのが橋本のような気がするのだ。順応性に乏しく、人間関係作りが下手で、長州などと対立しながら、自分らしさを追求していった新日本最後のリアルプロレスラーが橋本だと僕は思う。猪木の持っている魂を継承し、猪木の匂いを持っていた最後のレスラー、橋本。その点で前田に少し似ているところがある」と述べます。わたしも、まったく同感です。”破壊王”橋本真也が”暴走王”小川直也に連敗したときが、ストロングンスタイルを標榜した新日本プロレスの「終わりの始まり」だったと思います。
橋本を完膚なきまでに叩きのめした小川はそんなに強かったでしょうか。著者、「その後の小川のプライドの試合、たとえばヒョードルや吉田秀彦との試合を見ると、小川はそれ程ハートの強い選手ではないということがわかる。だから、あの時に橋本がもう少し覚悟を決めて、プロレスの範疇を超えた反撃をしていたら、案外、小川はあっさりと萎えていった可能性もあった。それを考えるとあの結末は残念だった」と述べます。伝説の「1・4橋本vs小川」が著者が本気で見た最後の試合だそうですが、「その後まもなくして、小川との再戦にも敗れた橋本は新日本を去り、自分の団体を作るが、40歳という若さで亡くなってしまう。もうあれから15年以上経つと思うと不思議だ。橋本が亡くなった後、猪木の魂を継ぐレスラーはいなくなった」と述べるのでした。
第5章「UWF系」では、第二次UWFでの前田対船木戦が取り上げられます。1990年(平成2年)、船木は前田と初めて対戦。2回試合を行い、2回とも前田の勝利に終わりました。著者は、「新生UWF時代の前田のベストバウトはこの船木戦だと僕は思う。その試合は久々におもしろい前田の試合だった。船木は掌底などすばやい攻撃で前田を窮地に追い込んだ。後のパンクラス時代の攻撃に比べれば、またまだ甘さのあるものだが、その動きはとても新しく見えた。その攻撃に対して前田はフラフラになりながらも、ここ一番の踏ん張りを見せて、最後は首締めで逆転して勝利を収めた。地力の面ではまだまだ、前田と船木には差があると思わせた試合だった」と述べます。
しかし、その映像を見た時に、著者は「前田が今まで一番いい姿形をしていたと思っていたが、船木と同じ画面に映った時に、船木の方がかっこいいなと思ったのだ。ある時期、猪木と前田と比較した時に前田の方がかっこいいと思ったように、この時の船木に、後のパンクラス時代ほどの身体や動きのシャープさはまだなかったが、見た目のかっこよさは前田や高田を上回っていたように思う」と述べます。この著者が指摘した「見た目のかっこよさ」がプロレスラーの重要な要素であるというのは盲点でした。確かに、そうだと思います。
ちなみに新生UWFの頃は肥満気味だった髙田延彦はUWFインターナショナルを旗揚げしてエースとなってからはシェイプアップしました。著者は、「高田というレスラーが最も輝いていた時期はこの頃だった。身体つきも以前より締まり、紫色のトランクスをはいたその姿は、パンクラスの船木に負けない美しさがあり、貫禄・風格を感じさせた。完全に同時期に前田を上回っていた。その姿形のよさは、コンディションの良さを示していた。やがて武藤と試合をして敗れるまでの期間は、日本の格闘技界で最も輝いていたのは高田だ」と述べるのでした。
新日本プロレスでは、前田は猪木より輝けませんでした。また、新生UWFでは、船木は前田より輝けませんでした。このことについて、著者は、「プロレスの衰退した原因の1つに新陳代謝が正常に行われないということがあげられる。真の実力によって序列を決めないシステム、つまり本当は強いのにその実力に見合ったポジションや報酬を得ることができない体制が、選手間のトラブルの原因となり、離合集散を繰り返してきた。新生UWFはそうしたプロレスの矛盾を改善して、やや衰えの見える前田から高田や船木にエースの座をかえるなど、実力に見合った地位の確保、マッチメイクをする団体となる可能性があった。新日本、全日本に並ぶ、格闘色の強いプロレス団体として、共存共栄を図れば、プロレス人気がこうも下降することはなかったかもしれない」と指摘しています。
新生UWFは、3派に分裂しました。その根本原因は前田の人間関係作りに問題があると想像しつつ、著者は「僕は、前田のストレートな物言い、信じたらトコトン進んでいく姿勢や時には激怒して人に当たったりする熱いところが大好きなのだが、周囲にいる者にとってはそれを嫌悪し、憎悪する者も出てくるのは想像できる。安生や宮戸、あるいは後の長井満也や田村などもその中に入るかもしれない。調和的な人間では全くなく、好き嫌いが激しく、人を攻撃したり排したりすることもある前田の一面が、組織の長としての資質に欠けるところがあった結果の出来事だったのかもしれない。振り幅が大きく、激烈な感情の持ち主で、他にない新しい考え方を持つ前田の生き方が前田たる魅力なのだが、人によってはそれを絶対に受け入れられないと捉える人もいて、多くの敵を作ってしまうのも前田の1つの側面であった」と述べていますが、前田への深い愛情を感じます。
新生UWFから藤原組を経て、リアルファイト団体であるパンクラスを立ち上げた船木は、2000年5月26日に東京ドームでヒクソン・グレイシーと戦い、敗れます。著者は、「船木は死ぬ覚悟でリングに上がったと言う。負ければそれは死と同じだとも。僕はそれを、まだ31歳に過ぎない船木の驕り、視野の狭さから来るものだと思っている。短絡的に物事を決めようとする若年層にありがちな判断だと。船木は、あのヒクソン戦の敗北から、本格的な総合格闘技の選手へと変貌していくべきだった。年齢的にもそれが可能だった。ああいう大舞台で試合をしたプロレスの選手は、高田と桜庭、藤田しかいない(永田裕志もいるが、彼の場合は試合があっけなさすぎて数に入れるのは抵抗がある)」と述べています。非常に的確な意見であり、感服しました。
あの試合から後、プライド等のリングにあがり、ヒクソン以上の実力のある選手、たとえばヴァンダレイ・シウバ、ミルコ・クロコップ、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、あるいは吉田秀彦などとの試合を僕は見たかった。船木は2007年(平成19)年に復帰するまでの7年間をそういう時間に使っていたならば、おそらく桜庭以上の人気を博したのではないか。船木の持つスター性があれば、日本人選手のエースとして、UWF系レスラーを支持する僕たちの思いをプライドのリングで実現してくれたのではないか。船木の2000(平成12)年の引退は残念としかいいようがない。船木は今もプロレスを続けているが、一番輝いていた時はこのパンクラス時代だった」と述べます。これまた著者の卓見に感服です。
新生UWFが崩壊して30年が経ちますが、21世紀になってからの総合格闘技の数々の試合よりも、1980年代から1990年代にかけての前田や高田や船木などの試合の方を鮮烈に記憶しているという著者は、「彼らは、馬場や猪木が作った古いプロレス界を本当の強さを求めて、変革しようと試みた。数々の挫折や分裂、妨害を経験しながらも自分の道を突き進んでいった。総合格闘技の隆盛の時代、プロレスラーの中で参戦に手を挙げたのはほとんどがUWF系であった。彼らの多くは敗れることが多かったものの、彼らの参戦があったからこそ、ヒクソンをはじとした選手が脚光を浴び、プライドが注目され、総合格闘技というものが1つの大きなジャンルとして根付いていたのだ。プロレス界のパイオニアだったUWFは消えてしまったが、我々の心の中には輝いていたあの頃の風景が今もしっかりと残っている。前田を筆頭に高田や船木、安生、田村などのUWF戦士は総合格闘家ではない。総合格闘技もできるプロレスラーであったのだ」と述べます。格調高い名文であり、これを読んだわたしの胸は熱くなりました。
第6章「PRIDE(プライド)」では、プライドで試合をした日本人の中で最も強かった選手といえば、桜庭和志や藤田和之の名を挙げる人が多いですが、著者は吉田秀彦だといいます。柔道でオリンピックの金メダリストであったという身体能力と精神的な強さの面で吉田がNo.1だったとし、著者は「ああいう舞台で柔道の強さを見せつけた初めての選手かもしれない。実際は強かった木村政彦やヘーシンクやルスカなどがプロレスの試合の中で、その真価を発揮できぬままで終わった歴史を振り返る時、真剣勝負の総合格闘技の試合の中で世界レベルの柔道家の強さを世に知らしめたのが吉田だ。そう簡単には倒されない、倒して寝技になったら決めてしまう力と、立っての打撃でも堂々と応戦する胆力が吉田には備わっていた」と述べ、さらに「吉田が完敗したのはミルコぐらいなものだ。シウバともいい勝負をして、少なくとも桜庭よりは拮抗した試合内容だった。特に吉田の強さを示した試合は、田村戦と小川戦だ」と指摘しています。
総合格闘技の世界的な中心となったプライドには、一攫千金を夢見て、多くのまだ見ぬ強豪が集結してきました。著者は、「柔術、レスリング、柔道、キックボクシング、ボクシングなど腕に覚え有りの名もなき強者たちの試合ぶりが新鮮だった。かつての日本プロレス時代にアメリカから多種多様なレスラーたちが来ていたように」と回想します。しかし、プライドは2007年(平成19年)4月の「プライド34」を最後に、この年の10月に消滅したのでした。著者は、「大リーグやNBAに興味がないのと同様にUFCに魅力を感じなかった。その後、ドリーム、戦極、RIZINなどができたが、かつてのプライドが放った総合格闘技の輝きは取り戻せないで今に至っている」と述べていますが、まったく同感です。わたしも、PRIDEロスからまだ立ち直っていません。
「おわりに」で、著者は「今のプロレスラーは、一概にすべてのプロレスラーとはいい切れないが、とても軽い印象を受ける。みんな同じような動きで、そこにプロの深さを感じることができない。立ち技のオンパレードで地味な見えにくい寝技の攻防がカットされ、安易な表現方法で観客に媚びを売っているように見える。両者に摩擦感や、技を仕掛ける困難さがなく、プロの技術の攻防を見ることが少ない。大相撲や野球は、以前に比べれば様々な面で派手になり、大きく変わった部分もあるにはあるが、教護としてやっていることはほとんど変わっていない。サッカーなど様々なスポーツの台頭で、大相撲も野球も以前に比べれば人気が落ちたとはいえ、プロレスのように凋落はしていない」と述べています。
なぜ、大相撲や野球は凋落はしなかったのか。それは変わらない部分、変わってはいけない部分をしっかりと維持しているからだと指摘し、著者は「プロレスの凋落は、変わってはいけない部分、つまり、『強さ』を求める、格闘技として核心の部分が欠落したことにある。リングやレスラーのコスチューム、入場曲、会場の装飾など時代の流れの中で変わるべき点は大いに変わってもいい。しかし、リングの中で行われているプロレスリングの動きを大きく変えてしまったことにプロレスが凋落した一番の原因があるのではないか」と述べるのでした。これまた大いに共感するとともに、見事にプロレス凋落の理由を喝破した著者には深く敬意を表したいと思います。
このブログ記事の冒頭にも書いたように、昭和プロレスの本は読み尽くしていると自負しているわたしですが、本書に書かれているプロレス愛、プロレスというジャンルの定義、そして個々のプロレスラーへの評価など、いずれも類書にはない味わいと鋭さがありました。ここでは新日本プロレス・UWF・PREIDEを中心に紹介しましたが、ジャイアント馬場、大木金太郎、吉村道明、上田馬之助、ラッシャー木村などについての考察にも唸りました。本書を読んで、わたしは、今や古典ともいえる村松友視氏の名著『私、プロレスの味方です』を読んだとき以来の感動をおぼえました。欲を言えば、カバー表紙のイラストは、リングに向かう馬場ではなく、伝説の前田vsアンドレにしてほしかったです。最後に、プロレス界は、なんとか著者が言うように「強さ」を取り戻してほしいと思います。”燃える闘魂”アントニオ猪木が健在なうちにプロレス界の再生を心より期待します!