- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.11.10
『昨日までの世界』上下巻、ジャレド・ダイアモンド著、倉骨彰訳(日経ビジネス人文庫)を読みました。「文明の源流と人類の未来」というサブタイトルがついています。領土問題、戦争、子育て、高齢者介護、宗教、多言語教育……人類が数万年にわたり実践してきた問題解決法を探る内容です。ピュリツァー賞受賞の世界的研究者が、身近なテーマから人類史の壮大な謎を解き明かします。全米大ベストセラーの超話題作ですが、養老孟司氏は「現代社会を深く考えるための必読書」、福岡伸一氏は「ダイアモンド文明論の決定版的集大成」と大絶賛しています。
著者は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校地理学教授。1937年ボストン生まれ。ハーバード大学で生物学、ケンブリッジ大学で生理学を修めるが、やがてその研究領域は進化生物学、鳥類学、人類生態学へと発展していく。カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部生理学教授を経て、同校地理学教授。アメリカ科学アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミー、アメリカ哲学協会会員。アメリカ国家科学賞、タイラー賞、コスモス賞、ピュリツァー賞など受賞多数。
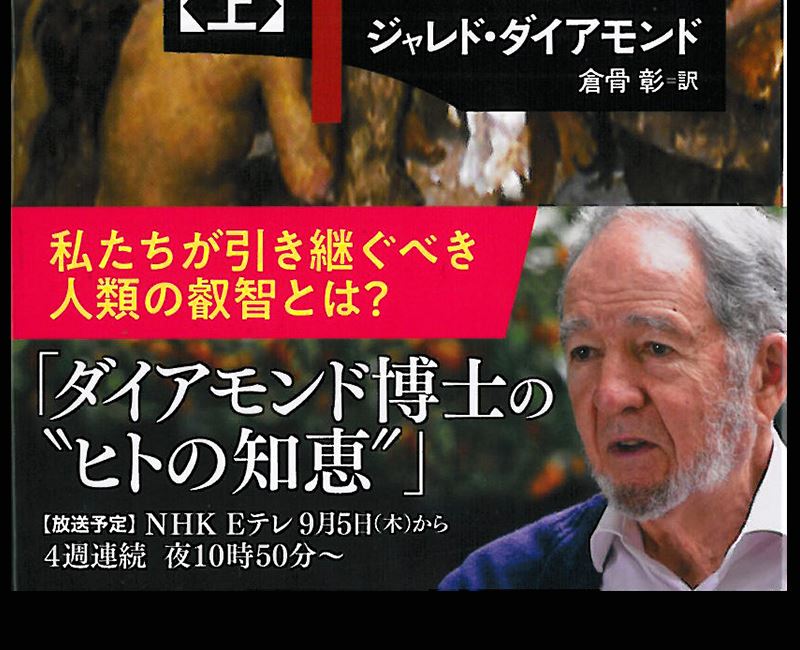 上巻の帯
上巻の帯
上巻の帯には、著者の顔写真とともに、「私たちが引き継ぐべき人類の叡智とは?」「ダイアモンド博士の”ヒトの知恵”」と書かれています。また、帯の裏には、「『これから1世紀先の学者たちはダイアモンドの3部作、『銃・病原菌・鉄』『文明崩壊』『昨日までの世界』に対し、ダーウィンの3部作と同等の評価を下すだろう』というマイケル・シャーマーの言葉が紹介されています。
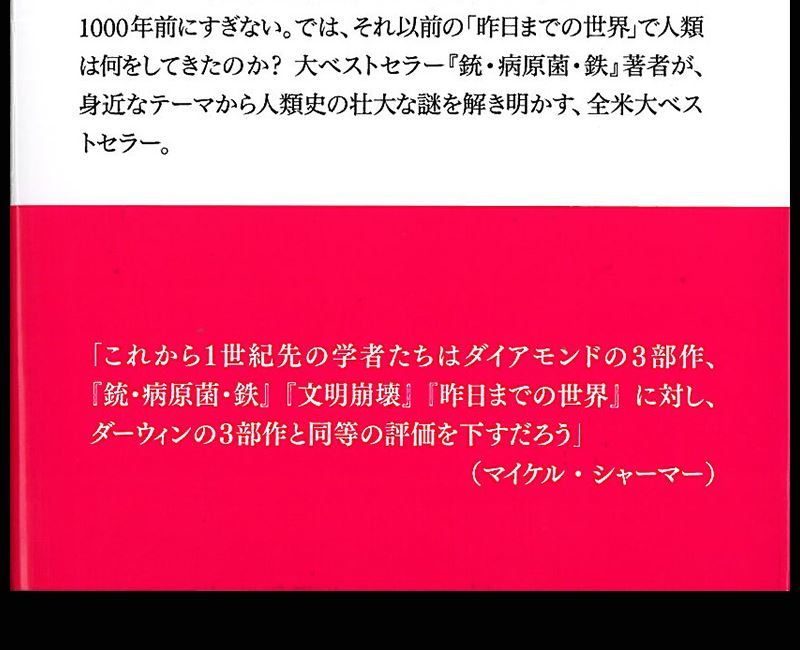 上巻の帯の裏
上巻の帯の裏
上巻のカバー裏表紙には、「600万年におよぶ人類史において、国家が成立し、文字が出現したのは5400年前、狩猟採集社会が農耕社会に移行したのも1万1000年前にすぎない。では、それ以前の『昨日までの世界』で人類は何をしてきたのか? 大ベストセラー『銃・病原菌・鉄』著者が、身近なテーマから人類史の壮大な謎を解き明かす、全米大ベストセラー」と書かれています。
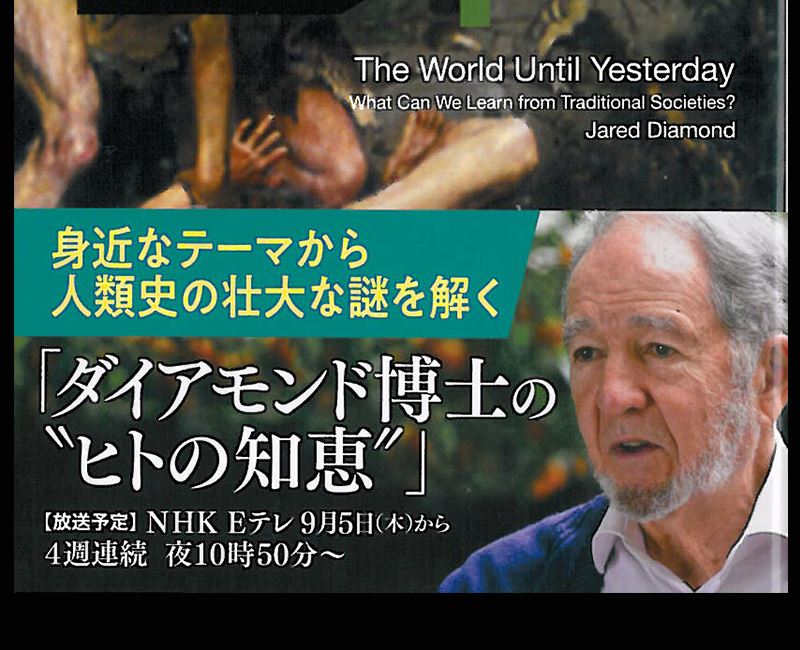 下巻の帯
下巻の帯
下巻の帯には、著者の顔写真とともに、「身近なテーマから人類史の壮大な謎を解く」「ダイアモンド博士の”ヒトの知恵”」と書かれています。また、帯の裏には、「本書はひとりひとりの人生や生活、日々の選択といった個人の興味関心に直接関係するテーマを扱っており、私の著作のなかではもっとも生活に身近な内容になっている」(「日本語版への序文」より)とあります。
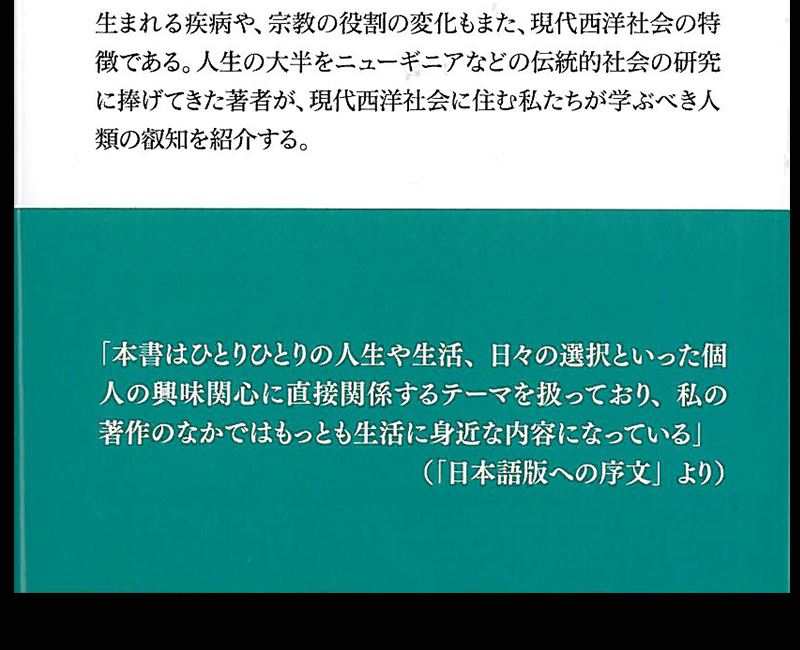 下巻の帯の裏
下巻の帯の裏
下巻のカバー裏表紙には、「現代西洋社会の特徴はインターネットや飛行機といった技術や、中央政府や司法といった制度ばかりではない。オフィス労働から生まれる疾病や、宗教の役割の変化もまた、現代西洋社会の特徴である。人生の大半をニューギニアなどの伝統的社会の研究に捧げてきた著者が、現代西洋社会に住む私たちが学ぶべき人類の叡知を紹介する」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の通りです。
【上巻】
「日本語版への序文」
プロローグ 空港にて
第1部 空間を分割し、
舞台を設定する
第1章 友人、敵、見知らぬ他人、そして商人
第2部 平和と戦争
第2章 子どもの死に対する賠償
第3章 小さな戦争についての短い話
第4章 多くの戦争についての長い話
第3部 子どもと高齢者
第5章 子育て
第6章 高齢者への対応
――敬うか、遺棄するか、殺すか?
【下巻】
第4部 危険とそれに対する反応
第7章 有益な妄想
第8章 ライオンその他の危険
第5部 宗教、言語、健康
第9章 デンキウナギが教える宗教の発展
第10章 多くの言語を話す
第11章 塩、砂糖、脂肪、怠惰
エピローグ 別の空港にて
「日本語版への序文」を、著者は「客観的にみて、日本は世界でもっとも興味深く、特徴が際立っていて、さらに成功をおさめた国のひとつである」と書きだしています。また、伝統的社会とは、人口が疎密で、数十人から数千人の小集団で構成される、狩猟採集や農耕や牧畜を生業とする古今の社会で、なおかつ西洋化された大規模な工業化社会との接触による変化が限定的にしか現れていない社会のことであると定義し、「本書は、現代の工業化社会、つまり西洋社会と伝統的社会の違いを浮き彫りにし、そこから判明する叡智をどのようにわれわれの人生や生活に採り入れ、さらに社会全体に影響を与える政策に反映させるかについて解説するものだ」と述べています。
すべての現代の工業化社会は、インターネットや中央政府といった現代的特徴と一緒に、伝統的社会の特徴も併せ持っていると指摘し、著者は「日本にも伝統的社会の特徴が残っているし、私の国であるアメリカにも同じことがいえる。実際、私のようなアウトサイダーからみると、現代の日本の『強み』の源泉は、一国のなかに伝統的な部分と現代的な部分がうまく共存していることにあると思う。さらに、伝統に新しい事柄を織り交ぜて残すものと捨てるものを選択し、みずからを革新し再発見するという能力をたびたび発揮していることにあると思う」と述べます。
プロローグ「空港にて」では、「国家とはそもそも何か」として、著者は「国家の特徴としてあまりにもよく知られていることではあるが、もっとも平等主義が進んだ北欧諸国の民主主義社会においても、市民は政治的、経済的、社会的に平等ではない。必然的にどのような国家でも、命令を発し、法律を制定する少数の政治的指導者や、それらの命令や法律にしたがう大勢の一般人が存在せざるを得ない。国民にはさまざまな経済的役割(農家、守衛、弁護士、政治家、店員など)があり、なかには他の仕事より高い収入を得る仕事もある。また、他の市民より社会的地位が高い者もいる。カール・マルクスは共産主義の理想として「能力に応じて働き、その必要に応じて受け取る」を掲げたが、国内の不平等を最小化しようとする理想主義的努力はすべて失敗に終わっている」と述べています。
また、紀元前9000年頃にようやく始まった食料生産以前には国家は存在し得ず、その後、食料生産が数千年にわたって続けられて国家政府を必要とするほど稠密で膨大な人口が形成されるまで、国家は存在しなかったと指摘し、著者は「初めて国家が成立したのは紀元前3400年前後の肥沃三日月地帯で、それにつづいて中国、メキシコ、アンデス、マダガスカルで国家が成立し、つづく1000年のあいだにその他の地域にも広がり、ついに今日では地球全体が描かれた地図を広げると、南極大陸以外の土地はすべて国家に分割されるという状況にまでなった。南極大陸でさえ7カ国が領有権を主張している」と述べます。
人間社会はどれもユニークではありますが、一般化できる異文化間の共通パターンもあると指摘する著者は、「とくに、少なくともつぎの社会の4つの側面は、相互に関係する傾向がある。それは、人口規模、生業、政治の中央集権化、社会成層である。人口規模が拡大し、人口が稠密になると、食料やその他の必需品の獲得方法は集約されやすい。つまり、移動型の狩猟採集民の小集団より、村に定住する自給農耕民のほうが1エーカーあたりの食料を多く獲得できるし、人口がさらに稠密になり、機械化が進んだ現代国家の農地では灌漑農業が集約的におこなわれ、1エーカーあたりさらに多くの食料を得ることができるようになるのである。政治的な意志決定はしだいに中央集権化され、狩猟採集民の小集団のように成員が一堂に会して討議をする形態から、現代国家のように政治的ヒエラルキーが成立して指導者たちが意思決定をする形態へ移行する。社会成層も増えるので、狩猟採集民の小集団では比較的平等主義がとられていたのに対し、大規模な中央集権社会では不平等が生じる」と述べます。
本書では、アメリカの文化人類学者エルマン・サービスが人口規模の拡大、政治の中央集権化、社会成層の進度によって分類した、人間社会の4つのカテゴリーを折に触れて使っていくとして、著者は「それはすなわち、小規模血縁集団、部族社会、首長制社会、国家である。これらの用語が定義されてから50年が経過し、その間に他の用語も提案されているものの、サービスの用語にはわかりやすいという利点がある。用語を7つではなく4つに絞り、単語をいくつもつなげるのではなく端的に一語で表現しているからである」と述べるのでした。
第1部「空間を分割し、舞台を設定する」の第1章「友人、敵、見知らぬ他人、そして商人」では、最大かつ最後のファーストコンタクト」として、小規模社会は、外界についてかぎられた知識しか有していなかったことが紹介されます。そして多くの小規模社会では、人類学上、「ファーストコンタクト」と称される、彼らの社会と西洋文明との最初の相互接触によっていきなりその状況に終止符が打たれたのであるとして、著者は「彼らを植民地支配したくてやってきた人々、彼らの土地を探査したくてやってきた冒険・探検家たち、彼らと交易したくてやってきた商人たち、彼らに自分たちの文明と宗教を伝えたくてやってきた宣教師たち――こういう人々が彼らの世界にヨーロッパからいきなりやってきた」と述べます。
そして、彼らの世界の外側に、未知の世界が存在する事実を突然つきつけたのであると指摘し、著者は「もちろん世界には、今日にいたるまでファーストコンタクトの洗礼を受けていない部族が存在する。しかしそれは、ニューギニアの奥地や南アメリカの熱帯地方の奥地に暮らすひと握りの部族に限定された話だ。そういった部族でさえ、頭上を通過する飛行機を目にしているし、すでにコンタクトずみの近隣の部族の人々が外界について話すのを耳にしている」と述べています。
「交易と商人」として、著者はこう述べています。
「現代社会においてわれわれは、お金を払って商品を購入し、それを受け取る。伝統的な取引は、この現代の方法とさまざまな点で大きく異なっていた。たとえばである。新車がほしくてやってきた客が、いつかこの新車と等価の贈り物をするから自分を信用して、いまはこの車を自分に渡してくれ、と販売担当者に告げおいて、新車に乗って走り去る。こういう取引の場面をあなたは想像できるだろうか? これは現代ではあり得ない取引である。しかし、伝統的社会では、このあり得ない取引がまったくふつうにおこなわれていた」
だからといって、伝統的な交易形態が現代の買い物のしかたとすべてにおいて異なるというわけではないとして、著者は「なかには、現代の買い物のしかたに通じる部分もあるのである。とくに、機能性があるから価値があるといったものでもなく、ただただ高額であるというステータス・シンボル的なもの、たとえば宝石やブランドものの衣服などを購入する際の取引には、多くの場合において伝統的な取引形態の特徴のいくつかがいまだにみられる」と述べるのでした。
第2部「平和と戦争」の題2章「子どもの死に対する賠償」では、交通事故で息子を殺された父親と加害者の運転手が勤務していた会社とのやり取りが紹介されます。息子を殺されたばかりの父親が加害者の雇用主と対面し、「今回のことは事故で、故意ではなかったことはわかっています。私たちは、騒ぎを起こす気はありません。ただ、息子に葬式を出してやるにあたり、援助をしていただきたいのです。葬儀の席で親族にふるまえるよう、少々のお金と食料を工面していただけませんか」と述べます。
雇用主は漠然とした約束をまじえながら、会社と従業員を代表して哀悼の意を伝えました。そして、地元のスーパーマーケットに足を運び、米や缶詰の肉類、砂糖、コーヒーなどといった生活必需品を購入し始めました。そうしている最中に加害者の運転手は偶然にも父親と顔を合わせましたが、その際も、二人の間でもめごとのようなことは一切起こらなかったといいます。賠償の儀式そのものは事故から5日目に、正式な手順にのっとって執り行われたそうです。その儀式は、加害者の会社の全社員が揃って社有車で低地人の居住区に到着するところから始まりました。一行は社有車から降りると、居住区内を徒歩で進み、ビリーの遺族の家の裏庭へと向かったのです。
「謝罪の儀式」として、ニューギニアの伝統では、哀悼の儀式においては、会葬者の頭上を覆うために何らかのシェルターが用意され、葬儀はそのシェルターの下で行われることになっていることが紹介されます。今回は、交通事故の被害者少年の遺族が防水シートを天幕として張っていて、その天幕の下に、遺族や弔問客を含むすべての出席者が並んで座ることになっていました。そして、加害者らの一行が裏庭から入ってくると、被害者のおじのひとりが彼らの座る場所を指し示し、すでにそこに着席していた遺族の人々に、別の場所に動いて席を空けるようにと告げたのです。
儀式の場では、被害者のおじが最初に話し、弔問客に謝意を述べたあと、少年の死がどれほどの悲しみをもたらしたかを語りました。つづいて、雇用主、そして他の社員が席を立ち、順番に哀悼の意を表しました。「国家の関与」として、著者は「ここまでの一連の出来事は何を物語っているのだろうか。それは、ニューギニア独自の伝統的方法によっても、他者の手にかかって人が亡くなってしまうといった問題を平和裡に解決でき、大切な人を亡くした人の悲しみや苦しみを癒すことができる、ということを示している。そして、ニューギニア独自の伝統的方法と西洋の国家社会の司法制度とは、この問題への対処が対照的に異なるのである」と述べています。
ニューギニアの伝統的な賠償方法は、以前の関係の回復に主眼を置きます。たとえ、以前の関係が「なんの関係も持たない関係」だったとしても、面倒な関係になり得るという可能性を排除するために以前の「なんの関係も持たない関係」という関係を回復したいのであるとして、著者は「実際、このような目的やその根底にある歴然とした事実こそ、ニューギニアと西洋社会とを、係争の解決方法において大きく異ならせるものなのである。たとえば、西洋社会では一般に、係争の解決において以前の関係の回復が考慮され、問題にされることはない。もともと関係らしい関係が存在していなかったり、今後も関係らしい関係を持ちたいとは思わない人間同士のあいだで係争になったりする社会だからである」と述べます。
損なわれた人間関係を回復するうえで、ニューギニア人にとって何より重要な要素は何か。著者は、「相手側に敬意を払い、相手側が精神的および感情的な被害に遭った事実を認めることである。この要件を満たすことによって初めて、そのような状況下で相手側が当然感じているだろう怒りを鎮め、以前の関係を回復することができる。そして、その人間関係の回復の確約を固めるために支払いがなされるのである」と述べています。これは、いわゆる文明国に生きる人々にとっても大いに学ぶべき点があるのではないでしょうか?
第4章「多くの戦争についての長い話」では、「伝統的戦争の形態」として、現代では、騙し討ちは外交上のルール違反とみなされ、国家間では行われていないと指摘し、著者は「いずれの国家も、外交ルールにしたがうほうが自国の利益のためになると考えており、ヒトラー政権下のドイツや日本といったところでさえも、正式に宣戦布告をすると同時に、それぞれソ連とアメリカに対する攻撃を加えている(ただし、攻撃に先立っての宣戦布告はしていない)。ただし、これは国家間での話である。たとえば、反乱勢力のような外交ルールが適用外にある集団を相手にする場合は、国家政府も騙し討ちのような行為を平気でおこなうことがある。たとえば、フランスのシャルル・ルクレール将軍は、ハイチ独立運動指導者トゥーサン・ルーヴェルチュールを騙して拘束している」と述べています。
個人間の自然発生的な争いが軍事的および組織的な戦争へとエスカレートしてしまうケースは、現代の中央集権国家の間では珍しいです。しかし、その例がまったくないわけではありません。ひとつの例が、1969年6月から7月にかけてエルサルバドルとホンジュラスとのサッカー戦争です。この両国の間では、サッカー戦争が起こる以前から、貿易摩擦や不法移民問題といったことが原因で国民感情がギクシャクしていました。そのような状況の中で、両国は、1970年ワールドカップ出場をかけて予選の3試合を戦うことになったのです。本書には、「最終戦となる第3戦が6月26日にメキシコシティでおこなわれ、エルサルバドルが延長戦の末にホンジュラスを3対2で下すと、両国は国交断絶状態に陥り、7月14日には、エルサルバドル空軍がホンジュラス領内への爆撃を開始し、それと同時に、エルサルバドル陸軍がホンジュラス領内への侵攻を開始したのである」と紹介されています。
「類似点と相違点」として、自己犠牲も、伝統的社会と国家社会の間でみられる相違点であるとして、著者は「自己犠牲という行為は一般に、現代の戦争では高貴な行動とみなされ、称賛される。しかし、伝統的戦争において、戦闘員が自己の命を犠牲にして戦ったという目撃例はない。現代の国家は、お国のために命がけで戦えと兵士たちにしばしば命じる。たとえば、敵陣の有刺鉄線に向かって突撃しろ、などと命令するのである。みずからの命を賭して仲間の命を救おうとする兵士さえいる。爆発寸前の手榴弾の上に身を投げて仲間の命を救おうとするのは、一兵士の犠牲行為である」と述べています。
第二次世界大戦中には、何千人もの日本兵が自殺攻撃によって自己犠牲を払っているとして、著者は「彼らは、最初は志願して、のちには上官からの指名によって、神風特攻隊の一員となり、ロケット推進型滑空爆弾『桜花』や、人間魚雷『回天』などに乗り込んで、アメリカ軍の戦艦めがけ体あたりしたのである。人をこのような行動に走らせるには、将来の兵士である子どもたちを幼少のころから教育し、従順な忠誠心を尊び、お国とその思想信条を守るための自己犠牲を尊ぶ人間に育て上げる必要がある。ところが、ニューギニアの伝統的社会では、このような自己犠牲があったという話を私は耳にしたことがない。ニューギニアの部族の戦士は、敵を殺害することと、自分が生き延びることの両方を目標に戦う」と述べます。
国家の軍隊が捕虜を殺害しないのにはわけがあるといいます。それは、国家には、食料に余力があって、捕虜を食べさせることができるからであるとして、著者は「人的にも余力があって、人員を割いて捕虜を監視し、彼らに強制労働させることができるからである。しかし、伝統的社会にとっては、これはできない相談である。それゆえ、伝統的社会の戦士たちは捕虜を生かしておかないのである。そして、伝統的社会の戦士も、敵に捕まれば殺されることがわかっているので、敵に包囲され、負け戦が明々白々になろうと、降伏だけは絶対にしない」と述べています。
「戦争の究極の要因とは何か」として、著者は「伝統的戦争の究極の要因としてもっとも頻繁に候補にあがる説明とは何か。それは、土地の獲得のためであり、漁場、原塩産出場所、採石場、労働力などの、自分たちの居住圏内では十分に手にすることができない資源の獲得のためという説明である」と述べます。また、土地と資源の不足が戦争につながるという仮説の論証をもっとも幅広く試みたのは、文化人類学者のキャロル・エンバーとメルビン・エンバーの二人であるとして、著者は「彼らは、Human Relations Area Files(HRAF〈フラーフ〉)という、文化人類学および民族学の情報分析ファイル資料をもとに、飢饉の頻度や、干ばつや霜害などの天災の頻度、食料不足の頻度を資源不足の原因の指標として抽出し、186の文化的に異なる社会の事例を比較している。その結果、これらの指標が、戦争の生起の頻度を予測する、もっとも強力な予知因子であることが明らかになった。そこで、エンバーらは、人々が戦争を仕掛けるのは、敵から資源(とくに土地)を奪い、いつ起きるかわからない将来の資源不足に備えるためであると結論づけた」と紹介します。
第3部「子どもと高齢者」の第6章「高齢者への対応――敬うか、遺棄するか、殺すか?」では、「高齢者は社会のお荷物か」として、著者は「社会が高齢者をどのように処遇しているか。この問いに対する答えは、どの伝統的社会でも同じというわけではない。伝統的社会のなかには、高齢者の社会的位置づけがフィジー人以上に高い社会も存在する。そのような社会では、高齢者に強大な権限が認められている。そして、高齢の親が成人後も子どもを支配している。高齢者が公共の財産を管理している。40歳以下の男は結婚できない。だが一方で、伝統的社会のなかには、高齢者の社会的地位がアメリカのそれより低い社会もある。そのような社会では、高齢者は餓死したり、遺棄されたり、高齢であるがゆえに殺害されたりする。もちろん、高齢者の処遇のバリエーションは、同一社会のなかでも認められる」と述べています。
「何が高齢者介護に期待されているのか」として、著者は「高齢者の世話は理想として、いかにあるべきであり、だれがになうべきなのだろうか。これはナイーブな問いかけにほかならない。そして、その答えでさえ、完全なものではあり得ない。しかし、このナイーブな問いかけのうちに、高齢者ケアの手掛かりを求めることができる。理想的な高齢者ケア論のどこに、破綻の原因があるのかを考察することができるからである。前記の問いに対する楽観主義的理想論はおそらく、つぎのようなものだろう。親と子は互いに愛し合うものである。また、愛し合うべきものである。それゆえ、親は、子どもの成長、発達のために最大限の努力をいとわない。子どものためならいかなる犠牲も惜しまない。子どもは子どもで父母を敬い、敬愛し、自分を育ててくれた親の情けを忘れない。ゆえに、子どもというものは、世界のどこにおいても、自分を育ててくれた親が歳を取れば、自分が手厚く介護し、面倒をみたいと思っているに違いない」と述べます。
「なぜ親を遺棄したり殺したりするのか」として、著者は「子ども(および若い世代全般)が親のケア(および高齢の世代全般のケア)を放棄してしまう。棄老してしまう。あるいは、殺害してしまう。このような社会とは、一体、どのような社会なのだろうか」と読者に問いかけ、このような行為の報告例の多くは、高齢者の存在が深刻な足手まといとなる社会における事例であり、その場合、理由は以下の2通りです。著者によれば、1つは「移動型の狩猟採集民のあいだにみられる理由であり、それは、野営地からつぎの野営地へ移動する彼らの生活形態に起因している。彼らには荷役動物がおらず、荷物を運ぶのは何もかも人頼りである」といいます。
移動型の狩猟採集民の場合、赤ん坊は人が背負って運びます。集団と同じ早さで歩けない4歳以下の子どもも、だれかが背負って運びます。武器、道具、その他の所有物、あるいは、携帯用の食料や水といったものも、人が運ばなければなりません。著者は、「そういう状況のなかで、これらの子どもや荷物に加え、自力歩行が困難な高齢者や病人を帯同させて、野営地からつぎの野営地へ移動するとなると、それは集団にとって大変な負担であり、とてもできない相談なのである」と述べます。
親のケアの放棄、棄老、親殺しといった行為がみられるもう1つの環境は、北極圏や砂漠地帯などであるとして、著者は「このような土地柄で暮らす集団は、ぎりぎりの食料しか入手できないほどの深刻な食料不足にときおり見舞われる。しかも、集団全体の食い扶持をまかなうに足る食物の備蓄ができないため、食料不足の時期には、社会にとって用済みの人間や、食料の生産や獲得に貢献できない人間といった少数の弱者を犠牲にしてでも、集団の多数の生き残りをはからなければならない、という事情が存在する」と述べます。
それでは、高齢者はどのようにして遺棄されるのでしょうか。高齢者は、間接的な方法から直接的な方法まで、5種類の方法で遺棄されるとして、著者は「もっとも消極的な方法は、高齢者をまったくケアせず、ひとりで放置し死なせてしまう、という単純な方法である――極端な場合は、存在をまったく無視し、何もせずに放置する。ほとんど食事を与えず放置する。衰弱したまま放置する。勝手に放浪し、徘徊するのを放置する。下の世話を一切せず、不衛生な状態に放置し死なせる、といった方法がみられる。そして、これについては、北極圏のイヌイット族、北アメリカの砂漠地帯のホピ族、南アメリカの熱帯地方のウィトト族、オーストラリアのアボリジニのあいだで報告例がみられる」と述べます。
高齢者遺棄の2つめの方法は、集団が野営地から野営地に移動する途中のどこかで、意図的に置き去りにしていく方法です。これは、スカンジナビア北部のラップ族(サーミ人)、カラハリ砂漠のサン族、北アメリカのオマハ族とクテナイ族、南アメリカの熱帯地方のアチェ族のあいだで報告例があるそうです。3つめの方法は、自発的に自殺をさせたり、自殺を教唆する方法です。これは、シベリアのチュクチ族やヤクート族、北アメリカのクロウ族、イヌイット系部族、古代スカンジナビア人のあいだで報告例があるそうです。具体的には、崖から飛び降り自殺、小さな船をあつらえてひとりで大海原に漕ぎ出す入水自殺、戦場で殺され戦死という名の自殺の道を選ぶ、といったことです。
自殺幇助が許されたり、嘱託殺人が許される社会もあります。これが高齢者遺棄の4つめの方法であり、自殺に手を貸す人がいるという点で3つめの方法とは異なります。5つめの方法は、犠牲者の同意や協力なしに乱暴に殺害する方法です。著者は、「これはさまざまな社会でおこなわれていた方法である。具体的には、人が絞殺される、生き埋めにされる、窒息死させられる、刺殺される、頭を斧で割られる、首や背骨を折られるといったことが起こる」と述べています。
「社会の価値観」として、高齢者への敬意が特に強く表れているのは、父母、先祖を敬う儒教の教えが浸透した社会であると紹介されます。著者は、「儒教の教えは伝統的に、中国、韓国、日本、台湾などで広くみられた。実際、日本では憲法改正にともなって1947年に教育基本法が改正されるまで、儒教の考えかたが盛り込まれた教育勅語に依拠していた」と述べています。日本人のわたしから見て、この記述はいささかアバウトな印象もありますが。
中国では1950年に婚姻法が改正されるまで、明文化されていました。著者は、「儒教の教えにおいて、子は、両親に絶対服従すべしとされる。そして、親にしたがわないこと、親を尊敬しないことは、人間として卑しいおこないであると考えられた。実質的に、子ども(とくに長男)は、年老いた両親の世話をする、というきわめて重要な義務を負うのである。父母、先祖を敬う理念は、現在も東アジアで実践されている。そして、最近まで、中国では、高齢者のほぼすべてが子どもや家族と同居していた。日本では、4分の3が子どもや家族と同居していた」と述べています。
アメリカ社会については、著者は「独立性、個人主義、自助、プライバシーといったアメリカ特有の価値観が複雑にからみあった社会である。そして、アメリカ人の価値観にとって、高齢者ケアの享受というものは、これらのすべてに反する行為なのである。アメリカ社会は、独立した存在ではない赤ん坊に対するケアの必要性を認めながら、独立独歩の生活をしてきた高齢者が依存生活へ逆戻りすることはよしとしない」と述べます。また、「最後に紹介するアメリカ特有の価値観は若さへの礼賛である。アメリカではまさに、この礼賛が高齢者への偏見の源となっているのである」とも述べています。
「高齢者への対応は改善したか、悪化したか」として、著者は「現代社会における高齢者を取り巻く状況は、伝統的社会のそれと比べ、どのように変わったのだろうか。この問いに対する答えは、劇的に改善された部分もあるが、悪化がみられる部分のほうが多い、ということになる」と述べます。改善がみられる部分は、まず、高齢者の平均余命が延びたことです。高齢者の健康状態がはるかによくなったことです。高齢者にとっての娯楽の機会がはるかに増えたことです。高齢者が子どもに先立たれる悲しみを経験することがはるかに減ったことです。そして、これらはすべて、人類史上かつてなかった出来事です。
著者は、「たとえば、平均寿命であるが、一番長生きなのは日本人の84歳である。そして、先進工業諸国26カ国の平均は79歳である――この79歳という数字は、伝統的社会の平均寿命のほぼ倍である」と述べます。また、「現代の高齢者は社会的に孤立する傾向にある。そして、その背景にあるのは、現代の高齢者が、利用価値という面で、昔より低くみられているという現実である。高齢者の利用価値が下がってしまった理由はつぎの3つである――現代人の識字能力の高さ、正規教育の普及、急速な技術革新」と述べるのでした。
第4部「危険とそれに対する反応」の第7章「有益な妄想」では、「危険に対する姿勢と『建設的なパラノイア』」として、著者がニューギニアに野外視察に行き始めた頃、1週間を過ごすキャンプのために、見事な巨木を見つけた彼はニューギニア人の助手たちに「あの巨木の苔むした幹の脇のところにテントを張るので、準備にとりかかって下さい」と言いました。しかし、彼らはひどく動揺し、「あの巨木の幹の脇で寝るのは嫌だ」と言ったのです。「あの巨木はすでに枯れて、死んでいる。だから、我々がテントで夜、眠り込んでいるあいだにわれわれの上に倒れ込んできて、われわれを殺すかもしれない」というものでした。実際に巨木はすでに枯れていましたが、この1週間の間に倒壊する可能性は限りなく低いです。それでも、少しでもリスクがあれば冒さないというのが伝統的社会の知恵なのでした。
この「有益な妄想」を学んだ著者は、その後は、濡れると滑る浴室でのシャワー、電球の交換で脚立に上がるとき、階段の上り下り、つるつると滑る歩道を歩いたりするときに気をつけているそうです。著者いわく「1回あたりのリスクは低いが、生活のなかで頻度の高い行為であり、用心深く対応することに越したことはない」というわけですが、そんな彼が最も用心深く対応する機会こそ、車の運転なのでした。「有益な妄想」は「建設的なパラノイア」とも言い換えられていますが、想定外の出来事の連続である人生においては素晴らしい知恵であると思います。過度の心配性もストレスを溜め込みますが、つねに最悪の事態を想定して生きることは、最悪の事態を回避する最大の方策ではないでしょうか? それは車の運転においても、新型コロナウイルスの感染対策においても、すべてのリスクに対応しうる人類の叡智なのです。
「有益な妄想」あるいは「建設的なパラノイア」について、著者は以下のように述べています。
「現代の西洋社会における危険と、伝統的社会における危険は同じではない。まず最初に、種類が違う。われわれにとっての危険とは、自動車事故やテロ、心臓発作といったことである。そして、伝統的社会で暮らす人々にとっての危険とは、たとえば、ライオンに遭遇する可能性や、敵部族の人間に出遭う可能性、眠っている自分の上に木が倒れ込んでくるといった可能性である。そして、もっと重要な違いは、危険の度合いである。危険の度合いは、伝統的社会で暮らす彼らよりも、現代の西洋社会で暮らすわれわれのほうがはるかに低いのである。たとえば、われわれの平均寿命は彼らのそれよりも2倍も長い。この事実は、1年ごとの平均的な危険度において、彼らのほうがわれわれよりも2倍以上、危険にさらされる可能性が高いということを示唆している。もうひとつの重要な違いは、われわれアメリカ人が事故に遭って怪我をしても、たいてい治療できる点だ。しかし、ニューギニアの奥地で危険の犠牲になったら、それが最後、一生涯残る障害になるか、命を落とす可能性が高いのである」
第8章「ライオンその他の危険」では、「伝統的社会に特徴的な病気」として、集団感染症が狩猟採集民や小規模農耕民にみられないのは、免疫があるからではないと指摘されます。著者は、「感染症が継続的に存続するのに必要な数の宿主人口がいないだけの話である。そのような小規模集団の人々が外の世界の人々と接触すると、悲劇的なことが起こる。人々が集団感染症の犠牲になりやすいのである。集団感染症のなかには、子どもよりも大人の致死率が高くなるものがあるため、幼少期に感染機会のなかった小規模集団の人々が犠牲になりやすい。たとえば、麻疹である。先進諸国では、(最近まで)すべての人が子どものころに麻疹にかかっていて、大人な免疫を持っている。しかし、外の世界から孤立した環境で暮らす小規模集団の狩猟採集民は大人も麻疹ウイルスにさらされたことがなく、免疫がないため、病原体が持ち込まれるや病気にかかって死亡する人が多いのである。イヌイット族やアメリカ先住民、オーストラリア大陸のアボリジニの人々などに関しては、ヨーロッパ人との接触を通じて伝染病が持ち込まれ、その結果、集団の人口がほとんど消滅してしまったという恐ろしい話が枚挙にいとまのないほど存在する」と述べます。
第5部「宗教、言語、健康」の第9章「デンキウナギが教える宗教の発展」では、「宗教の役割と便益」として、本書の目的は、人間社会のあらゆる側面を考察するところにあると明かされます。つまり、人口の大小ということでは、小規模社会から大規模社会まで、歴史的な新古ということでは、古代から現代にいたる人間社会の諸側面を考察するところにあるとして、著者は「この観点からすれば、宗教がわれわれに突きつけるさまざまな疑問はとくに興味深いものである。たとえば、宗教は、現代社会において伝統的なものが衰えをみせずに存在しつづけている唯一のものである」と述べています。
また、著者は以下のようにも述べています。
「1400年から3000年以上も前に小規模で伝統的な社会で誕生した世界の主要宗教に、いまでも多数の信者が存在し、しかも誕生当初の社会よりはるかに大規模で現代的な社会で信仰が実践されている。それにもかかわらず、社会の規模が異なると、そこにみられる宗教が変わることも事実である。この事実は説明されなければならない。さらに本書の読者の方々のなかには、人生のある時期に、自身の信じる宗教(あるいは自身が無宗教であること)に疑問を抱くことがあるだろう。私もそうだった。宗教の意味するところは人により多様である。その現実を認め、宗教の多様性を理解しておくことは、自身の疑問に見合った答えを見つける助けになり得るだろう」
「宗教の定義」として、著者は「多くの信者がいる著名な教えを宗教として認めるべきか否かについてさえ、すべての宗教学者が同意見ではないからである。たとえば、宗教学者のあいだでは、仏教や儒教、そして神道を宗教とみなすべきか否かについて、いまだに論争がつづいている。現在の傾向としては、仏教は認めるが儒教は認めないという見解が多いが、10年、20年前は、儒教を宗教として認める見解が一般的だった。しかし、現在では、儒教は倫理と道徳の教えであり、世俗的な哲学である、とする考えが一般的である」と述べていますが、これには大いに異議を唱えたいと思います。逆に10年、20年前は儒教を倫理道徳であるとか世俗哲学であるという考え方が主流でしたが、日本における儒教研究の第一人者である加地伸行先生の功績などもあって、現在では儒教を宗教とする見方の方が強いように思います。
宗教は、一般に宗教と結びつけられる特徴をいくつか有する事象に宗教的な色彩を帯びさせることもあります。それゆえ、世界の4大宗教のひとつとみなされる仏教がほんとうに宗教であるか否かが論争の対象となったり、仏教はたんなる人生哲学にすぎないという説が唱えられたりするのであるとして、著者は「一般に、宗教はつぎの5つの要素に関連づけて認識される――すなわち、超越的存在についての信念の存在、信者が形成する社会的集団の存在、信仰にもとづく活動の証の存在、個人の行動の規範となる(たとえば、善悪の規範のような)実践的な教義の存在、そして、超越的存在の力が(たとえば、祈りによって)働き、世俗生活に影響をおよぼし得るという信念の存在である」と述べます。
「因果関係を考える脳の進化と宗教」として、著者は「宗教の起源は人類の形質のどの部分にあるのか?」と読者に問いかけ、この問いに対する1つの答えは、起源は人類の脳の思考機能にあるというものであるとして、「人類の脳は、原因と主体と意図を推定する努力と、そこから考えられる危険を予測する能力を徐々に磨いていった。また、その予測結果の因果関係を説明する能力を身につけたのである。宗教は、人類のさらなる生存を助け得るようになったこれらの能力の副産物として誕生した、という考えかたである」と述べています。
伝統的な治療法のなかには、益するところがあるものもたくさんあると思われていると指摘する著者は、「それには、いくつかの理由が考えられる――まず、結局のところ、病気は、ほとんどが自然に治癒するからである。つぎに、伝統的な薬草には薬効があるものが多いからである。ベッドの横でシャーマンがおこなう儀式には、それによって患者の恐怖心が払拭され、プラセボ効果が引き出される可能性もあるからである。病気の原因を教えてもらえれば、たとえそれが正しくなかったとしても、何らかの対策を取れると思え、何も知らされずに絶望状態にいるよりは気休めになるからである。病人が亡くなれば、それは病人が禁忌を犯したからである、と説明できるからである。あるいは、病気にさせて殺す呪いをかけた呪術師をみつけて殺すことができるからである」と述べます。
先史時代の人々が、壁画をみる人を敬虔な気持ちにさせようと意図して描いたのかどうかはわからりません。しかし、彼らに意図があったかどうかは別として、彼らがたしかに宗教といい得るようなものを認知できる十分な、現代的な頭脳の持ち主だったとはいえるという著者は、「現生人類の近縁種とされているネアンデルタール人たちに関していえば、彼らがオーカー顔料を体に塗って、身体彩色していたことを示す証拠もみつかっている。また、彼らが遺体を埋葬していたということを示す証拠もみつかっている。したがって、おそらくネアンデルタール人たちも、宗教に関してはクロマニョン人たちと同じだったのかもしれない、と私には思えるのである。少なくとも行動学的現代人の6万年強の歴史を通じて、あるいはそれより若干長い期間を通じて、われわれの祖先は宗教を有していたと仮定してもよいと、私は思う」と述べます。
「不安の軽減」として、今日のわたしたちにとって、物事の成否は科学や知識の力に負うところが多いと指摘する著者は、「それゆえ、現代人のあいだでは、祈りや儀式や呪術といったものの実践があまりみられない。しかし、現代においても、われわれの手ではいかんともしがたいことは、依然として数多く残されている。科学や知識の力では、成功が確約されない事態にもたくさん遭遇する。そうした事態に遭遇したとき、われわれも祈りを捧げ、お供え物をし、儀式を執りおこなうのである。近代の例としては、つぎのようなことがよく知られている――航海の無事や豊作の祈り、戦勝の祈願、そして、病気の治癒などである。とくに医者から、予後の保証ができない、あるいは医学的にできることはないと宣告されたとき、人々は祈りを捧げたい気持ちになる可能性がある」と述べます」と述べています。
続けて、どのような結果になるかの予測が人知でつけられぬ場合、儀式や祈りの効果を結果に関連づけようとする人々がいるかと思えば、そのような関連づけをまったく想起しない人々もいると指摘する著者は、「この好対照の事例がギャンブラーとチェスプレーヤーである。ギャンブラーのなかにはサイコロを振る前に、験担ぎの儀式をする人が多い。しかし、チェスプレーヤーが駒を動かす際にそういう儀式をすることはまずない。それは、ギャンブルには偶然が左右する要素が多いが、チェスはそうした偶然の要素がないゲームだからである――下手な差し手が原因でゲームに負けたのであれば、相手の反応を読めなかった自分が悪いのであり、言い訳のしようがないからだ」と述べます。
わたしたちは、先がわからない状況や危険な状況に直面すると、自己の不安を和らげようとして、いまだに宗教的な儀式や非宗教的な儀式に身を委ねています。しかし、人の不安な気持ちを静め、和らげるという宗教の役割は、伝統的社会においてはるかに重要な働きを求められていたとして、著者は「現代の西洋社会の人々よりも、伝統的社会の人々のほうが、先がわからない状況や、より大きな危険に直面することが多かったからである」と述べるのでした。
「癒しの提供」として、人に癒しや希望を与え、人生の意味について語る。これも宗教の主たる役割であり、過去1万年の人類史を通じて、人々のあいだでしだいに受け入れられるようになってきた部分でもあるとして、著者は以下のように具体的に述べています。
「宗教がわれわれに与える癒しとは、死期が近づいたり、大事な人を失ったときに、宗教から提供されるそれである。哺乳動物のなかには、仲間が死んだことを認知でき、その死を悲しむような行動を示す動物も存在する。もっとも顕著な例がゾウの行動である」と述べています。
しかし、自分もいつかは死ぬと思えるのは人間だけであり、人間以外の動物がこの事実を理解しているとは思えないとして、著者は「人間は自意識と推論能力を得た時点で、小規模血縁集団の仲間の死をみとる経験から死という概念を一般化し、それを自分にあてはめて考えられるようになったのである。人類が昔から、命が尽きるというこの意味を理解していたことを示す証拠は、ほとんどすべての人間集団の発掘や調査の現場で発見され、考古学的に検証されている。そして、それらの証拠によれば、死者は放置され、野ざらしになっていたわけではないのである。死者は、埋葬されたり、火葬されたりしていた。丁重に埋葬布に包まれていたり、ミイラ化されたり、食されたりなどしていたのである」と述べます。
続けて、著者は以下のようにも述べています。
「ほんのちょっと前まで体に温かみがあった人がいまや、冷たくなってしまっている。ほんのちょっと前まで元気に動き回っていた人がいまや、微動だにしない。ほんのちょっと前まで話ができた人が、自分で自分を守る力も持っていた人がいまや、何もすることができない。この光景はだれにとっても恐ろしい。同じことが自分の身にも起こると想像するだけで、空恐ろしくなる。それゆえ、死の現実を否定する宗教は多い。そして、肉体に付随する魂という概念を持ち出し、魂には死後の世界が待っていると説くことで癒しを提供するのである」
さらに、著者は「魂は、地上の肉体に生き写しの抜け殻とともに、天国などと呼ばれる超自然的な世界に旅立つのかもしれない。あるいは、鳥に宿ったり、だれか別の人の肉体に宿ったりするのかもしれない。また、数ある宗教のなかには、たんに肉体の死を否定するだけで終わらせない宗教もある。その種の宗教の説くところによれば、死後の世界では、よい事が、生前の世界ではなすことがかなわなかったようなよい事が死者を待ち受けている――あなたは永遠の命を得ます。先にいかれた最愛の人々とふたたび出会うことができます。すべての悩みから解き放たれます。美しい処女と美酒があなたを待っています」と述べ、「時代が後世になり、人口が密になるにしたがい、さらなる悪を押しつけられるようになった人々が癒しを求めるようになった。その結果、宗教の癒しの役割がより重要視されるようになった」と説明しています。
「組織と服従」として、現代の宗教には、宗教活動の拠点となる建物(施設)が制度化されて存在する(この建物は、教会、シナゴーグ、モスクなど、さまざまな名称で呼ばれている)と指摘し、著者は「どの宗派にも聖典が存在している(聖典は、聖書、トーラー、コーランなど、さまざまな名称で呼ばれている)。宗教儀式、宗教画、宗教音楽、宗教建築、宗教服といったものも存在する。それゆえ、ロサンゼルスで育ったカトリック教徒がニューヨークを訪問し、カトリック教会で日曜礼拝に参加した場合、そこで目にするものも聞くものも、すべてが見慣れた存在なのである。しかし、小規模社会の宗教ではようすが異なる。宗教儀式、宗教画、宗教音楽、宗教服といったものは、まったくばらばらである。また、専門職としての聖職者、宗教活動の拠点となる建物(施設)、聖典といったものはまったく存在しない」と述べるのでした。
エピローグ「別の空港にて」では、「『昨日までの世界』から何を学べるか」として、行動的には現代人と変わらないホモ・サピエンスは、6万年から10万年前に誕生したと指摘し、著者は「『昨日までの世界』は、その歴史の大半の時代であり、そのホモ・サピエンスの遺伝的性質、文化、行動を形づくった時代である。考古学的発見から推測できるように、生活様式や技術的な変化の歩みは、およそ1万1000年前に肥沃三日月地帯で誕生した農耕の発生を受けて加速するまで、非常にゆっくりとしていた。最初に国家政府が誕生したのも、およそ5400年前の肥沃三日月地帯であった。つまり、今日のわれわれすべての祖先は1万1000年前まで『昨日までの世界』で生活し、多くの祖先もごく最近までそうした生活を送っていたということである。ニューギニアのもっとも人口の多い地域で、人々が外部とじかに接するようになったのはごく最近になってからのことである。そして、ニューギニアとアマゾンのごく一部の集団はいまだに外部との直接的な接触もなく、国家政府の支配も経験していない」と述べています。
「昨日までの世界」から得られる学びは、現代社会を何でもかんでも非難するものではなく、現代社会への感謝の念をも教えてくれます。現代社会では、長引く戦争や嬰児殺し、高齢者の遺棄がなくなっています。これにはほっとしている人々がほとんどだろうとしながらも、著者は「『昨日までの世界』の特徴のなかには、ぞっとするようなものばかりではなく、多くの読者にとって魅力的なものもある。たとえば、社会全体が変わらなくても個人の生活にすぐに取り入れられる特徴として、食事時に塩を振りかけないといったものなどがある」と述べます。
食事や食習慣はわれわれの生活を向上させるために、個人として実行できる範疇にあるとして、著者は「伝統的社会のニューギニア人が脳卒中や糖尿病、心臓発作で死ぬことはほぼないという驚くべき事実を再考してほしい。そうした疾病で死にたくはないとしても、部族戦争を再開したり、食事の90パーセントをサツマイモにしたりしなければならないわけではない。世界の偉大な料理を味わい、穏やかに生活しつつ、こうした疾病を避けるには、つぎの3つの習慣を取り入れればいいだけである。ひとつめは運動である。ふたつめは、ひとりでガツガツと食事をするのではなく、ゆっくりと友人とおしゃべりをしながら食べることである。3つめは、塩分や飽和脂肪酸、単糖を多く含む食品を避け、生の果物、野菜、低脂肪の肉、魚、ナッツ、穀物などの健康的な食品を選ぶことだ。この食習慣の分野は、社会全体(たとえば、有権者、政府、食品メーカー)の力を使えば、もっと簡単に実行できるようになる。たとえば、フィンランドなどの国がすでにおこなっているように、加工食品の基準を健康的なレベルにすることなどである。その他に、社会全体の変化を持たずに、個人あるいは夫婦ができることは、伝統的社会のように、子どもをバイリンガルやマルチリンガルに育てることである」と述べます。
著者は、数千年以上におよぶ社会のそれぞれの歴史的時期で、各宗教が果たしてきた役割について言及し、「そうした役割とは、物理的な世界に対する究極の疑問について満足のいく説明を与えることや、不安やストレスの多い状況に対応すること、大事な人の死や自分自身の死期、その他の辛い出来事についてみずからを納得させること、みずからの行動や権力への服従あるいは不服従を規定する道徳規範を正当化すること、教義を共有する集団の一員としてのアイデンティティを与えることなどだ」と述べます。
最後に、著者は「宗教的な不信に陥る時期を経験する人々にとって、考えを整理し、異なる社会では宗教の意味が異なることを知り、自分にとっての宗教の意味と、意味し得るものについて誠実に向き合うことは助けになるはずである」と述べるのでした。名著として名高い『銃・病原菌・鉄』『文明崩壊』に次ぐ本書は読み応えのある知的刺激に満ちた内容でした。特に、本書で紹介されている「有益な妄想」には多くのヒントを与えられ、経営上でも大きな学びを得ました。何度も読み返したい本です。
