- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2022.01.20
『むずかしい天皇制』大澤真幸・木村草太著(晶文社)を読みました。大澤氏は1958年生まれの社会学者で、木村氏は1980年生まれの憲法学者(東京都立大学大学院法学政治学研究科法学政治学専攻・法学部教授)。そんな2人が天皇制をめぐる諸問題を徹底的に語り合います。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「なぜ他のものは捨てられても、天皇制だけは捨てられないのか。悠久の謎の根幹に挑む」と大書され、「起源はどこにある? なぜ途絶えなかった? 何を象徴している? 人権に問題はない? 数々の謎をめぐり、天皇制の過去、現在、そして未来について、社会学者と憲法学者が自在に語り合う、日本人論の決定版!」と書かれています。
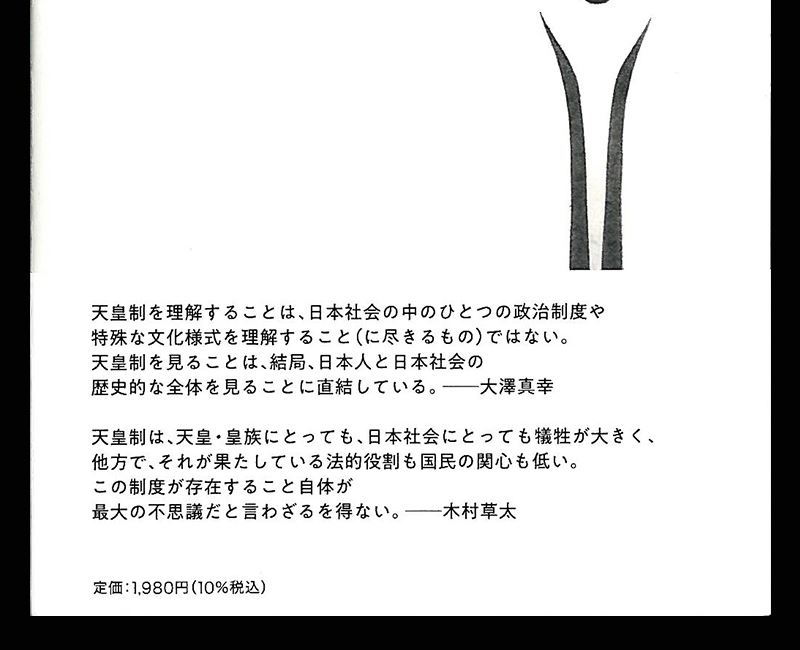 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、こう書かれています。
「天皇制を理解することは、日本社会の中のひとつの政治制度や特殊な文化様式を理解すること(に尽きるもの)ではない。天皇制を見ることは、結局、日本人と日本社会の歴史的な全体を見ることに直結している。――大澤真幸」
「天皇制は、天皇・皇族にとっても、日本社会にとっても犠牲が大きく、他方で、それが果たしている法的役割も国民の関心も低い。この制度が存在すること自体が最大の不思議だと言わざるを得ない。――木村草太」
カバー前そでには、こう書かれています。
「天皇とは何か。天皇制は何のために存在しているのか。天皇の家系は、どうして他の家系と比べて特別に高貴なのか。 こうしたことを誰にも納得できるように説明することは、とてもむずかしい。だがいかにむずかしいとしても、天皇制こそが、日本人である「われわれ」は何者なのか、を理解する上での鍵なのだ。天皇制の過去、現在を論じることを通じて、日本人とは何か、日本社会の特徴はどこにあるのかを探究する刺激的対談。社会学者と憲法学者が、誰もが答えられない天皇制の謎に挑戦する。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「まえがき」(大澤真幸)
第1章 現代における天皇制の諸問題
──象徴、人権、正統性
第2章 歴史としての天皇制
──上世、中世、近世まで
第3章 近代の天皇制
──明治維新から敗戦まで
第4章 戦後の天皇制
──憲法、戦後処理、民主主義
「まえがき」の冒頭を、大澤氏は「天皇制はむずかしい。日本人にとっては、それがむずかしいということを知ること自体、すでにむずかしいことになっている」と書きだしています。しかし、いかにむずかしいとしても、天皇制こそが、日本人である「われわれ」は何者なのか、を理解する上での鍵であるとして、大澤氏は「天皇制を理解することは、日本社会の中のひとつの政治制度や特殊な文化様式を理解すること(に尽きるもの)ではない。天皇制を見ることは、結局、日本人と日本社会の歴史的な全体を見ることに直結している。日本列島の住民は、歴史上一度も、天皇や朝廷を根本から否定したことはない。否定の度合いが最も大きかった出来事は、承久の乱だが、そのときでさえも、勝利した武家政権(鎌倉幕府)は、朝廷の主だった者を配流しただけで、制度としての天皇・朝廷を温存した。どうやら、日本人には、天皇制を否定しきることはできないらしい」と述べています。
第1章「現代における天皇制の諸問題──象徴、人権、正統性」の「天皇制とはどんなゲームか」では、大澤氏は「僕らは、日本人だけのレベルではなく、人類の一員としてものを考えないといけないときです。僕らにとって重要で深刻な問題は、ほとんど国レベルでは解決できない。たとえば、環境問題をどうするのか。格差の問題もグローバル経済のメカニズムから生まれている。働き方の問題も、抜本的に考えるのであれば、日本だけでは解決できない。経済問題だって、国レベルではよい解決法かもしれないが、世界レベルから見ると、それは最悪の手になったりする。ブレグジットだってそう見えます。日韓関係においても、ドメスティックには相手に一撃与えて気持ちの良い感覚をもつような政策でも、外から見ると全然いいことをしていない。ネーションにとってよいように見える解決方法は、ほとんどグローバルな観点からはよくない。むしろ、人がそれぞれのネーションに執着することこそが、問題を深刻化しているわけです」と述べます。
「二つの矛盾したベクトルの共存」では、大澤氏は「客観的に見ると、天皇制の機能は、究極的には呪術的なものに由来しています。それは、法的な正統性の論理には還元できない、人間のプリミティヴな態度や感情に基づいています。この呪術性が、今言ったような矛盾、国民を超えて行こうというベクトルと、国民の一人であるというベクトルが両方あることからくる曖昧さみたいなものを隠蔽するようなかたちで、無意識のうちに活用されていたように思います」と述べます。
「敗戦問題で果たした積極的機能」では、政治の失敗や困難を、天皇の道徳的な行為が補償してくれた一例として敗戦問題があるとして、大澤氏は「総力戦に敗戦したことによって、日本人は、戦争の死者とどう対応すればよいかわからなくなってしまった。日本の侵略戦争の犠牲になった他国の死者と、それから戦争で散っていった自国の死者です。特に、後者の死者にどう対したらよいのか、とても難しい。しかも、前者の死者との関係は後者の死者との関係を前提にしています。というわけで、日本人は、戦争の死者との関係をうまくつけられずにいたところ、平成の天皇は、皇后とともに、戦争の死者のために、慰霊の旅をある時期から非常に熱心にした。敗戦があったため、日本人は死者とどう付き合ったらいいのかわからなくなっていた中で、です」と述べます。
続けて、大澤氏は「そのため、僕には、天皇が、日本の一般国民や、政治家の代わりに、戦争の死者と向かい合ってくれた、というように見えるのです。平成の天皇・皇后の慰霊の旅がなかったら、ずっとひどいことになっていた、と思います。逆にいえば、天皇・皇后がやってくれたおかげで、日本人は、死者に対する追悼等の行為を免除されてしまった、という面もあるのですが、いずれにせよ、これは、政治の失敗を天皇が補償してくれたケースのひとつです。平成の天皇は、少なくとも日本近代史にとって最大の躓きの石になった死者との付き合いをどうするのかについて、ひとつの解答、やり方を示したと見ることができるような気がします」と述べるのでした。
「人間が感じる正統性の源は何か?」では、大澤氏は、普通のカリスマは圧倒的な能力を誇示することを指摘します。神の声を聞けたり、霊感があったり、などです。しかし、天皇は、ほとんどカリスマらしい能力を発揮しません。発揮しないなら、普通はカリスマが衰えていくはずですが、発揮しないがゆえに失敗もなく、カリスマ性が維持されているとして、「極論すれば、いかなるカリスマ的な力も発揮しないがゆえに、カリスマ性がある、という逆説ですね」と述べます。
また、天皇は積極的に意思を表現しない限りで機能すると指摘し、大澤氏は「天皇の意思は、周囲のみんな忖度することになっている。そして、クリティカルな場面で、天皇がこう思っているらしいということが決め手になる。その時に天皇がほんとうに出てきてはっきりものを言ったらかえってダメなんですよ。誰かが思っていることがあって、それを天皇に投影できるかどうかが勝負を分けるのです。尊王攘夷を、天皇の意思のように言うことが出来るのか。霊感によって積極的に決断したりするような、カリスマ性を証明するときに使う様々なパフォーマンスをしないことで、カリスマ性が維持されることになっている」と述べるのですが、それに対して木村氏は「先代の天皇が国民の尊敬を集めたのは、黙々と慰霊の旅をしたからです」と言います。すると、大澤氏は「天皇自身は一生懸命やっていて、みんなそれに感謝しているし、とても癒されている。しかし逆に『天皇がやってくれているから』、国民としては自分もやった気分になる、という機能もあるのです」と語るのでした。
「天皇と歴史修正主義の関係」では、少なくとも、敗戦のときには、日本の戦後のリーダーもGHQも「日本を大手術しなければならないが、患部を全部取ってしまったら死んでしまうかもしれない」と思ったとして、大澤氏は「だから、こっちの方だけを取る、みたいな手術をした。すると、日本人は死なずに生き延びて、だんだん健康にもなってきたので、手術が成功したように見えたのです。ただ、今日、よく診断してみると、癌はいろんなところに転移していて『永続敗戦』という病になっているのですが、この病は実は、自覚症状のない慢性病のようなものなので、本人はむしろ、そこそこ自分は健康だ、という気分になるのです。あんまり健康な気分なので、歴史修正主義の人が、そもそももとから病気にかかっていなかったのではないか、手術も要らなかったのではないか、ということを言い始めたのですね。そんな状況です」と述べています。
「死者の思いや願いを継承すること」では、天皇制がそのまま敗戦を生き延びたことに、日本人にとって意図せざる効用があったかもしれないと指摘し、大澤氏は「天皇制だけが、日本人が戦前にまで遡る過去の伝統とつながりうる手がかりになったからです。伝統を引き継ぐというのは、別の言い方をすると、自分たちの『死者』の思いや願いを継承するということです。ところが、日本人の場合、自分たちが継承すべき死者というものが、敗戦時点よりも深い過去にまで遡ることができなくなってしまったのです。この問題については、すぐ後でまた論じますが、ともかく、そのことで、現在の日本人は、自分たちが生まれる前の死者の思いというものを配慮したり、引き継いだりすることができなくなった。僕はこのことの代償はものすごく大きいと思っています。自分たちが生まれる前の過去の世代のことを思えない人は、自分たちが死んだ後の未来の世代のことを考えることができなくなるからです」と述べています。
「昭和天皇の人間宣言をめぐって」では、天皇の戦争責任ということに関連することとしては、少なくとも昭和天皇は、人間宣言をしたことを指摘し、大澤氏は「普通は、これは、日本が戦前の体制から脱却して民主化するために必要な手続きのひとつとみなされていますが、三島由紀夫をはじめとして、この人間宣言に批判的な人もいる。人間宣言のどこに問題があるかというと、これでは、日本の戦死者があまりにも浮かばれない、というか、死者に対する極端な裏切りになってしまうからです」と述べます。また、一般の日本人は、戦争の、あるいは戦前の死者と自分たちの間の連続性ということを打ち立てられないので、アジアの死者への謝罪に成功しませんでした。しかし、天皇は継続しています。大澤氏は、「だから、少なくとも天皇は、日本の死者とアジアの死者を慰霊し、追悼し、また彼らに謝罪することもできる。平成の天皇は、昭和天皇の息子として、昭和天皇の代わりに、同じ『天皇』を継ぐ者として、それらのことをやったわけです。もし天皇がいなかったら、もっとひどいことになっていたでしょう」と述べます。
「皇室メンバーの人権問題」では、天皇の地位を承継するために、様々な宗教儀式が出てくるとして、大澤氏は「それについて考えている頃に、ちょうどカルト2世問題のネット記事を読みました。カルト家庭では宗教が決まっているので、2世たちは信じたくもない儀式に参加させられる。天皇家に生まれたら、憲法が信教の自由を謳ったところで、天皇の祭祀から逃れるのは無理でしょう。カルト2世が親のカルトから抜ける以上に難しい。精神の根幹であるはずの信教の自由ですら、ものすごい拘束をうける。これは、すさまじい人権侵害として認識すべきです。こうした人権侵害を受忍してもらうなら、即位をしない権利や退位をする権利を保障しなければいけない。そう考えてみると、先代の天皇が前例にない退位を望んだのはいわば当然で、今までそうした希望を叶えるための制度を整えずにいたことの方が、よほどおかしかったのではないか、と感想を持ちました」と述べます。
「持続可能性の危機」では、かなりの日本人が天皇制はあったほうがいいと思っているが、その持続可能性については、せいぜい女性の天皇を認めるかどうかくらいのことしか考えていないとして、大澤氏は「たとえ女性の天皇が容認されたとしても、皇族に子どもが生まれない場合だって十分にありうるわけです。女性の天皇を認めたくらいでは、皇室が安泰とは言い難い。もし天皇制の、少なくとも『万世一系』のフィクションを維持したいのであれば、この制度が持続可能であるように抜本的な考え直しが必要になります。しかも、改革された皇室の制度が、われわれの正義の感覚と合致するものでなくてはならない。一部の人が、人権を著しく制限され、奴隷になればいい、というような制度ではどうかなと思います」と述べます。
「本気で考えられていない持続可能性」では、大澤氏は「持続可能性もないし、もはや必要がないということで、国民の意思としてやめる、ということであれば、それもいいと思うという大澤氏は、「実際、日本史をふりかえってみても、天皇制を終わらせることができたかもしれないような危機的状況が何回かはあったのですから。しかし、もし天皇制を続けるのであれば、それを前提にした覚悟が必要だと思います。天皇制に、持続可能性を、しかも僕らがもっている人権や正義の感覚と両立する形での持続可能性を与えるべく、改革する必要がある。誰かが奴隷になってくれればいいというような制度であったら、天皇になりたい人、皇室に入りたい人、皇室にとどまりたい人はそんなにいないでしょう。天皇制の支持率は高いのに、日本人が、この制度の持続可能性についてあまり本気で考えず、なるようになるさというようにしか見ていないのは不思議なことです」と述べ、それに対して木村氏が「女帝反対と言っている人は、割と年寄りが多い。自分たちの世代では安心だ、と思っていそうですね」と言います。
木村氏が「結論はみんな見えていると思うんです。今の天皇家は世襲できなくなる時が必ず来る。その時には、天皇制度を廃止するか、なんらかの理由をつけて他から新たな天皇を立てるしかない。でも、両方とも地獄でしょう。この地獄から目をそらすために、話をしようともしない」と発言すれば、大澤氏は「旧皇族でわざわざ復活したいと思う人や家はいないだろうしね……。天皇関係の大きなフィクションは万世一系ですよね。こんな古い王権は世界中探してもどこにもない、というのが日本人の自慢です。でも、どうしてそんなに長続きできたのか、考えてみるとよい。それは、そもそもその『一系』であることの基準がきわめてあいまいだから、別の言い方をすれば柔軟だったからなんですね」
また、大澤氏は「要するに、天皇の万世一系性というのは、かなりゆるい、適当なものだったのです。だから、断絶することなく長続きした。しかし、天皇制を近代的制度として整えるとしたら、そんないいかげんなことではいかないので、誰が継承者かを一義的にきちんと規定した。もちろん、側室制度も野蛮なものとみなしてやめた。かつて万世一系を可能にした条件を捨てたのですから、存続・持続が困難になるのは当然のことです」とも述べるのでした。「なんのために、どうして必要なのか」では、木村氏が「国民主権に絶対の自信があれば、天皇は不要、余計な味つけです。天皇制支持には、二つの系統があると思います。1つは、天皇に伝統とカリスマを感じる『天皇教』の信者的なもの。もう1つは、議会政治への根本的な不信感によるもの。議会政治一本だと危ないから、サブを持っておきたい。この系統は左派的な考えとの親和性もある。こうして、右から左まで揃って天皇制を支持できるわけです」と語ります。
すると、大澤氏は「実際問題として、平成の天皇は――そしておそらく現天皇も――かなりリベラルな方で、民主主義を支持し、憲法9条を支持している感じがある。天皇ははっきりと明言しないけれども、その「象徴的行為」には、明らかに「リベラル」を支持する政治的なインプリケーションを伴っている。しかも、これを天皇の政治関与とみなして批判する日本人は、あまりいない。むしろぜひともやっていただきたいと思っている。やはり、天皇にはある種の象徴的行為を期待している。それではどんな行為を期待しているのか。たとえば、被災地に行く。社会的弱者や被害者に対して共感し同情する。慰霊の旅のような、国のために死んでいった人を含めた、慰霊や鎮魂。そこが共感されている一番の理由になっていると思います」と述べるのでした。
第2章「歴史としての天皇制――上世、中世、近世まで」の「『天使』でもなく『王』でもなく」では、古代の天皇制に言及し、大澤氏は「当時の日本の支配者たちは、とりわけ聖徳太子は、完全に中国の皇帝に従属することは嫌だったのでしょう。とはいえ、対等に張り合うこともできるはずがない。そこで、『天子』でもなく、しかし、『王』でもない。妥協点として『天皇』という『天子』に準ずる名前をつくって勝負に出たのだと思います」と述べ、また、「実際、卑弥呼の段階から冊封されることでドスを効かせる作戦をしていた。『漢委奴国王』と。冊封的な雰囲気を出すことで国内に権力を誇示することは、倭の五王も行っていましたが、ある時期からその手はやめて、国内で独立してやろうと思ったのではないか。一大帝国である隋との間の関係を良好に持ちながら、しかし完全に従属的な地位につかずにやるという作戦に出たんですね。そのときに発明された名前が『天皇』じゃないかな」と述べます。
大澤氏が「中世や近世では、ほとんど『天皇』なんていう語は使われていません。この事実を見ても、『天皇』は国内向けよりも、むしろ、対外的なもの、とくに中国を意識したものであることが暗示されます。それまで、『花園院』とかいうのが普通だったのを、正式に『花園天皇』というようになったのは、なんと大正末期です。外交文書も、ずっと『皇帝』が使われていたのですが、昭和11年になってはじめて、正式に『天皇』になります」と言えば、木村氏も「そうですよね、『禁中』とか『院』と言われていた」と同意します。すると、大澤氏は「いずれにせよ、『天皇』という名前が導入されたのは、聖徳太子の時からです。十七条憲法の話もありますけど、先進国の律令的なものを取り入れてみたいと、思った時期と重なります。ここに文明国の目覚めがあったのではないか」と語るのでした。
「所有と占有の中間の成り立つ荘園」では、平安時代のごく初期までは天皇の軍隊らしきものがあったとして、大澤氏は「つまり、武芸をもって天皇につかえる臣下がいたのです。その中でももっとも有名なのは、征夷大将軍となった坂上田村麻呂(758-811)でしょう。彼は下級の貴族ですよね。戦うのが得意だったので、東国の蝦夷の追討のために派遣され、大きな軍功を挙げて戻ってくる。坂上田村麻呂のような、武芸で天皇に仕えた貴族の子孫が、独立して武士になった……という筋だったら、日本史はもっとわかりやすかったのです。しかし、そうではない。確かに、こういう系譜の武士もいます。坂上氏の末裔も武士になっています。しかし、彼らはどうみても主要な武士ではない。武士の中心にいたのは、平家や源氏ですね。彼らは、しかし、武芸をもって天皇に仕えた人の子孫ではありません」と述べています。
「天皇への敬意がゼロだった信長」では、織田信長はまさに武士の中の武士であると同時に、武士としての条件を極限までつき詰めたために例外的な武士でもあるとして、大澤氏は「武士には二重性があると言いました。一方では、天皇への直接の従属から離れて自立しようとする面。他方には、天皇や公家へと憧れ、最終的にはそれらに従うという面。前者が、天皇からの遠心力で、後者が、天皇への求心力です。織田信長は、前者が非常に強く、後者が極小化した唯一に近いケースです。信長が仕えるとすれば、足利将軍か、天皇ですが、結論だけ言えば、彼はどちらにも本気で仕える気はない。天皇を自分の上に見なかった唯一の武士が信長です。詳しくは説明しませんが、彼が、志半ばで謀反にあって殺されてしまった、究極の原因は、彼の天皇への敬意がゼロだった、ということにあると僕は考えています」と述べています。
「武士は滅びて天皇は残る」では、木村氏が「南北朝になり、足利義満(1358-1408)が統一しました。義満が『日本国王』と名乗ったあたりは重要ですよね」と発言すれば、大澤氏が「義満は天皇を狙っていましたよね。義満が天皇になろうとしていた、というのは今谷明氏の有名な説です。今谷説は通説になっているわけではありませんが、しかし、義満が、上皇や天皇が担っていた儀礼的な役割をできるだけわがものにしようとしていた、ということまでは言えるようです。義満は、天皇そのものになり代わろうとしたかどうかはわかりませんが、少なくとも義満は、『治天の君』のようにふるまい、その地位を、寵子義嗣に継がせたいと考えていたと思う。結局、義満の死後、義嗣が兄の義持との争いに敗れ、この継承はうまくはいきませんが」と答えています。
「天皇の権力がきかない戦国時代」では、応仁の乱の後では、武士の支配者は、地元に留まっていなくてはならないとして、大澤氏は「そんな地元に根をもつ武士のリーダーの中から、戦国大名が出てくるわけです。戦国大名は、もともと守護大名だった者もいるし、そうでない者もいる。いずれにせよ、守護大名ならば、足利将軍の代理人として地方を支配しているという体裁になりますが、戦国大名にはそんな意識はほとんどない。こうして、中央の権力、幕府の権力、そしてもちろんのこと天皇の権力もほとんどきかない戦国時代に突入するわけです。そのかわり、戦国大名の統治機構は、ローカルなものだったとはいえ、日本の歴史上初めて、僕らが今日『政府』と呼んでいるものと同じ意味での政府を実現したのです」と述べています。
「天皇の存在感が希薄な江戸時代」では、著名な法制史学者である石井良助氏の『天皇 天皇の生成および不親政の伝統』という文献が取り上げられます。徳川家康はたった2年で、天皇からもらった「征夷大将軍」の地位を息子の秀忠(1579-1632)に譲ってしまった事実をあげ、大澤氏は「この地位自体はあまり重要なわけじゃないという感じも受けます。家康は、徳川家が『将軍』の地位を世襲することも他の大名たちに示そうとしているわけですが。石井説の『天皇親政せず』の究極の姿が江戸時代にはあります。本当に親政していないし、ほとんど存在意義もわからない。でも天皇は京都にいる。不思議な感じがします」と言います。それに対して、木村氏は「石井先生の解説では、家康は頼朝を信奉していたようですね。だから頼朝にならって、征夷大将軍になった。頼朝はいちおう皇室を尊重した点もポイントかなと思います」と言います。すると、大澤氏は「でも征夷大将軍を選ぶ。そのモデルが頼朝にあるんですね」と述べるのでした。
大澤氏が「江戸時代の皇室は、かなり貧乏ですよね」といえば、木村氏は「そうですね、大嘗祭も出来ないような」と答えます。すると、大澤氏は「それに庶民にとっても天皇というものは、どうでもいいものに感じられていた。人形浄瑠璃や歌舞伎にけっこう天皇が出てきますが、たいてい道化的な役割です。庶民にとって、天皇って具体的なイメージがないんです。見たこともないわけだし。どっちかというと、嘲笑の対象になっていた。江戸時代に流行したお伊勢参りでも、天照大神と全然関係なく、天皇への敬意というものに繋がってはいない。庶民的な感覚からしても、天皇のプレゼンスというのは非常に小さくなっているのです。けれども、天皇はきっちり残り続けている」と述べるのでした。
「神話的な権威がきいていない」では、木村氏がここまで急ぎ足で歴史を振り返ってみました。いくつか質問があります。天皇には宗教的な権威があり、神道によって自らを正統化しました。これはどの程度天皇の地位と関係していたのでしょうか。というのは、歴史を振り返ると、天皇が果たした役割は官位の授与であって、天照大神とは関係がない。現在に比べてドライな、律令制の支配の中にいたわけです。天皇の正統化神話は、日本史の中でどう効いているのでしょうか」と質問します。すると、大澤氏は「どの段階を見るかにもよりますが、天皇の神話的正統化が重要だったのは、律令以前の古代だと思います。とくに中世以降は、天皇の神話的な正統化はほとんど効いていないと思います。近世になってから天皇が天照大神と繋がっていることについてはっきり主張したのは、本居宣長です」と述べるのでした。
大澤氏は、以下のような重要なことを語ります。
「中国の王権――というか皇帝――であれば『天命』を受けたことを人々に納得させなくてはならない。『天命』を受けていることの証明は難しいですが、天命が確かにこの皇帝に対してあった、と皇帝自身もまた臣下も、はっきりと証明されたと思うくらいの実質が必要です。天命がなくなれば、革命です。ヨーロッパの王権神授説でも、神の委託を受けていることを示し続ける必要があった」
また大澤氏は、「あるいは、カントーロヴィッチが明らかにしているように、ヨーロッパの中世・近世の王権においては、王は、自分自身の自然的身体とともに、政治的身体が継承されているということを示す、キリスト教由来の繊細な政治神学を通じて、支配の正統性を維持してきた。『天命』とか『王権神授』とか『政治的身体』に対応するものが、天皇制にはない。多分、天皇が、天照の子孫でなくても、天皇としての資格や権威が消えて無くなるわけではないのです。ただ、他人から、天皇とは何で、なぜ特別なのか聞かれたら、ほかに答えようがないので、日本人は、皇祖神として天照を持ち出すしかない、ということでしょう」と述べます。
「幕末・明治維新へ」では、上世、中世、近世となっていくにつれ、天皇の存在理由が薄れてきているように見えるとして、大澤氏は「上世は、『天皇親政せず』といえども、支配のシステムの中で、しっかりと天皇や朝廷が明示的な機能をもっています。中世になって圧倒的に力を持った武士が出始めても、武士たちの天皇への依存度はある程度あって、天皇に官位を与えられたり、勅許とか宣旨とかを武士たちは欲しがったりしています。近世の幕藩体制になると、天皇の役割は、ほとんどミニマムになる。天皇の意向はほとんど尋ねられることはなく、天皇が官位を与えるという儀礼的な手続きは残りますが、天皇から与えられる官職で有意味なものは、令外官である『征夷大将軍』ですが、これだって、実際には徳川だけで決めている。むしろ、禁中並公家諸法度を幕府側が制定して、天皇や公家を上から目線で指導するような状況です。このように、どんどん天皇の明示的な機能は少なくなっていくわけですが、しかし、天皇に残ってきた」と述べます。
第3章「近代の天皇制――明治維新から敗戦まで」の「徳川には正統性が不足している」では、日本の思想史には2回の大きな山場があるといいます。1回目は、鎌倉時代です。そこで、さまざまな鎌倉仏教が出現し、独自の思考を展開した。2回目は、江戸時代の中盤以降です。大澤氏は、「今度の思想の主役は、仏教ではなく、儒学と国学です。儒学と国学の間には、明らかにつながりがある。今、1回目の方は関係がないので、脇に置いておくとして、どうして、江戸時代の中頃に、儒学・国学というかたちで、思想が深化したのか。それは、人々が支配の正統性ということに不安と疑問を抱いていたからだと思います。つまり、そこには支配の正統性の不足という問題があったのではないでしょうか」と述べています。
武士は典型的には、自分自身のイエの家長であると同時に、より包括的なイエの中で、そのイエの主人(主君)に忠義を尽くすという形式になっています。そのイエの重層的システムの頂点に徳川家があるのです。しかし、ではなぜ徳川家が偉いのか。どうして、徳川家にすべての武士は仕えるのか。徳川家が政治の頂点にいて支配することに、どんな正統性があるのか。そうした理由がよくわかりません。大澤氏は、「だから、江戸時代に儒教が栄えたわけです。儒教というのは、政治的な支配の正統性にかかわる思考だからです。しかし、儒教は、もうひとつ日本の現状を説明するのにしっくりいかない。儒教的な知へのアンチテーゼとして発達したのが国学。国学は、必ずしも、支配の正統性を中心的な主題としてはいませんが、儒教がピンとこない、ということに関係した学問、儒教への反作用という面をもつ」と述べます。
「文官に軍人をコントロールした経験がない」として、木村氏は「国内防衛に必要な実力組織は、正統性を持ちやすい。軍人だけではなく、国民にも命の危機がありますから、みんなで協力しようとなりやすい。しかし、外に出て侵略をしようとする場合には、相当なイデオロギーがないと説明がつきません」と語りますが、大澤氏は「フランス革命のときに、国民軍ができる。ナポレオンが率いた軍隊は国民軍です。『国民(ネーション)』という共同体に主体的にコミットした、ヨーロッパにおける最初の軍隊ですね。だから強かったわけです。日本は、明治維新のときに、ヨーロッパのモデルをまねして国民化する。そのための策が富国強兵ですね。これが意味するところは、国民というのは、皆、ある意味で労働者であり、そして、潜在的には皆軍人だということでもあります。特に、軍人としての側面をコントロールするには、イデオロギーが必要になる」と述べます。
「天皇制の顕教・密教」では、天皇概念に、顕教的な側面と密教的な側面があったために、数々の行き違いのようなものが起きることを指摘し、大澤氏は「2・26事件はそのような行き違いの生んだ悲劇のひとつですね。皇道派の青年将校たちは、顕教の方に徹しているわけですが、天皇自身が、そこまで顕教に純化していない。むしろ密教の方に近い態度をとり、将校たちを怒った。三島由紀夫は、戦後、天皇が人間宣言をしたことを怒ったわけですが、これも、考えようによっては、次のようにいえます。三島は、天皇が戦前の顕教的側面を完全に放棄したことを怒ったのだ、と。天皇が、密教の方に自分を特化させてしまえば、2・26の将校も、特攻隊の死者も浮かばれないですから」と述べるのでした。
第4章「戦後の天皇制――憲法、戦後処理、民主主義」の「天皇の戦争責任の扱い」では、マッカーサーの下で働いた軍人であるボナー・フェラーズという人物を取り上げ、大澤氏は「NHKスペシャルで彼の遺族の話を特集していましたが、アメリカに留学した日本人の女性と仲良くなって、戦前の日本にも何度も来ている親日家だった。日本人は天皇を重視しているので、もし処罰したら大きな抵抗にあって面倒なことになるから、むしろ天皇を活用したほうがいいのではないかと、フェラーズがマッカーサーに助言している。マッカーサーは野心家で、大統領選挙に立候補しようとしていますよね。人気のあるルーズベルトがいるときに、太平洋戦争の英雄になって、戦争が終わるころにはルーズベルトが死んでいた。日本の占領統治を成功させ、祖国に凱旋し、共和党候補として立候補し、無能なトゥルーマンよりも俺が大統領になりたいと野心を持っていたわけです。だからこの占領統治の成功を、マッカーサーは重視していたのでしょう。普通に考えれば難しい、天皇を処罰しない方向に舵を切った理由のひとつも、ここにあった可能性があります」と述べています。
「マッカーサーの誇張」では、大澤氏は「実際、天皇陛下だって、『私には全く非が無い』とまでは言っていないと思うのです。東條を含むA級戦犯7名が絞首刑になった日に、天皇陛下の涙で泣きはらした姿を侍従たちが目にしている。やはり相当に心を痛めていたのは事実でしょう」と述べます。また、「天皇が戦争をやめると通達したら、日本人は実に従順に戦争をやめ、抵抗らしい抵抗も起きなかった。これは僕の勝手な憶測ですが、GHQはこれを見て、天皇の力を利用しようと考えたのではないか。しかし、さらに勝手な憶測を重ねれば、仮に天皇を排していたとしても、日本人は、占領政策に対して従順に従ったようには思います。とにかく、ある段階で、天皇の力を日本の民主化に活用してしまおうとGHQは考えるようになった」と述べるのでした。
一方の木村氏は、「東ドイツがそうであったように、9月の段階で、『日本全土を社会主義化して、土地や財産を国有化します』と発表していたら、違う展開が待っていたのではないかとも思います。占領国の側が民主主義の先生としてふるまったからこそ、日本側が占領を受け入れやすくなったのではないか。これは私の印象論ですが、日本では天皇崇拝と同時にマッカーサー崇拝もあったので、マッカーサーが『天皇は悪い奴だ』と言っていたら、国民はその言葉に対して、案外従順だったのではないかと思います」と述べています。
「善意の圧政者」では、マッカーサーについて、大澤氏は「自己演出の激しい人だから。日本の占領統治は歴史上まれにみる成功で、ジュリアス・シーザー以来の軍事占領史に名を残すものだというような趣旨のことを人に語ったりもしていたらしい(笑)。いずれにせよ、1948年の大統領選に共和党からの立候補を目指しますが、予備選段階で全然だめで、太平洋戦争の英雄だったこと、極東の敗戦国の統治の責任者としてそこそこ成果をあげたことは、アメリカの中西部の田舎の人たちにとっては関係のないことがわかってくる」と述べています。
「平和主義でも民主主義でもなく」では、現代思想の用語を使えば、「共産主義」はまさに「シニフィエなきシニフィアン」であるとして、大澤氏は「客観的に見れば、原点の『共産主義』にシニフィエ(意味)がないのですから、『共産主義の地平』の中で位置づけられたとしても、ほんとうは意味などない。しかし、当事者たちには、『共産主義の地平』の中にあると、何やらとても深い意味があるように感じられてしまう。どうしてなのか。それは、『共産主義』が『シニフィエなきシニフィアン』だからです。このシニフィアン(記号)は、シニフィエ(意味)がないのに人を拘束しているのではなく、シニフィエがないからこそ、強い拘束力があったと見るべきです。シニフィエ(これは限りなくゼロに近い)に対してシニフィアンが過剰である、まさにその過剰性が人を縛る」と述べます。
続けて、大澤氏は日本人がやっている天皇制をめぐるゲームにも似たものを感じるとして、「『天皇』とか『国体』とか『三種の神器』とかは、『シニフィエなきシニフィアン』なのではないか。『国体』という観念の神通力は、戦後まもない時期の国体護持のための努力の中で、逆に雲散霧消してしまうわけですが、『天皇』はいまでも、その効力を残しています。『天皇』は、もしかすると、連合赤軍の『共産主義』よりももっと徹底した『シニフィエなきシニフィアン』なのではないか」と述べます。
「天皇制の文化財的な価値」では、木村氏が「大嘗祭には公費を出していますが、政教分離違反ではないかとの批判があります。これに対して、『文化財の保存活動として支出しているのだから合憲だ』と主張するのは、あり得る筋でしょう。宮中行事には歴史的な価値があるものも多い。大嘗祭には長い歴史もありますから、国宝級民俗文化財として扱い、文化財補助金を出すことはできるはずです。実際、たとえば、愛知県岡崎市では、大正天皇即位の際の大嘗祭に供えるお米を収穫した際の唄や踊りが、市指定の無形民俗文化財になっています。でも、大嘗祭本体を文化財にする議論に支持は集まらない。政治家が大嘗祭に公費を出すべきだと思うのは、天皇に政治的な価値を見出しているからであって、重要な文化財の管理者としての側面は、ほぼ無視されています」と述べます。すると、大澤氏は「僕は本音を言うと、大嘗祭どころか天皇制全体を文化財にするのはひとつの手だと思っています。でも、きっと受け入れられないと思います。大嘗祭を民俗文化財にしようとするだけでも、ダメな状況なのですから」と述べるのでした。
天皇の身になってみると、「象徴」と言われてるが、本当は何もできないと指摘する大澤氏は、「『象徴としての行為』と前の天皇は言っていますが、よく考えると、そんな言葉はありえません。象徴というのは定義上、無為でなければいけない。しかし、天皇や皇族に、何もしないことに価値があるような人生を強いるなんて、ひどいことですし、天皇としてもとうていやってはいけない。だから、前の天皇は、皇后とともに、『象徴としての行為』とか『象徴的行為』とかについて一生懸命考えたのだと思う。そして実際、前の天皇・皇后は、けっこうよいことをしたと思う。戦争の犠牲者のために祈ったり、ハンセン病の人たちに会ったり、被災地で苦しんでいる人を訪問し、元気づけたり、と。だから、多くの人が、この『象徴としての行為』を承認しています。片山杜秀さんは、戦後の天皇には、『象徴』としての側面と『人間天皇』としての側面、矛盾する二つの側面がある、と言っています。『象徴としての行為』というのは、この矛盾した二側面を強引に貼り合わせた結果とも解釈できます」と述べます。
平成の天皇・皇后の「象徴としての行為」がそれなりに成功した背景は「戦争」であるとして、大澤氏は「明仁天皇自身が、戦前の生まれで、戦争を経験しているし、何より自分の父である昭和天皇は、本来だったら戦争の責任を負ってもおかしくない立場だった。平成の天皇はだから、あの戦争に対する日本人の集合的な懺悔心とか後悔とか反省とかを身に帯びて行動することができたし、自らも積極的にその役割を引き受けたと思う。さらに、そういう天皇だからこそ、戦争には関係がない場面でもオーラが宿ったのかもしれない。そういう可能性は否定できません。しかし、令和の天皇、徳仁天皇は、戦後生まれで、戦争との関係は薄い。そういう天皇に、有意味な『象徴としての行為』、がたくさんできるか、微妙です」と述べています。
「天皇はリザーブか、レギュラーか」では、「被災地に来た時に、ありがたい感じがすることもある。それは天皇に、何とも説明しがたいオーラがあるからです」という大澤氏は、総理が行ってもそれほどありがたい感じはしないし、むしろ文句を言いたいそうです。今頃来てなんだとか、もうちょっと支援物資をとか、というわけです。しかし、「天皇が来たら、すごく元気づけられましたということになる。なんで元気づけられるのかは、良くわからないけれども(笑)。先ほどの連合赤軍の『共産主義』と同じ、『天皇』が、『シニフィエなきシニフィアン』で、象徴体系の全体にエネルギーを供給する『ヘゲモニー的な記号』である、ということと関係があります」と述べます。ただ、平成の天皇、皇后に特別なオーラがあったのは、彼らが「戦争」の影を宿していたからかもしれないということもあるかもしれません。大澤氏は、「国民の大半が戦後生まれで、天皇自身も戦後生まれであるような状況で、なお新しい天皇に、平成の天皇のようなオーラを期待できるだろうか……。天皇が訪問することで、被害者がよほど力づけられない限り、被災地訪問などかえって迷惑、などということにもなりかねませんからね」と述べるのでした。
「天皇がいる以上、日本に空気は存在する」では、大澤氏は以下のように述べています。 「日本人にとっての意思決定は『空気』です。天皇がいても、いなくても、それは変わりない。ただ空気は、僕らが一致してそう考えているという想定が必要です。客観的にみれば、本当はどうか知りませんよ。みんな意見がバラバラかもしれない。しかし、それでも、一校岩の同一的な空気が存在しているはずだという、先験的な想定が、日本人の集団や共同体を成り立たせている。空気にとって『同一性』は本質的な条件で、『多様な混合気体のような空気』というのは、空気の自己否定、自家撞着のようなものと考えられている。でもそんな不純物のない空気なんて存在していない可能性があるわけです。そのために、普通はたとえば多数決によって決めたりするわけですが、日本人は、空気があることが前提ですから、その前提が成り立っていないことをあからさまなものにするかもしれない多数決はあまり好まれない。とにかく日本人は空気が存在していることに、絶対の確信を持っている。少なくとも、誰もがそのような確信を持っている、という想定で皆が行動する。『空気が読めない』と批判されたりするのも、空気が存在しているからです。その空気の、最後の最後の砦が天皇なんですよ。天皇がいる以上、日本に空気は存在するんです。
そして、天皇がいる以上、かならずその空気が見出されるのです」そして「思想や理念を測るリトマス試験紙」では、大澤氏は、江戸政府にとっての天皇制は「ノンアルコールビール」で、明治政府にとっては「アイロニカルな没入」であったと指摘します。では、現行法制化での天皇制とはいったい何か? 大澤氏は、「機能的に説明するなら『消極的な機能』と『積極的な機能』だと言えます。他方、憲法条文を素直に読むと、天皇がいないと国事行為ができなくて、内閣総理大臣も最高裁判所長官も任命できず、国家が回らないことになります。そして今の制度では、天皇が『即位なんてしたくない』とか『憲法なんて無視して好き勝手にする』と言い出したときに、それに対処する手段がありません。つまり、天皇制は、天皇が国民の期待する役割を引き受けることによって、天皇が天皇制を維持する努力をする限りにおいて、成り立つ制度なのだと言えます」と述べるのでした。日頃から天皇制に関心の深いわたしは、本書を読んで多くのことを学びました。しかし、あまりにも大澤氏が一方的に喋り、木村氏といえば相槌を打つ程度ですので、対談の体はなしていないようにも思いました。ここまで語りまくるのなら、大澤氏の単著にすべきではなかったでしょうか?
