- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2022.05.03
『Dignity』ドナ・ヒックス著、ワークス淑悦翻訳、ノ・ジェス監修(幻冬舎)を紹介いたします。著者は、ハーバード大学心理学教授。Dignity(尊厳)とDignityが関係性の中で果たす役割について、初めて言語体系化した第一人者。英国BBCの「真実と向き合う」と題するテレビ放映シリーズで、ノーベル平和賞受賞者であるツツ大司教と共同でファシリテーターを担うなど、国際紛争解決の現場において、世界各地の対立関係にある共同体間の対話のファシリテーターを20年以上にわたり務める。また数多くの企業や組織には、自らが考案した「Dignityモデル」を適用した実践的コンサルティングも実施。現在ハーバード大学やコロンビア大学をはじめ、世界中でDignityを活用した対立解消法を学ぶコースの教鞭に立ち、Dignityの役割やリーダーシップに関するトレーニングやセミナーを展開中。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「”尊厳”こそが、あらゆる人間関係の基礎となる」「自分への、他者への理解を深めて幸福に生きるたったひとつの原則」「全世界の知識人たちの間で話題となっているベストセラー、待望の邦訳版!」とあります。
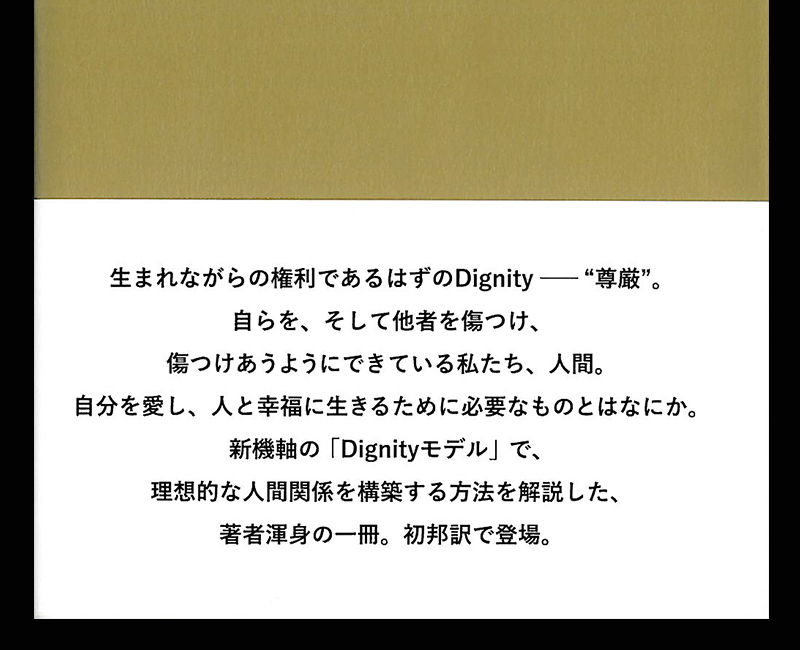 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また、帯の裏には、以下のように書かれています。
「生まれながらの権利であるはずのDignity―”尊厳”。自らを、そして他者を傷つけ、傷つけあうようにできている私たち、人間。自分を愛し、人と幸福に生きるために必要なものとはなにか。新機軸の『Dignityモデル』で、理想的な人間関係を構築する方法を解説した、著者渾身の一冊。初邦訳で登場」
本書の「目次」は、以下の通りです。
序文「デズモンド・ツツ名誉大司教からのメッセージ」
「まえがき」
「謝辞」
はじめに「尊厳の新しいモデル」
第1部 尊厳の10のエレメント
第1章 アイデンティティを受け入れる
第2章 仲間に迎え入れる
第3章 安心できる場をつくる
第4章 存在を認める
第5章 価値を認める
第6章 公正に扱う
第7章 善意に解釈する(疑わしきは罰せず)
第8章 理解しようと努める
第9章 自立を後押しする
第10章 言動に責任を持つ
第2部 他者の尊厳を侵害してしまう
原因となる10の心理的誘惑
第11章 されたことをやり返す
第12章 面目にこだわり、虚偽や隠蔽に走る
第13章 自分の過失を認めず責任から逃れる
第14章 他者からの承認という偽りの尊厳を求める
第15章 偽りの関係性の中に安心を求める
第16章 衝突や対立を避ける
第17章 自分を被害者と見なす
第18章 人からの意見に抵抗し自分を守る
第19章 罪の責任から逃げるために他者を責め侮辱する
第20章 偽りの親交や品位を落とすような
ゴシップに加わる
第3部 尊厳によって
関係性を癒すのは
第21章 尊厳によって和解する
第22章 尊厳の約束
「注釈」
「参考文献」
本書のテーマである「尊厳」とは何か。それは、個人の尊厳あるいは、個人の尊重とは、すべての個人が互いを人間として尊重する法原理を指します。日本法では最高の価値基準であり、各種基本的人権、中でも平等権を直接根拠づけるものとされます。世界的ないし歴史的には憲法制定権力に正当性を与える自然権として理解されています。
序文「デズモンド・ツツ名誉大司教からのメッセージ」では、ツツ大司教は以下のように述べています。
「尊厳は人を支えるだけでなく、人に活力を与え、可能性を広げ、偉大な行いを可能にします。そしてまた、傷ついて倒れた者を立ち直らせ、破壊されたものを回復する力を持っています。他者の中にある善意を認識し、それを本人と共有することで、相手は自分の尊厳を感じられるようになります。これこそ、将来起こり得る紛争を平和に導く方法なのです。自分の尊厳に気づくこと、自分の価値に気づくことが、『私には価値がない』という感覚で麻痺した日常を打開する、唯一の答えになるのです。もし私たち1人ひとりが尊厳の実践者となり、尊厳は神から与えられた生まれながらの権利であるという真実を世に伝えていくことができたら、どんなにかすばらしいことでしょう」
「まえがき」で、著者は「人が尊厳の力を理解し、それを実践することで得られるウェルビーイング(身体的、精神的、社会的に健康で幸せな状態)の感覚というのは、実際に体験して理解するものであり、数字で測れるものではありません。また、どうすれば尊厳を相手に与えられるのか、どうすれば自らの尊厳を維持できるのかを知っていることが、どれだけの利益を私たちにもたらすのかは、計算式で産出できるものでもありません。人は自らの尊厳を相手の目の中に見出したときに初めて、その真価を理解するのです」と述べています。
はじめに「尊厳の新しいモデル」の冒頭には、「尊厳とは、命あるものすべての価値とヴァルネラビリティ(心の脆さ、傷つきやすさ、弱さ)を認識し、それらを受け入れることによって開かれる内面的な平和の境地のことである」と書かれ、「尊厳モデル」として、「尊厳モデルとは何でしょうか。それは、人生と人間関係の中で、尊厳が果たしている役割を、誰もが理解できるようにするために私が開発したアプローチ法です。それはまた、私が対立の本質というものを探求していくなかで見つけた、パズルの最後の1ピースでもありました。尊厳を顧みられず、価値のないものとして扱われたとき、人間がいかにヴァルネラブル(脆く、傷つきやすい状態)になるかということを、私たちは見逃してしまっている。そう私は感じたのです」と書かれています。
また、「尊厳モデルは、尊厳を侵害されたときに、なぜ人が痛みを感じるのかを説明しています。また、知らないうちに他者を傷つけてしまうことを事前に防ぐための知識や気づき、スキルについても示しています。加えて、対立の中で破綻してしまった関係性の建て直し方を提示し、和解のために何ができるかについても提言しています。さらに、この尊厳モデルは、関係性の破綻とは切っても切れない、けれども誰も触れてこなかったある問題に対する私なりの答えです。私はその問題を「尊厳の侵害」と名づけました」とも書かれています。
「尊厳と尊敬の違い」として、著者は尊厳と尊敬は違うと指摘し、「『尊厳』とは、人間が生まれながらにして持っている権利のことをいいます。生まれたばかりの赤ん坊を前にすれば、誰しもそれを感じるでしょう。赤ん坊に価値が備わっているということに異論を唱える人はいません。もし周りにいる私たちが、そんな子どもたちが成人へと成長していく過程でも、この尊厳というひとつの真理を手離さず大切に育み続けることさえできたなら、もしすべての人間に備わっている生来の価値を感じ続けることさえできたなら、もっと当たり前のように子どもたちを大切に扱い、傷つかないよう彼らを守ってあげられるでしょう。そうなれば、尊厳を持って人と接するということが、人と人が交流する際の基準になっていくはずです。そして尊厳を基準とした交流では、相手を大切な存在として、また、関心を向ける価値がある存在として扱うことがたいへん重要になってきます」と述べています。
18世紀に執筆活動を行った啓蒙哲学者のイマニュエル・カントは、「人間の尊厳」についての問題を取り上げました。彼は、条件や状況に左右されることなく、何が道徳的に正しいかを普遍的に定める方法、「定言命法」の考え方を提唱したことを紹介し、著者は「カントは、正しい行動の基本原則のひとつとして、『自身の人格、ならびに他のあらゆる人の人格における人間性を、いつでも同時に目的として扱い、決して単に手段として扱わないように行為せよ』と述べました。また彼は、自殺は『他人だけでなく自分自身をも、生来の価値を持った存在として扱うように』とした定言命法に反するとして、道徳的に誤りであると考えました」と述べます。
「人間の進化の歴史における尊厳のルーツについて」として、人間の尊厳への欲求は、私たちの古来の進化の過程を起源としていると指摘し、著者は「進化生物学者たちは、無意識深くから生まれるこの衝動こそが、私たちが祖先から受け継いできた生存行動の謎を紐解く鍵であることをよく理解しています。私たちの生存行動は、いかにして生き残るかを探求してきた進化の歴史と密接に結びついており、こういった人間の性質が、生涯を通じて私たちを動かしています。それはまた、私たちが何を求め、何を回避すべきかを、自動的かつ無意識的に私たちに選択させることから、『本能』とも呼ばれています」と述べます。
オランダ生まれの心理学者であり、動物行動学者のフランス・ドゥ・ヴァールによると、「つながり」は人間の生態の一部であり、人は互いにつながり合うよう生まれついているといいます。それは「つながり」というものが、傷つく恐れよりも、安全や安心を人にもたらすからです。シェリー・テイラーは、彼女の同僚たちとの共同研究で、女性には「闘争・逃走反応」に代わって、「世話と友情」と呼ばれる性質があることを実証しました。著者は、「危険と向き合うときには、1人より誰かと一緒の方がいい、数も強みになる、ということなのでしょう」と述べています。
わたしたちはつながり合うための心の器を呼び覚すこと(ダニエル・ゴールマンが「原初の共感(primal empathy)」と呼んでいるもの)によって、親密な社会的絆だけがもたらすことのできる心地良さと安心感を感じられるようになるとして、著者は「尊厳の念をもって扱われるという経験は、大脳辺縁系を刺激します。そして、『誰かが自分を見てくれる』『認識してくれる』『価値を認めてくれる』といった、心地良い感情を生み出します。それらの感情はすべて、他者との関係性の中でしか得られないものであり、人生を豊かにしてくれる経験といえるでしょう。私たちは、恐れや怒り、恨み、報復に呑まれるのではなく、こういった新しい方法で心理的安心感を経験することもできるのです」と述べます。
さらに、著者は以下のように述べるのでした。
「尊厳の侵害が、私たちの人生にどれほど影響を与えているのかを理解するうえでは、次の点が大切な鍵になります。それは、21世紀を生きる人間にとって、外的な条件とその結果発生する脅威は著しく変化してきたにもかかわらず、私たちが生まれながらに備えている自衛的な反応自体は、まったく変わっていないということです。現代を生きる人間に対する脅威の大半は、獲物を探している野生動物というような形では襲ってきません。現代の脅威は、実際のところそのほとんどが、人間同士が心理的に傷つけ合う、尊厳の侵害に起因しているのです」
「自衛本能という遺産が関係性に及ぼす影響」として、人が武器に取って戦うときには、政治や経済、宗教などさまざまな実際上の理由があるだろうと推測し、著者は「そういった面を考慮しないのは、考えが甘いといえます。しかしそれよりも深いところで、尊厳に対する攻撃がいかに対立を生み出しているのか、その点を過小評価するのは考えが甘いというだけでなく、危険ですらあります」と述べ、さらに「人間が特筆に値する動物であるということをどうしたら証明できるのでしょうか。それを完璧に証明するには、脅威に対する反射的な反応に頼ることなく、この世界で互いに共存し、また同時に、尊厳の念を持って自他と接することができると示すことだと、私は考えています」と述べます。
「実践における尊厳モデル」として、人はみな尊厳を求め、探し、侵害されたときは同じように反応することを指摘し、著者は「誰しも傷つきたくはないものですし、誰しも尊厳の侵害に対する強烈な自衛本能を備えているからです。ただ、そういった本能的な反応は、他者とのつながりという大きな代償を伴います。自分の身を守ることを優先した結果、私たちは互いに相手から遠ざかり、自分のことだけに集中し、まるで相手との関係性などたいして重要ではなかったかのように振る舞うようになるのです。しかし、どれだけ私たちがそう思い込もうと、他者との関係性が重要であるという事実は変わりません。私たちが持つつながりへの欲求は、遺伝子に深く刻み込まれている強力なものであり、人から遠ざかって孤立することなど、人間の本来あるべき姿に反することなのです。尊厳を良好に保ち、尊重するための理解と技術を身につけることさえできれば、自分の人生と人との関係性を、見違えるほどに改善することも可能なのです」と述べるのでした。
第1部「尊厳の10のエレメント」の第1章「アイデンティティを受け入れる」では、『男が暴力をふるうのはなぜか――そのメカニズムと予防』(ジェームズ・ギリガン著、佐藤和夫 翻訳、大月書店)の著者であるジェームズ・ギリガンは、2500人の囚人にインタビューを行ったことが紹介されます。その刑務所は最高レベルに警備を強化されており、インタビューしたうちの大多数が殺人罪で投獄された囚人でした。「なぜ相手を殺さなければいけないと感じたのか」の理由を問われた彼らは「相手に馬鹿にされたから」と答えました。著者は、「アイデンティティの侵害は、『心臓に弾丸を打ち込まれて受けた傷』とでも表現できるようなレベルの危機として認識されるのです。自分の存在価値そのものが脅かされ、自らのアイデンティティが攻撃されるように感じれば、誰もがその状況から『逃走する』か、そうでなければ『報復』に転じる、という条件反射的な反応をします。人間であれば誰もが深いところにヴァルネラブル(脆く、傷つきやすい状態)な心を持っており、それが脅かされれば、いつでもお互い加害者に転じる可能性があるのです」と述べています。
第3章「安心できる場をつくる」では、小さいころに経験した、尊厳を尊重された記憶や、逆に尊厳を侵害されたときの記憶は、本人が自分の価値に対する理解を深めていく過程に非常に大きな影響を及ぼすと指摘し、著者は「幼少期には誰もがヴァルネラブル(脆く、傷つきやすい状態)であり、ウェルビーイング(身体的、精神的、社会的に健康で幸せな状態)の感覚を他者に依存して得るものです。その段階では、未熟な尊厳を育てていく土台を準備するためにも、保護者などの養育者から継続的に愛や関心を注いでもらう必要があります。それとは正反対の扱いを子ども時代に受けると、人はどうなってしまうのでしょうか。虐待やネグレクトなどさまざまなケースが考えられますが、そういった扱いを受けた場合、人は自らの価値に対して疑いを抱き続ける人生を送ることになります」
 「朝日新聞」2021年12月28日朝刊
「朝日新聞」2021年12月28日朝刊
続けて、著者は「自分が良き人間であり、愛されるべき存在で、価値を持っているといった意識を育てていく代わりに、自分がその場にふさわしくない、間違った人間であるという意識や、自分は欠陥品なのではないかという恐れで内面が支配されていくようになるのです。そして、記憶もないほど幼く未熟なころの観点で形成された自身への価値づけは、無意識深くに根づくようになり、大人になってからもなくなることはありません。幼少期の経験をどのように捉えるのか。私たちはそれを、幼いころの自分の視点からではなく、大人としての自分の視点で再解釈したものに置き換えていかなくてはなりません。このプロセスにちゃんと取り組まない限り、人は自己不信感にとらわれ、自分の価値を信じられないままになってしまうのです」と述べます。これを読んで、わたしは日本の七五三とは、まさに子どもの尊厳を示すセレモニーであると思いました。
第5章「価値を認める」では、ポール・ウッドラフが、著書『畏敬:忘れられた美徳を新たにする』(未邦訳)の中で、わたしたち「人間」は、自分たちよりも偉大な力の存在に気づき、それを畏れ敬う心情である「畏敬」の概念に立ち返るべきだと訴えていることが紹介されます。この「畏敬」を体感することはとても重要であるとして、著者は「私たちは、非常に人間的な傾向として、自分を優れた存在と見なし、周りに害を及ぼすあらゆる言動を正当化しがちです。しかし『畏敬』の経験は、私たちにそういった傾向を省みる機会を与えてくれるのです」と述べます。
もし「人間を超えた何か偉大な存在がある」という感覚がなかったとしたら、人は自分に限界があることを忘れ、慢心するという危険を冒すことになると指摘し、著者は「この『何か偉大な存在』とは、信仰を持つ人にとっての『神』、啓蒙哲学者たちを魅了した『真実』や『正義』のような理想、あるいは無神論者のリチャード・ドーキンスをひざまずかせた『宇宙の壮大さ』ともいえるでしょう。リーダーこそ、この『畏敬』を感じることが大切だとウッドラフは論じています。彼は古代ギリシャ哲学と孔子の教えに基づいた考察の中で、かつてギリシャと中国では、治めている民に対する過度な統制への誘惑を抑止するためにも、統治者が『畏敬』の心を表すことが大切だったと指摘しています」と述べます。
第6章「公正に扱う」では、本書では人に対する尊厳の毀損に主な焦点が当てられていますが、尊厳という概念は決して人間だけに留まるものではないとして、著者は「人間が他の生物と環境に対して行っている尊厳の毀損に対しても、同様の関心が向けられて然るべきでしょう。このように、地球上のすべての生物と地球という星そのものに対して、人間がどう接するべきかを尊厳という観点から考えていくことは、自分自身と自分を取り巻く世界との間に、感情という深い次元での結びつきをつくる道でもあります」と訴えます。
また、著者は「私たち人間が、お互いを傷つけるだけでなく、他のすべての生命までも傷つけてきたことで、今どんな結果になってしまっているのか。私たちがそこに向き合い、その痛みを感情という面からも感じられるようになれば、気候変動や、地球に影響を与えている自分たちの行動も、これまでとは異なる新しい視点から見ることができるようになるでしょう。そうなれば、人間の『公正さ』に対する感覚は自然界に対しても広げられることになり、人間だけでなくすべての命が、かけがいのない、貴重で、唯一無二のものであることを、私たちが忘れることは決してなくなるでしょう」と述べています。
第7章「善意に解釈する(疑わしきは罰せず)」では、無条件に人を「善意に解釈する」のは、ネルソン・マンデラとデズモンド・ツツ大司教に共通している資質であると指摘し、著者は「彼らの共通点はそれだけではありません。この2人は、自分自身の価値を受け入れているのです。ロベン島の刑務所の看守たちは、囚人たちから彼らの尊厳を奪い取ろうとしました。しかし、マンデラは、誰も彼の尊厳を奪うことはできないということを知っており、その信念こそが、過酷な試練の中でも彼を生き延びさせたのです」と述べます。
映画『インビクタス/負けざる者たち』はマンデラを描いた伝記ドラマです。彼が南アフリカ生まれの白人たちのラグビーチームを支え、強くさせていくことで、彼らの心からの信頼を勝ち取っていく過程が描かれていますが、その中で、マンデラの尊厳の信念は、19世紀のイギリスの詩人、ウィリアム・アーネスト・ヘンリーによって書かれた「インビクタス(ラテン語で、征服されない、屈服しない、の意)」に刺激を受けたと明かされる場面があります。1つの詩が、27年以上にわたってマンデラが自らの尊厳を維持する力の源泉となったのです。
第9章「自立を後押しする」では、「相手を束縛したいという衝動は、国家的なレベルに限られたことではなく、人間関係の大半に見受けられます。例えば、妻をコントロールしたいと思っている支配的な夫や、自立した人間として娘を見ることができず、本人が自分で経験し、自分の力で夢を叶えていくことの大切さを見落としてしまっている過保護な母親、権威を失うことを恐れて、社員たちが憂慮していることに耳を貸さない経営者などです」と書かれています。
「支配」の本当の問題は、人の自立心を奪い取ってしまうことであり、これは尊厳のエレメントのひとつを侵害する行為であると指摘し、著者は「これは他のどの尊厳の侵害にも共通していえることですが、自立心を奪うことで、その人の中には憤りが生まれます。そして、この憤りによって関係性が侵食され、相手がいつ敵になってしまってもおかしくない状況をつくり出していくのです。そんな支配とは対照的に、人が自ら声をあげ行動するように勇気づけることは、相手の自由を保証し、自分自身の自由を守るというだけでなく、『人とつながりたい』というこの人間の根源的な願いを実現する第一歩へとつながるのです」と述べます。
第2部「他者の尊厳を侵害してしまう原因となる10の心理的誘惑」では、「私たちが進化の過程で受け継いできた他の遺産と同様に、この『面目を保つ』という反応は、私たちを守るどころか、かえって困難な状況に追い込んでしまうこともあります。『自分の間違いを取り繕う』という本能的な行為は、人間の遠い祖先が生きていた時代ならまだしも、21世紀を生きる私たちにとっては、有益というよりむしろ有害なものとなっているのです」とあります。
第14章「他者からの承認という偽りの尊厳を求める」では、本物の尊厳は「自分が存在している」という奇跡を完全に受け入れたときにもたらされるとしながらも、著者は「にもかかわらず、なぜ私たちは誰もが価値ある存在であり、正しい扱いを受ける権利があるという真実を見失ってしまうのでしょうか。なぜこんなにも多くの人たちが、偽りの尊厳を探し求めるという罠にはまりやすくなってしまっているのでしょうか。こうしたことこそ、私たちが本当に持つべき問いであると私は考えています」と述べます。
第15章「偽りの関係性の中に安心を求める」では、人間の脳には神経メカニズム(ミラーニューロン)が備わっていて、そのメカニズムによって人は同調し合い、相手の感情を感じ取ることができるようになっているとして、著者は「そのメカニズムが働く際、私たちは相手の感情から、プラスとマイナスンの、どちらの影響も受けます。例えば、大切な人と一緒にいるときというのは、たいてい楽しい気持ちになるものです。しかし、誰かと一緒にいるときにマイナス感情を絶え間なく生み出し私たちを嫌な気分にさせるのもまた、この神経メカニズムの働きです。相手に対してプラスあるいはマイナスのどちらに感じていようと、いずれにしろ人はつながり合っているということです」と述べています。
第16章「衝突や対立を避ける」では、他者と一緒にいることが、建設的で人生を向上させるものだと感じられるとき、感情のエネルギーの流れは良い方向に作用するとして、著者は「私たちが関係性を楽しんでいるときに分泌されるホルモンやその他の科学物質は、健康に有益な効果を与えることが証明されています」と述べます。世界的に名の知れた医師であるディーン・オーニッシュは、著書『愛は寿命をのばす――からだを癒すラブ・パワーの実証的研究』(吉田利子翻訳、光文社)の中で、ライフスタイルを変えることによって、重度の心臓病でさえも快方に向かわせることができると報告しています。著者は、「彼の提案するライフスタイルの変化には、食事法や運動についてだけでなく、愛情ある建設的な人間関係が病気の快復に大きな役割を果たすという、驚くべき研究結果も含まれています。すなわち、人から大切に扱われることが私たちの病気を癒すというのです」と書いています。
第22章「尊厳の約束」では、児童精神医学者のブルース・ペリーが紹介されます。彼は、神経科学者としてもキャリアを重ねてきた人物ですが、心理的な傷を癒すうえで知っておくべき重要なポイントはたったひとつしかなく、それは「愛と思いやりに溢れた関係性」こそ大きな力を持っているということだと述べています。そして、専門的なセラピーの中での関係性も大切ではあるけれど、そのセラピーの外で起こることの方が大きな癒しになることもあるとまで言います。例えば、その人の話を聞いてあげたり、その人の存在や経験してきたことや悩みを認めてあげたりといった、シンプルな尊厳の実践が、当人にとっては自己の価値を取り戻すうえで大きな助けになるというのです。
ハーバード大学の成人発達研究所の所長であるジョージ・ヴァリアントは、歓びや愛や思いやり、そして許しといったプラスの感情を経験することが、スピリチュアルな人生、つまり、精神性溢れる人生の要素であると考えています。著者は、「彼は、スピリチュアリティ(精神性)を『他者と(そして神とつながるような経験と)私たちを結びつける、プラスの感情が組み合わさったもの』と定義しています。ヴァリアントは、『精神的な意味で重要となるプラスの感情』として、『愛、希望、歓び、許し、思いやり、信念、畏怖、感謝』の8つを挙げ、『これらの感情にはすべて、人間同士のつながりが関わっており、8つのうちで「自分のことだけ」に留まるものはひとつもない』と述べています」と紹介します。
尊厳について学ぶこと、そして、尊厳が人の社会面および感情面のウェルビーイングにどのように作用しているのかを学ぶことは、人間としての必須事項であるとして、著者は「人が無知で在り続ける限り、この暴力が溢れる世界に大きな変革が起こる見込みなどほとんどないでしょう」と述べます。ミシェル・オダン著『赤ちゃんの目で22世紀を考える――愛情の科学』(金光一郎・プライマルヘルス情報センター翻訳、同朋舎)の中で、オダンは、暴力を理解することに焦点を当てるのではなく、いかにお互いを愛するかを学ぶよう呼びかけています。そして、著者は「お互いへの『愛』を示すのに、相手の価値を認めることほど最良の道はありません」と述べるのでした。本書は、哲学や心理学の最新の領域までカバーしており、とても勉強になりました。わが社のミッションでもある「人間尊重」について考える上でも貴重な読書経験となりました。」
