- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0778 人生・仕事 『最後の授業』 北山修著(みすず書房)
2013.08.14
『最後の授業』北山修著(みすず書房)を読みました。
「心をみる人たちへ」というサブタイトルがついています。カバー画には赤羽末吉の「つるにょうぼう」が使われ、帯には次のように書かれています。
「〈心〉の時空に想いをこらし、患者と傷つきや罪悪感を共に見つめてきた精神分析家として、〈心〉をみる、診る、看る知恵と技術を伝えたい―。『最後の授業』のすべてを収録!」
著者は非常に多彩な人で、精神科医であり、精神分析家であり、臨床心理学者であり、作詞家であり、そしてミュージシャンでもあります。
1946年に兵庫県淡路島で生まれました。洛星高校を経て、京都府立医科大学医学部を卒業しています。現在は九州大学名誉教授、白鴎大学副学長兼教育学部特任教授、国際基督教大学客員教授などを務めています。専門は臨床精神医学および精神分析学で、元・日本精神分析学会会長です。
本書には、著者が九州大学を退官するにあたって、2009年から2010年初春にかけて行われた一連の最後の授業および講義を再録・編集された以下の3つの文章が掲載されています。
1.「最後の授業 テレビのための精神分析入門」
2.「最終講義 〈私〉の精神分析―罪悪感をめぐって」
3.「『精神分析か芸術か』の葛藤
―フロイトは私のことが嫌いだと思うことから」
さて、学会の会長になるほど学問を究めた著者ですが、その名前を全国的に有名にしたのは、なんといっても音楽活動によるものです。伝説のグループ「フォーク・クルセダーズ」のメンバーとしてデビューし、「戦争を知らない子供たち」「あの素晴らしい愛をもう一度」「花嫁」「風」などの多くの名曲を残しました。芸能・執筆活動を行う時は「きたやまおさむ」とひらがなになるそうです。
1.「最後の授業 テレビのための精神分析入門」の冒頭で、著者は次のように述べています。
「私は、今から35年ほど前に短期間マスコミに深く関わって、一時期はテレビやラジオによく出ました。その時にだんだん私が感じるようになったのは、いったいどこで誰が私を見ているのか分からない、話しているのか分からないということでした。それがすごく不安になったのです。ときどき、知らない人に親しげに『こんにちは』なんて声をかけられて、なんだか気持ちが悪くなってきたというようなことがありました。そういうことが起こって、テレビの世界から降りました」
著者にとって、精神分析学とは何でしょうか。著者は、「心には裏の意味がある」として、次のように述べています。
「精神分析というのは人間の心に『無意識』があることを認める学問であり精神療法です。心のありように意識と無意識の2つの領域を認めて、心の動きを観察し、それを言葉で取り扱う。心の裏側、心の見えないところ、心の普通はあまり意識されない領域のことについて言葉で考えるのです。精神分析は臨床心理学、精神医学のなかでも言葉をとても重視する、あるいは言葉を愛している学問です」
著者が述べる精神分析学の定義は非常にシンプルで明快なものですが、それでは精神分析学が扱う「心」とは何か。著者は次のように述べます。
「心とは意味に満ち満ちているものです。私は、心はなにかを思い、そして意図しよう、意味しようとしている装置であると思っています。心とか言葉とか一言で言いますが、もちろんその定義についてはさまざまありすぎて、すべて網羅できるものでもありません。ここでは精神分析の観点を強調するために単純化して、『心とは裏の意味である』という定義に焦点づけたい。それは、『何々とかけて何々と解く、してその心は』というときの心ですね。なにを意味しているのか、ということです。この心は表にはっきりとあらわれていない。背後にある。こういう、表に出にくい心の部分を私たちは取り扱っているのです」
著者によれば、日本人の心の感じ方とフロイトの感じ方は重なっているとか。日本語では「心の隅」「心の奥」「心の端」「心の見えない領域」などと言います。そいう言い方と無意識の領域のイメージはかぶります。ですから、日本人はフロイトの思考に合っているというのです。さらに著者は、次のように述べます。
「無口と言われる日本人も、面接室では多くが言いたいことを言います。ここだけの話ということが分かると、多くの方が話しはじめます。それは私たちの経験的事実です。話をしてもらうためには、治療者は、安心できる相手、秘密が保たれることを保証する聞き手にならなくてはならない。ここだけの話として話を聞く用意があることを強調し、2人の間に信頼が生まれると、みんな『心の秘密』を語りはじめるのです。でも、同じ人に、『では、調査研究でなにか喋ってください、マルペケしてください』と言うと、なんだかころっと違うことを言いはじめることがある。その時はすべてが表になる。つまり、誰が見ているか分からないここで、その裏の話はできないだろうと言うわけです。ここが私は大問題なんではないかと思うのです。だから、2人だけの話を簡単にべらべら周りに喋る人間は、精神分析家に向いていない」
わたしは、著者が作った数々の名曲が大好きです。高校の文化祭のフィナーレでは、みんなで大合唱したものです。著者の歌を聴けば、青春のさまざまなシーンが蘇ってくる人は多いのではないでしょうか。ところで、著者は自身が作った歌について次のように述べています。
「かつて私は歌を作りました。友だちのためとか、テレビのために作ったのではないのに、そこで歌が紹介されると、途端に私の歌ではなくなった、あの淋しさを覚えています。きっと心の問題を扱ってほしかったのに、テレビではなんだか歌だけが流れてしまって、私が置いてきぼりになった、そういう原体験だったのだと思います。だから、私は心のあるところに戻った。それが、私の40年間の歴史かなと思うんです」
それにしても、歌を作っていた人がなぜ精神分析の道に進んだのか。そのことについて、著者は次のように述べています。
「私の人生と重ね合わせるなら、作詞家だったことがこの仕事に就かせたということがあります。作詞家は人の心を言葉でなぞる仕事だった。だから、私は人の心を言葉で取り扱うことにすこしは長けているかなと思った。そういう思いがあったので、言葉の臨床心理学である精神分析を選んだのです」

著者は突然、マイケル・ジャクソンを取り上げて話します。2009年6月、マイケル・ジャクソンの死という事件がありました。彼の最後のコンサートのリハーサルを記録した映画「THIS IS IT」では、マイケルは常にカメラで自分を撮影して、すべて把握しようとしています。
彼はそのモニターの中の自分をいつも見ながら行動しているわけですが、あれだけ自分の「表」をモニターできるとなると、自分が自分の「表」を操作することになります。結局は、自分が自分の操り人形となってしまうというのです。
マイケル・ジャクソンの素顔はどこに行ったのでしょうか。著者は、「マイケル・ジャクソンの徹底したセルフモニタリング」で次のように述べます。
「私はマイケル・ジャクソンと同じような傾向が現代人には進んでいるのではないかと思っています。自分が自分を操作でき、そして自分の姿を見られるので、自分を修正することが可能になった。おかげで、私たちは自分を自分の操り人形にしてしまっている。そうすると、素顔はどこへ行ってしまうのか。マイケル・ジャクソンのあの黒い顔はどこへ行ってしまうのか。
彼の苦悩の根源は、黒人であったお父さんに似ているところにあったのではないかと言われています。素顔とつくりあげた白い顔との間の葛藤が、彼の中にあったのは当然でしょう。それを忘れるために薬物がだんだん必要になっていった経緯が空想できるのです。というのは、そういった現代人、そして患者さんが多いから」

著者は、精神分析を行う上で「罪悪感」の問題に惹かれたそうです。「罪悪感をめぐって」で、次のように述べています。
「『レ・ミゼラブル』のジャン・バルジャンは、銀の燭台を盗んでしまう。盗んでおいて、神父さんに許してもらった上にさらに少年を傷つけた後で『悪かった』と感じる。けっして憲兵に叱られたから『悪い』と感じるわけじゃない。愛している者を傷つけたことに直面して、私たちは悪いと感じる。この二者関係のなかでの罪悪感の発生論が、私を深いところで捉えました。私はこれにハマったといってもいいですね」

そして、著者は日本人の心の原点は『古事記』にあると見ます。
「『古事記』から読み取る日本人の『心の台本』」で、次のように述べます。
「神話は、人間が無意識に繰り返す「心の台本」が広く共有された例として位置づけることができます。よく知られている「エディプス・コンプレックス」は、フロイトがギリシャの父親殺しの神話を活用して理論化したものです。最終的にお母さんと結婚してしまうエディプスの物語を用いて、さきほど述べた父と息子の対決の物語をフロイトは読み取った」
『古事記ワンダーランド』にも書いたように、日本神話にはグリーフケアの要素が見られます。宗教哲学者の鎌田東二氏によれば、『古事記』には「女あるいは母の嘆きと哀切」があります。悲嘆する女あるいは母といえば、以下に示す3人の女神の名前が浮かびます。
第1に、イザナミノミコト。
第2に、コノハナノサクヤビメ。
そして第3に、トヨタマビメ。
『古事記』は、物語ることによって、これらの女神たちの痛みと悲しみを癒す「鎮魂譜」や「グリーフケア」となっているというのです。
特に、黄泉の国で変わり果てた姿となったイザナミノミコトのエピソードは強烈なイメージを伴います。北山修氏も、本書で次のように述べます。
「心理的に考えますと、物語にはたいてい幻滅がある。美しい女の人が、あるいは豊かで次々とものを生み出してくれた日本の女神様、母神様が醜い面をさらけだして腐ってしまう。急激に幻滅させる。その時の見た側の心の痛みや苦しみが、見にくい、醜い、汚いという言葉で表現されている」
この困難をどう克服するか。これが臨床心理学的な課題であり、著者にとっての臨床心理学的・精神分析的名問題のありかだといいます。
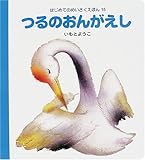
『古事記』に続いて、著者は「鶴の恩返し」という昔話を取り上げます。この昔話において、自分の羽根から布を織り上げている、つまり身体から生み出している鶴が登場します。著者は、これは出産している鶴ではないかと推測します。覗き見をする男は、出産の「血みどろ」の光景に驚いたのではないかというのです。出産とは出血がものすごくて死を伴いやすいものです。
それゆえタブーの対象になったというわけです。事実、昔の出産は出血死がたいへん多かったようです。そして、イザナミの姿はその事実を映すシンボルであると、著者は考えるのです。
著者は、「鶴の恩返し」について次のように述べます。
「ご存知のように、鶴に矢が刺さっているのを抜いてやるところから物語ははじまります。鶴は女性的な象徴、母親的な象徴です。それに矢が刺さっているのです。つまり、セックスをして出産して失敗したのが、罪悪感を避けるためにまた頭に戻ってやりなおされるという人間臭い発想で物語の加工的変化が起こったのではないか」
「あとがき」で、本書の内容を要約するとして、著者は次のように書いています。
「音楽を母親に科学を父親にして生まれた者たちの心の物語であり、それがゆえに私的で現代的であり、もちろん生きている限りはこれから後もまだ続くかもしれぬ。最終講義の時、大学人としての最後は私の好きな言葉で閉じたいと思い、あるバレエダンサーの次の言葉を紹介した。
『どう踊ればいいのか、ようやくわかった時に体がいうことをきかず辞めねばならない。人生ってそういうもんだ』」
著者は、一般に二者間の内的交流を重視する対象関係論の論者として知られるそうです。本書でも、『古事記』や「鶴の恩返し」などの神話や昔話に紡がれた男と女、母と子の関係を論じ、日本人の「心の台本」を読み取っていきます。
その作業は非常にスリリングで冒険的ですが、そこからは「人生は物語だ」、そして「物語に意味を与えるのは自分だ」、さらには「人生に意味を見つけて、生きていこう」といったメッセージを感じました。
なんだか、著者が作詞した「風」という歌に出てくる「何かを求めて振り返っても、そこにはただ風が吹いているだけ♪」「振り返らずただ一人一歩づつ、振り返らず泣かないで歩くんだ♪」という歌詞を思い出しました。