- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2023.12.08
『世界文学をケアで読み解く』小川公代著(朝日新聞出版)を読みました。「小説トリッパー」2021年冬季号から2022年冬季号まで連載した内容を、書籍化にあたって加筆訂正しています。著者は1972年、和歌山県生まれ。上智大学外国語学部教授。ケンブリッジ大学政治社会学部卒業。グラスゴー大学博士課程修了(Ph.D.)。専門は、ロマン主義文学、および医学史。著書に一条真也の読書館『ケアの倫理とエンパワメント』で紹介した前作をはじめ、『文学とアダプテーション――ヨーロッパの文化的変容』(共編著、春風社)、『ジェイン・オースティン研究の今』(共著、彩流社)、訳書に『エアスイミング』(シャーロット・ジョーンズ著、幻戯書房)、『肥満男子の身体表象』(共訳、サンダー・L・ギルマン著、法政大学出版局)などがあります。

本書の帯
本書のカバー表紙には、長髪の2人の人物の後ろ姿のイラストが描かれ、帯には「現代人が失いつつある〈ケアの倫理〉は、世界の文学にあふれている。」「『ケアの倫理とエンパワメント』で注目される英文学者が、弱者と暴力と共生、SF的想像力、新しい男性性、死者の魂を手がかりに、ケアの思想的な源をさぐり、世界の文学を読み直す画期的な5つの問いかけ」と書かれています。
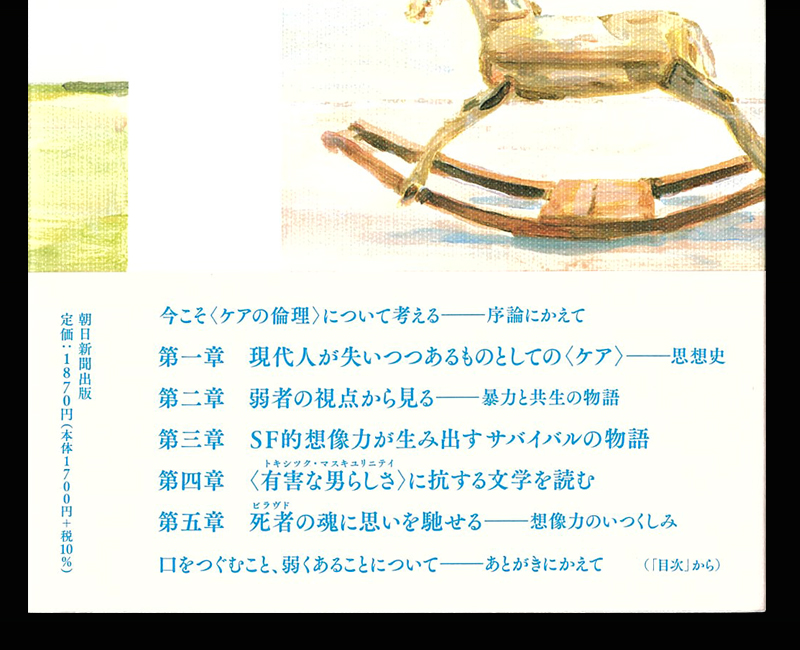
本書の帯の裏
帯の裏には、「目次」が紹介されています。
今こそ〈ケアの倫理〉について考える――序論にかえて
第一章 現代人が失いつつあるものとしての〈ケア〉
第二章 弱者の視点から見る――暴力と共生の物語
第三章 SF的想像力が生み出すサバイバルの物語
第四章 「有害な男らしさ
(トキシック・マスキュリニティ)」
に抗する文学を読む
第五章 死者(ビラヴド)の魂に思いを馳せる
――想像力のいつくしみ
口をつぐむこと、弱くあることについて
――あとがきにかえて
アマゾンの内容紹介には、以下のように書かれています。
「マン・ブッカー国際賞受賞作家の韓国のハン・ガンが描く『菜食主義者』、光州事件をあつかった『少年が来る』。欲望や怒り、憎悪などの暴力に振り回されながらも、どのようにその世界から抜け出せるのか。ブッカー賞受賞作家、カナダのアトウッドがSF的想像力で生み出した『侍女の物語』と『誓願』でのサバイバルとは? このディストピア小説の舞台である「ギレアデ」共和国は不可視の世界で、キリスト教原理主義と家父長制が支配する。そして一人の女性の苦悩が女性たちの連帯(シスターフッド)と結ばれ、「他者」の言葉の力、生存する力がしめされる。差別により死にいたらしめられる者とその過酷さを知らぬ者、老いを経験する者と年若い者、病に臥す者と健康な体を持つ者、はたしてこのような差異を乗り越えて他者の傷つきや死を、私たちは凝視できるだろうか。死者へのケアをテーマにした、トニ・モリソン『ビラヴド』、平野啓一郎『ある男』、石牟礼道子『苦海浄土』、ドリス・レッシング『よき隣人の日記』をもとに、他者への想像力を働かせることがどのようにケア実践につながるのかを考える。冷たい墓碑や硬い土に埋葬されている死者。かつては生命力に満ちていた身体と内面世界が、作品のなかで豊かな言葉によって回復されている」
「今こそ〈ケアの倫理〉について考える――序論にかえて」の1「シャーロット・ブロンテの場合」では、『ジェイン・エア』の作者シャーロット・ブロンテが、時間をかけて考えた物語を実際に「坐って書き記す暇を得られるように、家事や子の義務を果たそうと大いに気を遣っていた」ことが紹介されます。なぜなら、家事や家族の世話というケア実践のために、小説は「毎日書けるわけではなく、ときには何週間も、あるいは何か月も経って初めて、物語のすでに書かれた部分に何か書き加える」ことが多かったからです。シャーロットは、どれほど執筆にとり憑かれた状態になっていても、「彼女が何かしなければならないことがあったり、また他の人から助けを求められた時は決して一瞬の間もそれを無視したことはない」と周りの人々がはっきりと証言したといいます。
『もうひとつの声で――心理学の理論とケアの倫理』(邦訳は風行社)を書いたアメリカの心理学者キャロル・ギリガンは、〈ケアの倫理〉について熟考を重ねたことで、他者を「ケア」することと自己を他者から「分離」することとの間で葛藤していたであろうシャーロットの内面を想像することができるようになったといいます。著者は、「ギリガンが強調したように、人間は『自律モデル』か『依存モデル』かいずれかひとつで言い表されるほど単純な生き物ではない。とりわけ家事全般を担いながら、外で働こうとする女性にとっては、より複雑なモデルが必要だ。家族を養うために、年老いた父親を支え稼がなくてはならない責任を背負う長姉シャーロットも、家庭内における義務に目配りをするケア実践者シャーロットもいずれも彼女の本当の姿なのだ」と述べています。
2「ケアの価値とは何か」では、ケアがじつは互恵性を帯びることをギリガンは主張していることが紹介されます。つまり、「身勝手」なだけでもなく、「無私無欲」というわけでもない。「互恵性によって自律性を守り、自己を考慮に入れることと同じように他者のことも考慮するもの」、それが〈ケアの倫理〉であるというのです。シャーロットの妹で『嵐ヶ丘』の作者として知られているエミリー・ブロンテは「料理の主な部分を引き受け、家族のアイロンかけを全部担当していました。使用人が老衰してからは、彼女が家族のパンを全部作っていたそうです。勉強がどれほど面白くても、パン作りに失敗することはなかったそうです。
3「子育て・介護をする男たち」では、〈ケアの倫理〉を実践するのは女性だけに限らないことが指摘されます。近年、家事や育児を積極的に担うことが男性の望ましいあり方になりつつありますが、日本でいうとメンズリブ運動の嚆矢である1978年結成の「男の子育てを考える会」は男性が育児をすることが出発点でした。英文学者の河野真太郎氏によれば、近年の風潮は「第二波フェミニズムが、女性が無償の家事労働やケア労働(「再生産労働」)とも呼ばれます」を圧倒的に受け持たされている状況を問題にしたことへの応答」であったと、著書『新しい声を聞くぼくたち』(講談社)で述べています。
一条真也の映画館「ジョーカー」で紹介した2019年に公開されたアメリカの映画(トッド・フィリップス監督)では、派遣ピエロとして働きながら、年老いた母親を介護する息子アーサーが自分の能力を発揮することができず、一人前になれないことで社会の「規範」に苦しめられる「弱者男性」として描かれていることが指摘されます。アーサーは、不随意の笑いを止められないという障害のために、コメディアンを夢見るも、それがかなえられない傷を持つ男性です。河野氏によれば、この映画で表象されるのは「新たな男性主体に対する嫌悪もしくは反感」であるといいます。
また、河野氏によれば、アーサーが及ぶ暴力的な行為は「女性や有色人種などに向かうことは巧みに避けられ」てはいるが、代わりに「資本主義にまみれた富裕層」に向けられることで、この支配層にいる白人男性たちとアーサーが属する「アンダークラス」の間に分断があることが示されているという興味深い仮説を立てています。つまり、「ジョーカー」は珍しく「介護する息子」の物語であり、そこに埋め込まれた傷と憤懣の捌け口としての暴力が、男性の生きづらさを物語だというのです。著者は、「幸いこのようなケアをめぐる物語や男性性についての物語は、世界中の文学作品に見出すことができる。私も文学研究者の端くれとして、『個人』と『社会』の両方が変容するための、その紐帯として機能する「文化」が文学や映画の豊かな土壌に埋まっていることを確認したい。
第一章「現代人が失いつつあるものとしての〈ケア〉――思想史」の2「苦悩する魂――オスカー・ワイルド『獄中記』『幸福な王子』」では、耽美主義者として知られるワイルドの「美」の観念が、その先入観のせいで誤解されてきたことは作品を読めば分かるとして、著者は「ワイルドが『幸福な王子』(The Happy Prince,1888)で描いた金箔に包まれた彫像は決して外見的な『美』を具現しているのではない。ワイルドが恋人のダグラスに贈ったカフスボタンの『美』もその物自体に内在しているのではなく、2人の友情、あるいは互いへの『ケア』にあった。つまり、『美』は観念ではなく他者の『生』に関わり合うという実践でもある」と述べています。
アメリカの医療人類学者アーサー・クラインマンは、著書『病いの語り――慢性の病いをめぐる臨床人類学』(邦訳は誠信書房)において、『ドライブ・マイ・カー』の家福にしても、『リア王』のリアにしても、そして獄中のワイルドにしても、徹底的な弱さや不幸を経験することに光が当てられていることを指摘します。著者は、「自分のために、という利己的な目的が失効するところに、人間らしいケアがある。新自由主義的な社会で、競争を強いられ、保身や利潤のために日々精神をすり減らしているような人々が、このような文学に触れるとき、まさに砂漠のなかにオアシスを見つけたような気持ちになる」と述べます。
3「ケア思想――カール・マルクス、マックス・ヴェーバー、ミシェル・フーコー」では、著者は「今ではほとんどのモノやサービスが市場価値を持つ。ケアも例外ではない。〈ケアの倫理〉論者であるジョアン・トロント(Joan Claire Tronto,1952-)がイギリスのテレビドラマ『ダウントン・アビー』(Downton Abbey,2010-2015)を例に挙げているのはまだに慧眼である」と述べます。一条真也の映画館「ダウントン・アビー」で紹介した物語の舞台は1912年から1925年のイギリス、ヨークシャーの架空のカントリー・ハウス「ダウントン・アビー」で繰り広げられる物語。グランサム伯爵クローリー家とそこで働く使用人たちの生活を描いている。かつてはイギリスの貴族階級が多くの使用人を従えていたように、今では「富裕層」は誰かに労働の対価を払ってケアしてもらうことができる。つまり、ケアは「愛するひとから感謝の愛撫を受け取ったりするといった、幸せなときばかりに満ちたもの」というわけでは必ずしもないのだ(「ケアするのは誰か?」)。みさきが家福に対して行うケアもまた新自由主義的な文脈や階級の序列関係を踏まえると、より複雑な構造が見えてくるだろう。
著者によれば、ケアの問題を解きほぐすために参照できるのが、一条真也の読書館『人新世の「資本論」』で紹介した経済思想家の斎藤幸平氏のベストセラーだといいます。今の新自由主義的な風潮では、売れればなんだって構わないという資本の価値増殖を優先しすぎる「交換価値」至上主義が横行し、ケア実践を含む「使用価値」(人の役に立つという有用性)を犠牲にしてしまっています。ケア労働の「交換価値」が低いために、人々のケアに対する評価も下がっているのではないだろうか。資本蓄積と経済成長を主眼とする資本主義社会では、「感情労働」であるケア労働は、労働集約的であるため、生産性が「低く」、高コストと見なされがちです。一条真也の読書館『ブルシット・ジョブ』で紹介した名著を書いた人類学者のデヴィッド・グレーバーや斎藤氏によれば、「『使用価値』をほとんど生み出さないような労働が高給のため、そちらに人が集まってしまっている」のです。反対に、社会の再生産に不可欠な「エッセンシャル・ワーク」は使用価値が高いものを生み出す労働であるにもかかわらず、「低賃金で、恒常的な人手不足になっている」と、斎藤氏は指摘します。
何が有用で、何が有用ではないという基準が「資本」や「経済」に縮約されてしまう状況に疑問を投げかけてきた思想家はこれまでにもいました。カール・マルクス、マックス・ヴェーバー、そしてミシェル・フーコーです。著者は、「育児、介護、看護などのケアは尊い営為である。しかし、資本主義社会において、家庭内の労働と見なされるケアは、経済的な価値によって評価されない。ケアを、『善きもの』として評価した上で、ケアが新自由主義的な、あるいは資本主義のシステムのなかに組み込まれるときに、さまざまな問題を孕んでしまうことを批判的に捉えることも重要である。カール・マルクス(Karl Marx,1818-1883)の思想にはケアの精神が内在している」と述べています。
また、マックス・ヴェーバー(Max Weber,1864-1920)による『宗教社会学論集』では、専門分野がますます分化され、合理化されていく現代社会で価値が貶められるケア精神(=無差別主義的な愛)が、資本主義と西洋におけるプロテスタンティズムとの関連で論じられています。ヴェーバーは『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で、合理性を追求する資本主義の精神の根幹を「プロテスタンティズムの倫理」にさかのぼって見出していましたが、『宗教社会学編集』では「われわれの全存在が、専門的訓練をうけた官僚組織の枠組のなかに逃れるすべもなくがんじがらめになってい」る問題を指摘しています。
ミシェル・フーコーによれば、新自由主義の特異性は「社会的なものを経済化する」点にありました。労働が分業化されると、人は自分に押し付けられる一定の排他的な活動領域を持つようになり、そこから抜け出せなくなります。著者は、「フーコーは、そのような社会において個人の身体に働きかけるものとして重要なのは空間であると考えた。たとえば、学校や教会、病院、監獄、工場など、人間の身体をひとつの空間に囲い込み、その行動を監視するシステムが確立するのである。そのような空間のなかで規則的な行動が反復される。このようなシステムに呑み込まれている人間に対する包括的な『ケア』を考えていたのがフーコーといえよう」と述べます。
ケア精神を置き去りにしたビジネスの資本主義的な精神に傾倒することに反旗を翻している思想家、社会学者たちは他にもいます。インドの経済学者、哲学者のアマルティア・セン(Amartya Sen,1933-)は、「効用」情報への一元化という功利主義を批判しています。著者は、「センの思想には、物質的な豊かさや人々が満足しているかどうかという観点から人間の幸福を分析しようとする単純化された人間像を排し、新しい人間像を創造しようとする視点がある。セン以前の経済学では、人間は個人的な満足や利得や効用だけを目的に行動するという前提があったが、経済学の分野でも少しずつケアの視点を取り込むような思想が着目されるようになっているのだろう」と述べます。
人間は自分の利得にならなくても、他人の窮状をみかねて行動することもあるということでいうと、フランスの哲学者メルロ=ポンティ(Maurice Merleau-Ponty,1908-1961)やカナダの政治学者チャールズ・テイラー(Charles Taylor,1931-)らも重要な議論を提供しているといいます。著者は、「心理学には、幼児期に自己と他者が一体化した状態になることを表す『幼児の癒合性』という概念がある。メルロ=ポンティは、この自他未分化性を乗り越えたはずの成人が再び他者との混淆状態に投げ込まれ、自他が『癒合』することがあると考えた。それは苦しみを共有したいと思うほどの他者への献身愛が発現するときだという」と述べます。
また、チャールズ・テイラーによれば、孤立する近代的な自己は、〈緩衝材に覆われた自己〉(buffered self)であり、精神の外部にあるすべてのものから自分自身を分離することが可能であると見なしています。著者は、「つまり、他者と分離された〈自律的な個〉と、他者に開かれた〈多孔的な自己〉(porous self)が対比されている。後者は近代ではより希薄になりつつある存在で、内的世界と外的世界とを行き来するようなケアの精神に満ちた自己である。数々の文学作品にも『多孔的』な主体は描かれてきた」と述べています。
4「〈多孔的な自己〉――ヴァージニア・ウルフ『自分ひとりの部屋』「病気になるということ」」では、リベラル・フェミニストのシモーヌ・ド・ボーヴォワール(Simone de Beauvoir,1908-1986)が取り上げられます。同志社大学グローバル・スタディーズ研究科教授(西洋政治思想史・現代政治理論)の岡野八代氏は、著書『フェミニズムの政治学――ケアの倫理をグローバル社会へ』(みすず書房)において、ボーヴォワールが家を維持する仕事を単なる「ルーティンワーク」と見なし、人間的な価値を認めてこなかったことを「人類の活動」という広範な営みとして評価しています。著者は、「〈ケアの倫理〉論者であるジョアン・トロントも、イギリスの哲学者アダム・スミスやスコットランドの哲学者デヴィッド・ヒュームの道徳感情などの感受性の概念を採用しつつ、〈ケアの倫理〉が私的であるからこそ、普遍的な倫理より優れていると考えた」と述べます。
第二章「弱者の視点から見る――暴力と共生の物語」の2「〈妹の力〉――柳田国男『妹の力』、アンナ・ツィマ『シブヤで目覚めて』」では、柳田国男のフォークロア論に言及します。著書『妹の力』において、柳田は「妹の力」が「改めて痛切に要望せられる時代はきている」として、「過去の精神文化のあらゆる部面にわたって、日本の女性は実によく働いている。あるいは無意識にであったかも知れぬが、時あって指導をさえしている」と述べました。柳田によれば、女性は「精神作用に強く影響し」、「天然と戦い異部落と戦う者にとっては、女子の予言の中から方法の指導を求むる必要が多い」といいます。
この「女の力を忌み恐れたのも、本来はまったく女の力を信じた結果であって、あらゆる神聖なる物を平日の生活から別置するのと同じ意味で、実は本来は敬して遠ざけていた」ともいわれています。また、柳田は、彼が「精微なる感受性」と呼ぶこのケアの力を現代人が「迷信などと軽く見てしまって考えてみようともしなかった」ことに対して、疑義を唱えているといいます。さらには、沖縄の「御嶽の神々」が男女の二柱であるなど、「かくのごとき兄妹の宗教上の提携の、いかに自然のものであったかは、遠近多種の民族の類例を比べてみてもわかる」ということを著者は紹介しています。
第三章「SF的想像力が生み出すサバイバルの物語」の3「創造力の軽視/経済学の重視――ダニエル・デフォー『ロビンソン・クルーソー』」では、アメリカの女流SF作家であるル=グウィンは、著書『夜の言葉――ファンタジー・SF論』(邦訳は岩波現代文庫)において、大多数のアメリカ人男性が、「知的感覚的な精神の自由なあそび」である想像力を「抑圧」することを学んできたと指摘していることを紹介します。彼らがいかに想像力を、何か「女々しい、子どもじみた、益のない、そしておそらくは罪なこととして拒絶することを学んできた」かについて語っているとして、著者は「男らしくないという理由から『フィクション』や想像力の産物であるファンタジーやSF小説を避けるタイプの読者は、スポーツやポルノグラフィーといった『まやかしのリアリズム』に逃避するのだという」と説明します。
ル=グウィンは、「ル=グウィンの法則」、つまり「ファンタジーとお金は反比例する」という事実を指摘しながら、ファンタジーやSF小説を含む「日常意識と狂気のはざまに位置する作品群における想像力の効用」について強調しています。トールキンのSFファンタジーに描かれるホビットの世界は「社会的地位や物質的成功、収入」とは関係ないと言いそうな世の男性たちに対抗するため、彼女は「ちょっと経済学をはなれて、もうひとおし考えてみてください」と提案しています。相手が自分とは完全に異なる存在――すなわち他者――であると認識した場合の問題点をル=グウィンは物象化、あるいは「“物”にしてしまった」こととして批判しているというのです。
アダム・スミスは『道徳感情論』と『国富論』という大著を残していますが、後者では、利己心こそが経済を動かしていると確信していました。スミス自身もその経済活動に参加し、財産も相続していたわけですが、生涯独身であった彼の生活の一切合切を世話したのは母親のマーガレット・ダグラスでした。マルサルは、アダム・スミスのような白人男性が経済人の完璧なモデルであると述べています。そしてもう1人、忘れてはならないフィクションの登場人物がいるとマルサルは指摘します。それは、イギリスの作家ダニエル・デフォー(Daniel Defoe,1660-1731)が『ロビンソン・クルーソー』(Robinson Crusoe,1719)で描いた経済人です。
船に乗るたびに災難に見舞われるロビンソン。無人島漂着でさすがに悪運尽きたかと思えましたが、住居建設、家畜の飼育、麦の栽培、パン焼きなど、試行錯誤しながらも限られた資源を活用して28年も暮らすことになります。創意工夫と不屈の精神で生き抜いた男の波瀾の人生を描いた傑作です。このロビンソン・クルーソーの物語を介して、人間はモノに対してだけでなく、人間に対しても「所有」という関係を持ちうる、あるいは道具化しうることを確認できます。そしてその場合、その人間は「超越者」(「所有と固有」)と呼ぶべき存在であるという哲学者・鷲田清一氏の指摘は示唆に富んでいるといいます。著者は、「ロビンソン・クルーソーは、単なる経済人なのではなく、近代的自己に特徴的な『固有性』という幻想を見続ける『超越者』なのかもしれない」と述べるのでした。
第五章「死者の魂に思いを馳せる――想像力のいつくしみ」の1「生のかけがえのなさ」では、墓碑銘について語られます。墓碑銘は、古来より愛されし者の死を悼む「哀歌」の一部とされてきました。英文学者の友田奈津子氏は、墓碑銘は「その小さな墓石の上に人生すべてを描くことのできる」ものであり、「『喪失した過去についての瞑想』を促すもの」ともされているといいます。ノーベル文学賞者のアメリカの作家トーニ・モリスン(Toni Morrison,1931-2019)による『ビラヴド』は、南北戦争前後の時代を背景に語られる逃亡奴隷セサと彼女が自らの手で生を奪うしかなかった娘の悲劇の物語ですが、そのタイトルはセサが墓碑銘を刻んだ「ビラヴド」からきています。著者は、「幽霊となって蘇る娘をめぐるこの物語は母親セサの愛しい我が子への全身全霊の哀歌だといえる」と述べています。
死者に思いを馳せる近代文学の系譜は、18世紀イギリスの前ロマン派詩人トマス・グレイの「墓畔の哀歌」までたどれるそうです。友田奈津子氏によれば、グレイの想像力が生み出すこの詩において、墓の崇高さ、美しさは言葉1つひとつに凝縮されています。そして、その「墓」とは、かつては生を得て、日々の暮らしを送りながら千々の悲しみや喜びを抱いていた無名の人たちの比喩でもあり、この文脈における「墓」とは「そこに眠る人その人自身」であるといいます。彼らは地位や名声を得た人間ではなく、ハムデン、ミルトン、クロムウェルといった時代の寵児になりえたかもしれない、しかし生を終えてみれば、無名の誰かとして埋葬された死者であり、だからこそ、墓石はその人たちの記憶を探り当てる場所でもあるのです。
精神科医の木村敏氏は、著書『関係としての自己』(みすず書房)において、「死者とは究極の他者である」と述べました。そして「他人とは、自分でない人、自分と別の人のことである。他人を見たとき、私はそこに人間以外の生物でもロボットでもなく、私と同類の人間を見ている」とも述べました。「同類の人間を見ている」とはどういうことか。著者は、「とりわけ分断が深刻化している今日、他者を自分と同類の人間として見ることは困難になってきているのかもしれない。それは、近代人が個の自立や自己責任に重きを置きすぎるあまり、潜在的に懐疑心と攻撃性を抱え込んでしまっているからだ」と述べています。
4「ひきさかれた魂――石牟礼道子『苦海浄土』」では、一条真也の読書館『苦海浄土』で紹介したグリーフ文学の最高傑作が取り上げられます。で紹介した石牟礼道子の名著がよく知られています。2018年2月10日に90歳で亡くなった石牟礼は水俣病の現実を伝え、魂の文学として描き出した作品として絶賛されました。作家の池澤夏樹氏が個人編集した『世界文学全集』(全30巻、河出書房新社)には『苦海浄土』3部作が日本人作家の長編として唯一収録されています。池澤氏は「辺境から近代化に抵抗し、水俣にとっても、人類にとっても、石牟礼さんがいたことは『幸運』だったかもしれない。翻訳されても価値が減じず、訳された先でも価値が広がっていくような普遍性のある世界文学でした」と評しました。最後に、本書の著者である小川公代氏は「文学作品を読むとき、私たちはけっしてその作品だけを読むわけではない。その読書体験に促されて、かつて読んだ本はもちろん、それにまつわるさまざまな文化的、歴史的コンテクストをはじめ、無意識のうちに呼び起こされる他者の記憶やイメージの断片をも想像しながら読むのである」と述べるのでした。「ケア」というキーワードに惹かれて手に取った本書ですが、フェミニズムをはじめ、多くの学びを得ることができました。
