- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2377 プロレス・格闘技・武道 『増補版 日本レスリングの物語』 柳澤健著(岩波現代文庫)
2025.01.13
『増補版 日本レスリングの物語』柳澤健著(岩波現代文庫)を読みました。著者は1960年東京都生まれ。ノンフィクションライター。慶應義塾大学法学部卒業後、空調機メーカーを経て株式会社文藝春秋に入社。花田紀凱編集長体制の『週刊文春』や設楽敦生編集長体制の『スポーツ・グラフィック ナンバー』編集部などに在籍し、2003年に独立。著書に、一条真也の読書館『完本 1976年のアントニオ猪木』、『1964年のジャイアント馬場』、『1984年のUWF』、『1985年のクラッシュ・ギャルズ』、『2000年の桜庭和志』、『2011年の棚橋弘至と中邑真輔』で紹介した一連のプロレス・ノンフィクションがあります。
 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には自衛隊体育学校の乙黒拓斗選手の写真(撮影:保高幸子)が使われ、帯には「瞠目の大河ノンフィクション――『世界最強国・日本』の100年を生きる」「解説:夢枕獏」と書かれています。カバー裏表紙には、「日本のレスリングは柔道とプロレスの異種格闘技から始まった。多くの妨害と困難に挫けず日本レスリングを創始した八田一朗、笹原正三ら黄金期を支えたスーパースターや天才たち、指導者たち、そして現在、最先端で戦う選手たち。無数のドラマと多彩な人間を描ききる「正史」にしてエンターテインメント。関係者も太鼓判を押した話題の単行本(二〇一二年)に終章を増補し堂々刊行。スポーツとは、競技とは何かを抉りだす」とあります。
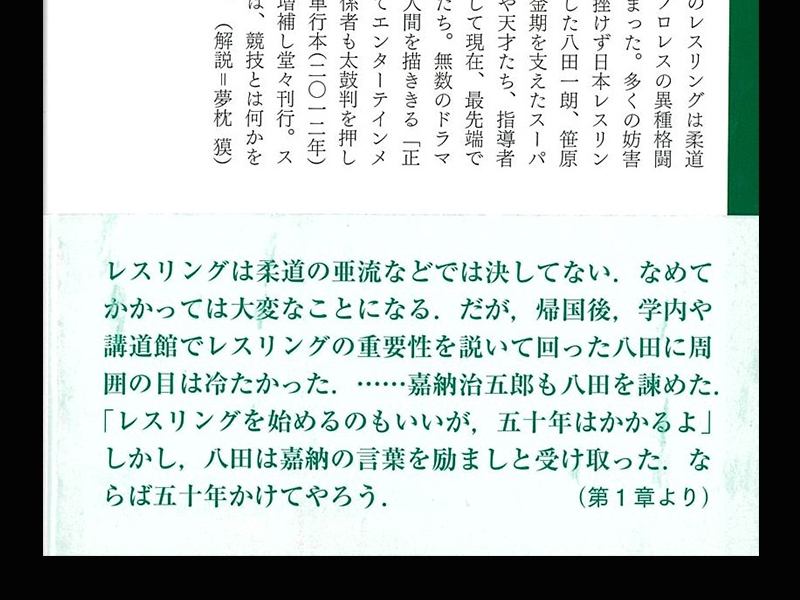 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「レスリングは柔道の亜流などでは決してない。なめてかかっては大変なことになる。だが、帰国後、学内や講道館でレスリングの重要性を説いて回った八田に周囲の目は冷たかった。…嘉納治五郎も八田を諫めた。『レスリングを始めるのもいいが、五十年はかかるよ』しかし、八田は嘉納の言葉を励ましと受け取った。ならば五十年かけてやろう。(第1章より)」とあります。
本書の「目次」は、以下の通りです。
第1章 柔道を超えろ
第2章 ヘルシンキ
第3章 クーデター
第4章 ササハラの衝撃
第5章 レスリングマスター
第6章 ローマの屈辱
第7章 すべての道は東京へ
第8章 東京オリンピック
第9章 スーパースター
第10章 反逆者
第11章 迷走
第12章 女子レスリング
第13章 少年レスリング
第14章 ロンドンへ
終章 東京オリンピック再び
「参考文献」
「あとがき」
「岩波現代文庫版のためのあとがき」
解説「オリンピックと格闘技噺」(夢枕獏)
第1章「柔道を超えろ」では、早稲田大学柔道部の庄司彦雄とプロレスラーのアド・サンテルが戦った異種格闘技戦が取り上げられます。このときサンテルからの挑戦に対し、講道館の創始者・嘉納治五郎は「プロレスラーと戦った者は破門」という声明を出しました。この声明は講道館の評判を落とし、人々はサンテルの挑戦に応じる柔道家を求めました。政治家志望であった庄司彦雄は“勇気ある柔道家”という名声を欲し、サンテルと戦うことになったのです。柔道対プロレスの異種格闘技戦は大評判を呼び、1921年(大正10年)3月、会場となった靖国神社相撲場には1万人近い観客がつめかけました。
このときのサンテルと庄司の試合について、著者は「柔道衣をつけ、様々な制約の下で戦ったにもかかわらず、プロレスラーは柔道家を終始圧倒した。しかし、サンテルが庄司に腕ひしぎ十字固めをかけたところでタイムアップ。試合は引き分けに終わった。リアルファイトであったかどうかは疑わしい。庄司は晩年まで家族にも真剣勝負だったと言い続けたが、『最初から引き分けという予定だった』という有力な証言が存在する。早大卒業後、庄司彦雄はサンテルを追うように南カリフォルニア大学(USC)に留学、柔道部を新設して柔道普及にあたる一方でプロレスのリングにも上がり、プロフェッショナル興行の仕組みを肌で知った」と述べています。
アメリカンプロレス黄金期の空気を胸いっぱいに吸い込んだ庄司彦雄は、帰国後まもなく、早稲田大学レスリング部を創設しました。ロサンジェルスオリンピックを翌年に控えた1931年(昭和6年)4月27日には、キャンパス内の柔道部道場で早稲田大学レスリング部の発会式が行われました。初代部長は早大きってのジャーナリスト教授である喜多壮一郎、コーチは庄司彦雄、主将に選ばれた八田一朗講道館四段でした。6月10日の大隈講堂では、日本レスリング史に永遠に残る第1回の公開試合が行われました。前夜には庄司彦雄がNHKラジオに出演して、オリンピック種目であるレスリングの本格参戦を大いにアピール。新聞雑誌への宣伝も行き届いていたので、入場料を徴収したにもかかわらず、大隈講堂は開設以来の大観衆を集めたのでした。
 本書より
本書より
講道館で活躍した八田一朗は、日本におけるレスリングの父です。彼は大日本アマチュアレスリング協会を設立して、全米チームを招いて大興行を行いました。そんな中、日本職業レスリング協会がひっそりと発足。日本発の本格的なプロレス団体でした。主力選手はロサンジェルスオリンピックに出場した加瀬清と、ベルリンオリンピックの予選を勝ち抜きながらも出場できなかった住吉涛。すなわち、八田一朗率いる大日本アマチュアレスリング協会から排除された元講道館レスリング部の面々でした。しかし、9月28日に洲崎ライオン球場で行われた旗揚げ戦はまったくの不入り。著者は、「現実の厳しさを思い知ったプロレスラーたちは、浅草の花やしきでプロレスを見せた。加瀬は豹柄のパンツを穿いて奮闘したものの力尽き、日本職業レスリング協会は解散に追い込まれた。元柔道家のプロレス進出は失敗に終わったのである。力道山と木村政彦がシャープ兄弟と戦い、日本中を熱狂させる17年も前のことだ」と述べます。
第2章「ヘルシンキ」では、終戦直後のGHQによる「学校武道禁止令」が、結果的にレスリングに有利に働いたことが指摘されます。多くの柔道経験者がレスリングに転向したからです。さらに当時の柔道は体重無差別級で行われていたので、小柄な選手はどうしても不利でした。体重で階級が分かれるレスリングならば互角の勝負が挑める上に、強くなればオリンピック出場も夢ではありません。第4章「ササハラの衝撃」では、日本レスリング史上に残るレジェンドである笹原正三が登場します。GHQの命令によって学校で武道を行うことが禁止されたこの時期、柔道経験者、特に比較的身体の小さい者は、体重無差別の柔道から階級制のレスリングに数多く転向しました。そして、剣道よりも柔道を好んだ笹原は、郷里・山形の先輩である三條國雄に誘われて中央大学レスリング部に入部したのでした。笹原は、1953年の全日本選手権で優勝します。
その後、1954年に東京で開催される世界選手権の前に、ソ連から日本チームに公式招待がありました。八田一朗はただちに遠征メンバーを選考。全日本選手権で優勝した笹原正三(中大OB=フェザー級)、飯塚実(明大=バンタム級)、笠原茂(明大=ライト級)、池田三男(中大=ウェルター級)らをレスリング最強国ソビエト連邦に送り込むことにしました。著者は、「日本スポーツ史上画期的なソ連遠征を実現させた日本レスリング界のリーダーは、東京世界選手権に私財をすべてつぎ込んだ結果、青山の外苑ホテルも手放し、戸越銀座のあばら家に引っ込んで貧乏暮らしを続けていた。まともな職に就かず、一切の財産を持たない八田は一朗は、銀座の洋服屋や洋菓子店の社長、天ぷら屋やレストランの社長などのパトロンたちに生活を支えられていたのである」と書いています。そして、八田の努力の結果、笹原は世界選手権で優勝。1956年のメルボルンオリンピックでも金メダルを獲得しました。
第5章「レスリングマスター」では、レスリングの歴史が俯瞰されます。まず、かつてアジアが世界の中心であったこと、“世界の中心”を守り続けてきたのは、騎乗技術、弓を弾く技術とともに、組み討ちの技術を持った騎士、ペルシャ語でいうところのパフレヴァ―ンたちであったこと、そして騎士を意味するパフレヴァ―ンは、やがてレスラーという意味に転じていったことが説明されます。著者は、「現在、トルコのイスタンブールにほど近いエディルネで年に一度行われているヤール・ギュレシュ(オイル・レスリング)に参加するレスラーは、ぺフリワンと呼ばれる。ヤール・ギュレシュは14世紀中頃のオスマントルコの時代から始まり、600年以上の長い伝統を誇る、一方、遥か東方のパキスタンでは、レスラーはパヘルワーンと呼ばれている。50歳以上のプロレスファンならば、1976年にアントニオ猪木と戦ったアクラム・ペールワンという名前のプロレスラーを覚えていらっしゃるだろう。アクラムの一族はもともとはムガル帝国のマハラジャに仕えるパヘルワーン、すなわちレスラーであった。戦国大名が力士を抱えるようなものだ」と述べています。
ギリシャとローマの文明の後継者を僭称するフランス人は、古代ギリシャで行われていたオリンピックを復活。著者は、「近代オリンピックが長らくアマチュアリズムを信奉し続けた理由は、スポーツが本来、ヨーロッパ貴族のために存在するものだからだ。そして彼らが考えるアマチュアリズムとは、貴族が平民を差別し、平民が賤民を差別するヨーロッパの階級社会を前提とする欺瞞に満ちたものであった。『肉体的労働者は職業として身体を使用している。だから彼らはプロフェッショナルである』としてオリンピック出場を禁じられた者は多い」と述べています。現在とはまったく異なり、戦前のオリンピックとは、ヨーロッパの貴族階級とアメリカの白人有産階級の裕福な子弟の間だけで争われるものでした。著者は、「戦闘技術を起源に持つレスリングは、貴族のために存在するスポーツとは本来相容れないものだ。しかし、古代オリンピック主要種目であった以上、IOC国際オリンピック委員会がレスリングを無視することはできなかった」と述べています。
近代オリンピックが始まった19世紀末から20世紀初頭にかけて、フランスでは元軍人のジャン・エクスブロイヤが始めたプロフェッショナルのグレコローマン・レスリングが爆発的な人気を呼んでいました。グレコローマンとは“ギリシャ・ローマ”という意味です。エクスブロイヤは「全裸で戦っていた古代のレスラーたちは下半身への攻撃を禁じられていた。上半身のみの攻防を行う自分たちのスタイルこそが、ギリシャやローマのレスラーが戦ったレスリングなのだ」と主張したのです。著者は、「実際にはギリシャ時代のレスリングは下半身への攻撃も認められていたのだが、それよりも重要なことは、19世紀末に行われていたグレコローマン・レスリングの試合の多くが、いわゆるプロレスであったことだ。試合結果はあらかじめ決められており、ふたりの選手は一致協力して試合を盛り上げた。現在のアマチュアレスリングの起源がプロレスにあることは興味深い」と述べています。これは、わたしも初めて知りました。そして、驚きました。
1896年の近代オリンピック第1回アテネ大会では、グレコローマン・スタイルが体重無差別で行われましたが、出場した選手はわずか5人でした。出場選手の少なさは、グレコローマンの興行に出場しているプロレスラーがオリンピックへの出場を禁じられたためでした。1900年の第2回パリオリンピックではではレスリングは種目として採用されませんでした。この頃、ヨーロッパのプロレス人気は頂点に達し、パリ、ウィーン、モスクワでは多くのトーナメントが開催されていたのに、です。1904年の第3回オリンピックはアメリカのセントルイスで行われましたが、遠い大西洋の彼方ということもあって、ヨーロッパの選手はほとんど参加しませんでした。そのためにアメリカは、レスリング競技を自国で流行しているキャッチ・アズ・キャッチ・キャン・スタイルで行ったのです。
キャッチ・アズ・キャッチ・キャン(後のフリースタイル)とは「どこでもいいからつかめ」という意味です。下半身の攻防を禁ずるグレコローマンとは異なり、全身への攻撃が許されます。キャッチ・アズ・キャッチ・キャンは、産業アック名が進行中だった18世紀後半のイギリス・ランカシャー地方で誕生しました。良質の石炭を算出するランカシャー地方には、多くの炭鉱が作られました、炭鉱夫となったのは、深刻な飢饉のために祖国を離れ、イギリスに出稼ぎにきていたアイルランド人たちでした。著者は、「貧しい彼らの娯楽はレスリングしかなかった。試合は仕事が休みとなる日曜日の午後に開催され、もちろん賭けが行われた。自らの力を頼む者同士がわずかな給金を賭けて闘ううちに、周囲の人間たちも、強いと思われるレスラーに投資するようになった。競馬のようなものだ。運が良ければ大金が稼げる。ランカシャーのレスリング熱は、たちまちのうちに石炭よりも熱く燃えさかっていく」と述べています。ランカシャー・レスリングの強者たちは、やがて炭鉱を離れてプロフェッショナル・レスラーとなっていきました。
19世紀後半、アイルランド人の多くが職を求めて希望の国アメリカへと移住すると、キャッチ・アズ・キャッチ・キャンのレスリングもまた、大西洋を渡りました。このようにアメリカのアマチュアレスリングもヨーロッパ同様に、プロフェッショナル・レスリングから派生したものだったのです。そして、第二次世界大戦後、レスリングの世界は大きく変わりました。著者は、「二度の世界大戦によってヨーロッパは凋落し、世界は2つの超大国米ソを軸に回り始めた。もはやオリンピックはヨーロッパ貴族のものではなくなっていたのだ。第二次世界大戦後初めて行われた1948年のロンドンオリンピックでは、キャッチ・アズ・キャッチ・キャンがフリースタイルと改称された」と述べます。ソ連、トルコ、イランが圧倒的な強さを示しましたが、著者は「何千年にも渡って世界の中心で戦い続けてきた男たちが、馬もいないヨーロッパの連中に負けるはずがない。歴史と伝統がまるで違うのだ。ところが日本の笹原正三は、ソ連、トルコ、イランというレスリングの伝統国に乗り込み、暑い選手層のトップに君臨する強豪をなぎ倒してみせた」と述べています。
第6章「ローマの屈辱」では、オリンピックで行われているフリースタイルとグレコローマンの二種のレスリングのうち、日本は長い間フリースタイルのみを行い、グレコローマンを無視してきたことが指摘されます。その理由を、当時早大レスリング部監督だった道明博は「グレコローマンが重要な種目でありながら、日本がこれまでに採り上げなかったのは、日本古来の競技が相撲、柔道等と、何れも下半身を活用するものばかりで、グレコローマンのように上半身のみに重点を置く講義は不適当であり、且つ成果をあげるのに時日を要すると考えられたからである」とスポーツ紙上で語りました。日本人は本来フリースタイルに適性を持ちます。それは、日本がタックルに特化したレスリングを追求してきたからだったのです。著者は、「フリースタイルにおけるタックルは四つ足の動物の動きに近い。相手の足下に虎やライオンのように低く飛びかかる。足が短く、当然重心が低く、足腰の強い日本人がヘルシンキとメルボルンで好成績を挙げた根本理由はここにある。ところが下半身の攻防を禁じられたグレコローマンでは、フリーでの利点がすべて欠点へと変わる」と指摘します。
第8章「東京オリンピック」では、1959年の全米選手権に優勝した西脇義隆が記した『米国遠征記』が紹介されていますが、これが八田一朗という人物を知る上で非常に興味深いです。西脇は、「ニューヨーク滞在中、八田会長に連れられてマジソン・スクエア・ガーデンにプロレスを見に行った。時のスターは、裸足の跳び蹴りで有名なアントニオ・ロッカだった。試合の途中、我々はリングの中央に上げられ日本のアマチュアレスラーと紹介された。リングから見た館内は驚くほど広く、最上段の観客席はかすんで見えた。試合後、会長に連れられてロッカールームに入れてもらった。シャワーを浴びて出て来たアントニオ・ロッカ選手は私の名前を書いてサインをしてくれた。八田会長の米国で顔の利くのにはまったく驚いてしまうばかりだ」と書いています。
また、西脇は「次の日、八田会長にブロードウェーの小綺麗なレストランに連れて行っていただいた。四人がけのテーブルに会長と初老の背の高い眼光鋭い鼻筋の曲がったアメリカ人とで座った。会長は私に『彼は誰だか分かるか、ジャック・デンプシーだよ。米国ではベーブ・ルースと同じくらい有名な男だよ』ボクシング元ヘビー級世界チャンピオン、ジャック・デンプシーだった」とも書いています。このとき、1959年。日本は敗戦の混乱から立ち直ったとはいえ、国際的には欧米と対等に付き合えるような時期ではありませんでした。そんなとき、ロッカやデンプシーとも懇意だった八田一朗の顔の広さは驚異的だったと言えます。陰謀論者ならば、「フリーメーソン」とか「CIA」といった名前を出すかもしれませんね。
解説「オリンピックと格闘技噺」で、作家の夢枕獏は「本書は、日本レスリングの優れた通史とでも呼べるものになっていて、日本レスリング誕生の背景に、柔道があったということまではっきり記されている」と書いています。日本のレスラーは、みんな最初は柔道家でした。しかし、これには大きく2つの流れがありました。1つは、日本に在住した日本人レスラーたちの流れであり、もう1つは、明治の頃、コンデ・コマこと柔道家の前田光世などのように、海外へ出てレスラーと戦った者たちの流れです。夢枕獏は、「本書を読んでわかるのは、日本のレスリングを作ったのは、もと柔道家の八田一朗であるということだ(なんと八田一朗は日本のプロレスにも大きな影響を与えているのだ)。そして、オリンピックというものがあったからこそ、レスリングという競技が日本に普及したということだ。もしも、オリンピックいうものがなかったら、今日日本レスリングは今のようなかたちでは存在しなかったであろう」と書いています。
その後、夢枕獏は、オリンピックと格闘技について語ります。古代オリンピックは、紀元前776年にギリシャで始まったとされています。ホメロスが『イリアス』や『オデュッセイア』を書いたのが、前750年頃です。ということは、最初のオリンピックが開催されたとき、彼はすでにこの世に誕生していたことでしょう。日本はまだ縄文時代でした。夢枕獏は、「そもそものことで言えば、オリンピック競技のほとんどは、槍を投げることも、速く走ることも、レスリングもボクシングも、戦争のための術、技であった。これは、書いておいていい。ただ、古代の彼らがすばらしかったのは、このオリンピック開催中は、基本的に戦争は中断したということである。つまり、オリンピックに出場する選手とその関係者は、戦争中である敵国の土地を、開催地へ向かうため、自由に、安全に通過することができたのである」と述べています。
夢枕獏は「戦争にほぼ直結する競技と言えば、まず、レスリングとボクシングである」と言います。レスリングが競技としてオリンピックに登場するのは、第33回大会(前648年)からでした。ボクシングはそれより20年早い第23回大会(前668年)からです。レスリングに強かった有名人といえば、哲学者のプラトンがいますが、彼はオリンピックで優勝したことはありませんでした。夢枕獏は、「このレスリング、ルールは今より苛烈であった。何しろ試合時間は無制限、相手選手の指を折ってもよかったのである。プラトン、オリンピアでの優勝経験こそないもののイストミア祭では、レスリングで2度優勝しているらしい。プラトンも、相手選手の指を折ったりしていたのであろうか。この指折りだが、ちゃんと技の名前があって、『アクロケイリモス』と呼ばれている」と述べています。
古代オリンピックには、ボクシングとレスリングの他に、パンクラチオンと呼ばれるもう1つの格闘競技がありました。今日呼ばれるところのMMA(ミックスドマーシャルアーツ)のことであり、ブラジルではヴァ―リトゥードなどと呼ばれた、なんでもありの総合格闘技のことです。プラトンは、このパンクラチオンについて「不完全なボクシングと不完全なレスリングとが合体した競技である」との言葉を残しています。パンクラチオンは、男子の最大の急所である睾丸を握りつぶしてもいいし、蹴りつぶしてもいいというルールでした。かなり陰惨なシーンもあったことと推測されます。しかし、驚くべきことに、古代オリンピック1000年以上の歴史の中で、同じ大会で1人の選手が、ボクシング、レスリング、パンクラチオンの3つの競技に出場して、そのどれもに優勝したことがあるそうです。選手の名前はクレイトマコスだそうですが、とんでもない格闘王が実在したのですね! 解説の最後に、夢枕獏は「総合格闘技MMAもだいぶ成熟してきたと思うので、そろそろ現代的ルールでオリンピック競技にしてもいいのではないかと思っているのだが、どうだろう」と書いていますが、わたしも基本的に賛成ですね。UFCなどは完全に競技として完成されているように思いますので。
最後に、本書は八田一朗の伝記としても興味深いですが、世界におけるMMAのルーツとされている1976年のアントニオ猪木とモハメド・アリの「格闘技世界一決定戦」が実現したのは、八田の一言がきっかけでした。前年の1975年3月、アリはニューヨークで開かれた、あるパーティーの席上で「東洋人でオレに挑戦する者はいないか。ボクサーでもレスラーでも空手家でもだれでもいい。100万ドルの賞金を用意する」と発言したのです。アリがこう話しかけた相手は、日本レスリング協会会長の八田でした。そこにいた白髪の紳士が日本のアマチュア・レスリング界の“大ボス”だということを知った“大ボラ吹き”のアリが、先制パンチとして放った社交辞令のようなものだったのでしょう。このアリのコメントが、八田のアメリカからのみやげ話の1つとしてスポーツ新聞に載りました。そして、それを知った猪木がアリの対戦相手として名乗りを上げたわけです。つくづく、八田一朗という人は格闘技の申し子のような人物だったのだと思えてなりません。