- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2286 死生観 『死生観を問う』 島薗進著(朝日新聞出版)
2023.12.01
『死生観を問う』島薗進著(朝日新聞出版)を読みました。著者から献本されたもので、「万葉集から金子みすゞへ」というサブタイトルがついています。著者は日本を代表する宗教学者です。1948年、東京都生まれ。東京大学文学部宗教学・宗教史学科卒業。主な研究領域は近代日本宗教史、死生学。東京大学名誉教授。本書は、一条真也の読書館『日本人の死生観を読む』 、『ともに悲嘆を生きる』で紹介した本に続く三部作の完成となる一冊です。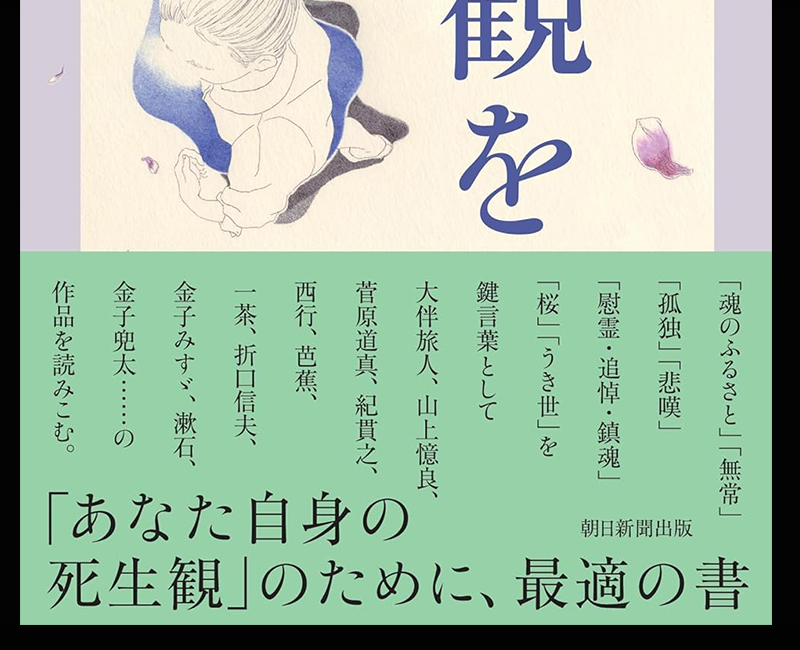 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「『魂のふるさと』『無常』『孤独』『悲嘆』『慰霊・追悼・鎮魂』『桜』『うき世』を鍵言葉として、大伴旅人、山上憶良、菅原道真、紀貫之、西行、芭蕉、一茶、折口信夫、金子みすゞ、漱石、金子兜太・・・・・・の作品を読み込む。」「『あなた自身の死生観』のために、最適の書」と書かれています。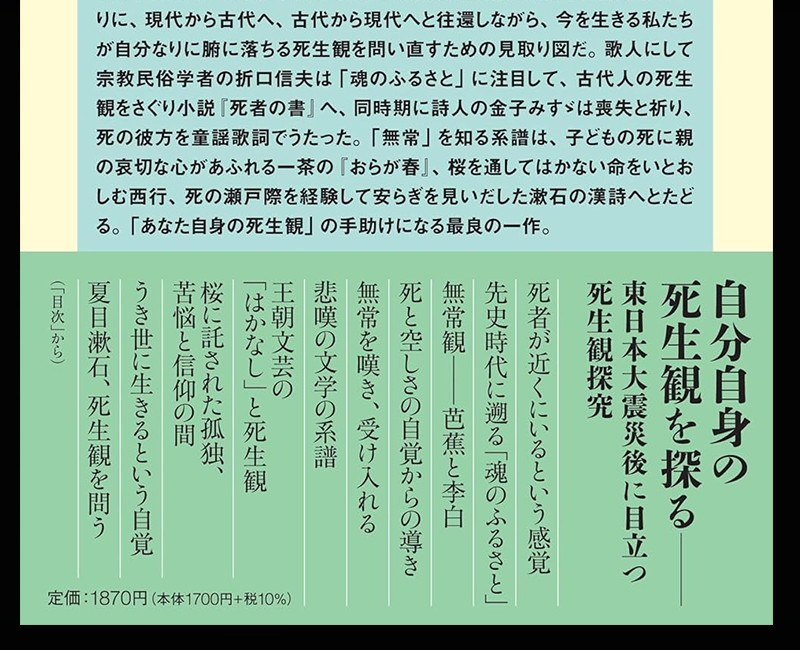 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「自分自身の死生観を探る――東日本大震災に目立つ死生観探求」として、「死者が近くにいるという感覚」「先史時代に遡る『魂のふるさと』」「無常観――芭蕉と李白」「死と空しさの自覚からの導き」「無常を嘆き、受け入れる」「悲嘆の文学の系譜」「王朝文芸の『はかなし』と死生観」「桜に託された孤独、苦悩と信仰の間」「うき世に生きるという自覚」「夏目漱石、死生観を問う」(「目次」から)と書かれています。
さらに、カバー裏表紙には、こう書かれています。
「死を前にして心は乱れてしまうだろうか。宗教学、死生学の第一人者で、グリーフケア研究を担ってきた著者にとっても、加齢とともに死、喪失、別れは、切実さがます。本書は宗教の教える死生観、詩歌や物語を手がかりに、現代から古代へ、古代から現代へと往還しながら、今を生きる私たちが自分なりに腑に落ちる死生観を問い直すための見取り図だ。歌人にして宗教民俗学者の折口信夫は「魂のふるさと」に注目して、古代人の死生観をさぐり小説『死者の書』へ、同時期に詩人の金子みすゞは喪失と祈り、死の彼方を童謡歌詞でうたった。『無常』を知る系譜は、子どもの死に親の哀切な心のあふれる一茶の『おらが春』、桜を通してはかない命を歌った西行、死の瀬戸際を経験して安らぎを見いだした漱石の漢詩へとたどる。『あなた自身の死生観』の手助けになる最良の一作」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
序章
一、『おらおらでひとりいぐも』の問い
――夫の死と死生観の覚醒
二、自分自身の死生観を探る
――東日本大震災後に目立つ死生観探究
三、あなた自身の死生観のために
――死生観の探求と文化遺産
第1章 魂のふるさとと原初の孤独
一、死者が近くにいるという感覚
二、先史時代に遡る「魂のふるさと」
三、折口信夫のマレビト
四、魂のふるさとへの憧憬
五、永遠回帰願望と原初の孤独
六、罪を贖うスサノオと出口王仁三郎、太宰治
第2章 無常を嘆き、受け入れる
一、弱さを嘆き、いのちのはかなさを知る
二、無常――野口雨情の童謡と一茶の「おらが春」
三、無常を描き出す宗教文書と文芸
四、無常観――芭蕉と李白
五、死と空しさの自覚からの導き
六、無常を嘆き、受け入れる
第3章 悲嘆の文学の系譜
一、永遠のいのちの約束とそれ以前・以後
二、王朝文芸の「はかなし」と死生観
三、母の悲嘆と作者の憤り、そして笑い
四、悲嘆・無常を描く『土佐日記』と漢文学の隔たり
五、意味深い切実な悲嘆をどう表現するのか
第4章 無常から浮き世へ
一、散る桜が表す無常感の形成期
二、散る桜の歴史、神話から無常へ
三、桜に託された孤独、苦悩と信仰の間
四、うき世に生きるという自覚
五、弱さを抱えて生きる者同士の共感
六、現代人のうき世観と魂のふるさと
終章
一、夏目漱石、死生観を問う
二、死生観表出の歴史を振り返る
――伝統のなかの死生観
三、夏目漱石の死生観、『夢十夜』
――不安と意味喪失
「あとがき」
「主な参考文献」
「はじめに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。
「宗教の教義が教える死生観は道徳と安心の源となってきた。正しい信仰をもち善業を積むことで永遠の生命、来世の幸せが与えられ、そうでなければ地獄に落ちる、あるいは悪しき運命に再生すると。こうした信仰は現代人にとってはそのままに受け取りにくくなっている。とはいえ、生活文化のなかには伝統的な宗教文化から引き継いだものが多く残っている。生活文化のなかの死生観もすっぱりと捨てることはなかなかできないものだ。弔いの文化はそのよい例だ」
そこで生活文化のなかの死生観は言葉としては表現しにくく、人生のさまざまな機会にその意味を問い直されることになるという著者は、「たとえば、なぜお墓参りをし、墓前で手を合わせるのか。教義的な死生観は受け入れにくいし、自分自身の死生観は言葉にしにくい。こうした事情もあって、自分なりの死生観を言葉にしたいと思う現代人は少なくないと思う。ヒントになるのは、過去の人々が宗教教義や科学的生命観の枠を超えて表現してきた死生観だ。自ら死に向きあったり、死別の悲嘆のなかから古人が生み出してきた言葉が豊かにあって、現代人も親しみやすいものが多い」と述べます。
特に多くの人が親しめると感じているのは文芸の中に表現された死生観だといいます。現代文芸にも死生観の表現はふんだんに見出せます。著者は「本書は古代から現代に至るまでの生活文化と日本の文芸のなかから、死生観の表現を拾い上げて、私たち現代人の死生観を問い直す手がかりにしようとして書かれたものだ」と説明しています。
序章の一「『おらおらでひとりいぐも』の問い――夫の死と死生観の覚醒」では、「魂のふるさとのありか」として、一条真也の読書館『おらおらでひとりいぐも』で紹介した小説を紹介。著者は、「この小説は、『あなた自身の死生観』を語った作品とも言える。青春小説に対して高齢者の境地を描く玄冬小説という言葉による特徴づけもあるようだが、高齢でなくても孤独をかこち、死を意識しつつ自らの身の置き所を模索している者にとっては身近な作品だろう。若者が読んでも引き寄せられるはずだ」と述べます。
著者は、『おらおらでひとりいぐも』を「あなた自身の死生観」小説と呼びたいといいます。それは死別の悲嘆と自らの死に備えて生きる生き方が正面から描き出されているからです。その意味では、無常を意識し、この世の生のはかなさを嘆く心が基底にあります。それに対して、特定の宗教の答えがあって、それを信じているというのではありません。かといって死を恐れ、死にとまどう、途方に暮れているというのでもないとして、著者は「死に備える意識があり、自分なりに答えのようなものが見えてきている。この作品はそれを描こうとしているのだ。『おらおらでひとりいぐも』という題の『いぐ』は『死に向かって行く』というニュアンスがあり、それを『おら』ひとり(自分自身)でできる、それを示した小説とも言えるだろう」と述べています。
二「自分自身の死生観を探る――東日本大震災後に目立つ死生観探求」では、大学のゼミの学習研究活動の中から、東日本大震災の慰霊・追悼と悲嘆の表出・分かち合いの深化・拡充に取り組み、そこから死生観の再構築という課題が読み取れるような書物があることが紹介されます。2018年に刊行された東北学院大学震災の記録プロジェクト・金菱清(ゼミナール)編『私の夢まで、会いに来てくれた』(朝日新聞出版)です。著者は、「これを読んだ多くの人々は、そこに記録された被災者たちの夢の語りに引き込まれ、あたかも祈りの場に立ち会っているかのように、心を動かされ、追悼の念と悲嘆への共鳴を呼び覚ますことになるだろう」と述べています。
「『夢』と『生きている死者』として、著者は、『私の夢まで、会いに来てくれた』が如実に示しているのは、現代日本では心の痛みを負うふつうの人々にとって、「夢」と「生きている死者」が深い心の痛みを慰め癒してくれるような経験領域があるということだと指摘します。その上で、著者は「これは人類社会にかつても多々あったことかもしれない。だが、『現代』の『日本』だからこそとくに際立つともいえそうだ。そこには日本の民俗宗教などの文化のなかに見られる現象とあい通じるものがときどき現れている。死者に向かって祈る、死者に何かを捧げる、死者の訪れを迎える、死者と語り合う、といった儀礼や習俗や実践は日本の過去には広く見られ、現代でも珍しいことではない。この書物にもそのような場面が多々現れている」と述べています。
このような儀礼や習俗や実践が、死者の言葉を聞く、死者のメッセージを受け止めるという形にまで展開することは伝統文化にもしばしば見られるものだったと指摘し、著者は「東北のイタコやカミサマ、沖縄のユタ、各地の稲荷信仰などでシャーマニズムとして捉えられることもある。この本の語りのなかにはそうした霊能者もときどき登場している。だが、この本の夢に現れる死者との交わりは、特別の霊能をもつ人を通して行われる『死者(霊)との交わり』ではなく、ふつうの人がふつうに見る夢のなかで行われるものだ」と述べます。このあたりは、わたしも『唯葬論』(三五館、サンガ文庫)の「交霊論」に書きました。
21世紀に入った日本では、それが珍しいことではなくなりました。夢で死者と交流する個人とその語りに引き寄せられる個人として、見知らぬ他者同士が語り、耳を傾ける関係に入る。そしてそれが相互にとって、慰めになったり学びになったりする、そのような時代になったのだといいます。著者が書いた『ともに悲嘆を生きる』(朝日新聞出版)にも書かれているように、これは各地で死別や喪失の悲嘆を語り合うグリーフケアの集いが開かれるようになった時代相と相通じているのです。ここではそれが、夢に死者が如実に現出する経験という視点をもって集められることによって、新たなスピリチュアリティの祭典のような様相を呈しているわけです。
三「あなた自身の死生観のために――死生観の探求と文化資産」では、「あなた自身の死生観のための文化資産を読み解く」として、著者は、死生観といっても広い範囲に及ぶことを指摘します。また、著者は「葬儀や追悼儀礼や死者祭祀のような、庶民生活にも及ぶような側面も重要である。この側面から死生観の歴史をたどることもできる。これは儀礼や祭祀が対象なので、何を調べればよいか、比較的、見通しやすい。実際、そうした視角からの死生観の歴史の叙述は多くなされており、有益なものもすぐに念頭に浮かんでくる」と述べて、一条真也の読書館『死者の救済史』で紹介した池上良正氏の著書、一条真也の読書館『死者のゆくえ』で紹介した佐藤弘夫氏の著書、一条真也の読書館『弔いの文化史』で紹介した川村邦光氏の著書の名をあげます。
第1章「魂のふるさとと原初の孤独」の一「死者が近くにいるという感覚」では、「『草葉の陰』と『千の風になって』」として、秋川雅史が歌って大ヒットした「千の風になって」が取り上げられます。著者は、「私が思うには、『千の風になって』では1人の死者と1人の生者の親密な関係が際立っている。それが『あの大きな空を』というように時空を超えて継続する。孤独であるとともにそれだけに親密性が重い意味をもつ、そんな現代人の心象を反映している。他方、『草葉の陰に』というと、血縁や地縁を思わせる地域性、集団性を連想させる。土臭さといってもよいだろう。私の母の中にはその両方の感覚があって、どちらも受け入れられたのだと思う。どちらにせよ、死者との近さはかわらない。『死者が近くにいる』という感覚が共有されてい」と述べています。
「千の風になって」の歌詞はアメリカ人女性が作ったもので、女友だちのドイツにいる母が死んだのを慰めるためだったといいます。復活のときまで地に眠っているはずのキリスト教の死生観とは異なりますが、死後も「草木虫魚」とともに大地の近くにとどまっている日本やアジア諸地域のアニミズムの死生観とも異なるようです。しかし、著者は「死者との『近さ』という点では後者に近いのではないか。『草葉の陰に』は地縁血縁の近さと関わりがあるが、『千の風になって』は孤独だけれども、あるいは孤独であるだけに近いという感覚を表している。だが、どちらも確かに『近い』。これはどういうことか」と述べます。
ここで著者は、「死んでも遠くには行かない。家の近くにとどまっている」ということから、文化人類学者の波平恵美子の『いのちの文化人類学』(新潮選書)の内容を紹介します。同書には、「死は、拒否したり受容したりするようなものではなく、死を目前にした人も死を看取る人も当然のものと受け止めた。それは、平静であるとか、嘆き悲しまないということでは決してない。死者が年若いか子供であれば悲嘆は大きかった。死んでゆく人も、幼い子供を残して死ぬ母親の場合は特に、生に執着した言葉を周囲の人々にもらしている。山口県の調査地で明治44年生まれの婦人が次のような話をした。自分が若い頃、近所にまだ年若い子供10人を残して死んだ人がいた。余程死ぬのが心残りであったのだろう。死ぬ時に『自分は死ぬが、(自分の霊は)裏のコンニャク畑でひざではいずりまわっているから』と家族に告げたという」と書かれています。
「『いのちのプール』から生まれ帰っていく」では、流産、死産、乳幼児突然死症候群は今もリアルであり、人工中絶も多いことが指摘されます。しかし、戦後すぐぐらいまでは、病気等で4、5歳までに死んでしまう子も多かったのも事実です。「七歳までは神の子」といういいならわしが全国であって、子どもには仏事をしませんでした。著者は、「これは生まれる前に戻ってもらって、早く生まれ変わってもらう、という考えがあったという。早逝した子の次に生まれた子に、前の子と同じ名前を付けたりするのも、それと関わりがあるという」と述べます。 波平恵美子氏と
波平恵美子氏と
「いのちのプール」というのは波平氏が用いたたとえですが、なかなか巧みな表現と感じるとして、著者は「死者はやがて先祖になる。だが、その人たちがまた生まれてくる。『いのちのプール』から生まれ、またそこへ帰っていく。こんないのちの循環がある。『いのちのプール』を尊び、そこと保つべきよいつながりを維持していくことが大切だ。そうすることで、この世も平穏で喜び多いものに保たれ、死んでもこの世を見守りながら安らかにいられる」と述べます。ちなみに、ブログ「最後の絆シンポジウム」で紹介したように、波平恵美子氏とわたしはちょうど10年前の2013年11月25日に開催された西日本新聞社主催のシンポジウムで共演させていただきました。
「『家の永続』と『縦の団結』」では、かつては「イエ」を単位に、「いのちのプール」のような生命循環の感覚があったと指摘し、これが古代以来、変わらぬ日本人の死生観の基盤だと考えたのは柳田國男(1875―1962)だったと指摘します。著者は、「死者は家と村の近くの他界にいる。多くは山だ。そして、集合体としての先祖は山の神でもある。夏には田畑に降りてきて、秋には収穫の祭りを生者とともにする。お正月にも先祖は家に帰ってきて、生者とともに新年の祝いに加わる。このように死者と生者が近くにいて、いのちの循環をともにしている。そこに『家の永続』と『死後』の霊魂の存続に対する堅固な信仰があった、と柳田は言う」と述べます。
柳田國男と並んで日本民俗学の創始者とされるのが折口信夫です。1921年、折口は初めて沖縄を訪れ、スサノオとイナヒノミコトが憧れた「妣の国(母の国)」の像を「琉球の宗教」に見出すことになります。それは日本人の宗教性の原型でもあると考えられました。奄美・沖縄・先島の人々が、記紀に記された日本の古代の宗教性を今に伝えていると捉え、そこに「魂のふるさと」の原型もあると考えたのです。折口は柳田よりより12歳年下の亥年生まれで、1945年(昭和20年)夏の敗戦時には、共に60歳を越えていました。戦後にのぞみ、重い口調で柳田は折口に「折口君、戦争中の日本人は桜の花が散るように潔く死ぬことを美しいとし、われわれもそれを若い人に強いたのだが、これほどに潔く死ぬ事を美しいとする民族が他にあるだろうか。もしあったとしてもそういう民族は早く滅びてしまって、海に囲まれた日本人だけが辛うじて残ってきたのではないだろうか。折口君、どう思いますか」と話しかけたといいます。その問いにしばらく両者深く思い沈んでいたそうです。
三「折口信夫のマレビト」の「海の彼方の他界から訪れる神」では、この世の近くにいて、折にふれてこの世に帰ってくる死者、そして死者たちが行ったそれほど遠くないあの世、他界といった観念について考えているとして、著者は「『魂のふるさと』とよべるような他界を感じ取っていて、現世と他界とのいのちの循環のなかで『ともに生きるいのち』への信頼感が、別離の悲嘆や死の恐怖と釣り合っている。折口信夫が『妣が国へ・常世へ』という文章で示そうとしたことの1つは、そこに古代人の死生観があり、奄美から先島に至る沖縄(琉球・南島)の宗教はそうした古代的・先史社会的な死生観を現代に伝えているということだった」と述べています。「折口信夫がマレビト像から得たもの」では、折口信夫が記紀神話の「妣が国」や「常世」に古代以来の「魂のふるさと」の表現を読み取ろうとしたのは1920年頃のことで、ちょうどスペイン風邪が世界中で猛威をふるっていたことが指摘されます。
欧米でも軍隊での感染が目立ち、第一次世界大戦の終戦を早めたとされます。日本でも若い兵士たちの死者が多かったですが、そんな苦難の後の1921年、折口は7月から8月にかけて沖縄に滞在しました。そして、沖縄には日本古代の宗教が今も伝えられていると感じ取ります。さらに23年の7月から8月、今度は沖縄の西方、八重山諸島を訪れます。そして常世の原型であるニライカナイや訪れる神、マレビトについて語るようになるのでした。著者は、「ちょうど関東大震災によって新たな大災厄が襲う直前のことだった。折口がマレビトについて語り考察を深めていくのは、日本社会が死の脅威を身近に感じ取る時期だった。後に述べるつもりだが、あたかも死や喪失や悲嘆を主調音とする物語や歌が次々に発表されていくのを予感するようでもあった」と述べています。
「花祭と霜月神楽」では、折口信夫は沖縄の祭りに強い印象を受け、古代人の信仰世界を感じ取ろうとした時期に、本州中部地方の山間地帯で行われる霜月神楽にも大変大きな関心を持ったことが紹介されます。天竜川上流の奥三河地域、三河と信州と遠州にまたがる地域ですが、11月から3月にかけて20ヵ所近くで、数十戸単位の地域ごとに夜を徹して、「花」とよばれる神事と芸能と祝祭の場が現出します。民俗学者の早川孝太郎が『花祭』という著書で紹介し(講談社学術文庫)、折口信夫も繰り返し親しみをもって語っているものです。災厄を払い、よい収穫を願う祭だが、神事芸能である湯立神楽や田楽や念仏踊りなどの様式も混じっています。
著者も何度か花祭を見学したそうですが、心に深く残っているのは、この祭のために故郷へ帰ってきた男たちが鬼に扮する地元の男たちとともに躍る場面だったそうです。著者は、「女や子供もまだ残ってそれを楽しそうに見ている。笑いと喜びの饗宴だが、あの世の存在が来臨しているという感覚が、私にはとても懐かしく感じられた。これはお盆のとき、法事のとき、またその宴の場面に、死者が来ている、生者と死者がそこにともにいると感じるのに通じる。だが、特定の死者をめぐる集いでは限られた死者とつながりのある人々の集いだが、村の祭の場合には村人すべてがそこに関与している。そのようにして『魂のふるさと』がそこに顕現していると感じるのだ」と述べます。
「『国文学の発生』と旅する詩人・芸人」では、1920年代の折口信夫が探究に力を入れた「マレビト」は、アカマタ・クロマタのように祭りのときにあの世からやってきて「神として現れる人」だけを指すものではなかったことが指摘されます。次第に神的なマレビトが人間的なマレビトになり、宗教的なマレビトが文芸・芸能的なマレビトになります。村の外からやってきて、村の人々に呪言を与えたり、伝承を伝え、それが職業になるような存在、これもマレビトです。マレビトという言葉は、「魂のふるさと」のよそ者、「魂のふるさと」から追放された人という意味合いも含むものでした。四「魂のふるさとへの憧憬」の「『日想観往生』から『社日参り』まで」では、折口が柳田國男の『歳時習俗語彙』からいくつかの例を引いて、日本全国各地で彼岸に太陽を拝む、太陽の動きを追うなどの信仰行事が残っていたと指摘したことを紹介します。
丹波中郡(現在の京丹後市)には「社日参り」というものがあり、朝早く東方のお宮やお寺やお地蔵様などにお参りして日の出を迎え、順に南を廻って西の方に行き、日の入りを送って還って来る。これを「日の伴」といいます。宮津辺りでは「日天様の御伴」といい、紀伊の那智郡ではただ「おとも」とよんでいるといいます。こうした行事の中心は女性です。女が中心の春の行事に「山ごもり」「野遊び」があり、1ヵ所にこもるという要素があるのが古い形だったのだろうと折口は推測しています。著者は、「『死者の書』では、中将姫が何かに取り憑かれたように当麻寺に向かい、こもるのだが、それはこうした古代以来の村々の信仰を引き継ぐものとして構想されたことが示唆されている」と指摘しています。
「金子みすゞと『燈籠ながし』」では、金子みすゞの「燈籠ながし」が紹介されます。金子みすゞがその詩作品を産み出したのは大正の終わりから昭和初期で、折口信夫が「魂のふるさと」について語っていた時期のことでした。ところが、その作品が多くの人々の心を揺さぶるようになったのは平成から令和にかけての時代です。そして、現代の新たなスピリチュアリティを代表する詩人として取り上げられる存在にもなっています。著者は、「金子みすゞは深い悲しみをたたえつつ魂のふるさとを歌う日本の死生観の水脈を、孤独に苦しむ多くの現代人の心に伝えた稀有な詩人と言えるだろう」と述べています。
五「永遠回帰願望と原初の孤独」の「童謡と夕日」では、童謡には「夕焼け」を、また「夕日」や「日暮れ」を題材にしたものが多いことが指摘されます。著者の家の近所では、午後5時になると、毎日、「夕焼小焼で 日が暮れて 山のお寺の 鐘がなる お手々つないで 皆かえろ 烏と一緒に 帰りましょう」のメロディーが流れてくるそうですが、この「夕焼小焼」(1919年)の歌詞は中村雨紅によるものです。葛原しげる作詞「夕日」(1921年)は「ぎんぎんぎらぎら夕日が沈む ぎんぎんぎらぎら日が沈む」とあります。
著者によれば、これらはたぶん「母のいる家に帰る」情景と関わりがあり、失われた故郷を懐かしむ望郷の心情にも関わりがあるといいます。ここには喪失と悲嘆のテーマが潜んでいる、そう感じる人も多いだろうとして、著者は「童謡の作詞家でもっとも人気があるのは野口雨情だが、その歌詞は喪失の悲しみをテーマにしたものが多い。『あの町この町』(1924年)は覚えて知っている人が多いと思う。『あの町この町、日が暮れる 日が暮れる。今きたこの道、かえりゃんせ かえりゃんせ。お家が だんだん、遠くなる 遠くなる。今きたこの道、かえりゃんせ かえりゃんせ』」と述べます。
「『魂のふるさと』の信仰」では、明治維新からアジア太平洋戦争に至る時期に、「魂のふるさと」を喚起する誌的音楽的表現が人々の心を捉えたことを指摘します。しかし、これは詩歌を作る文人や文人志望の若者たちだけのことではありませんでした。著者は、「この時代の日本に『魂のふるさと』に深い信仰を寄せる宗教運動が広く展開していたことを思い出したい。近代日本の精神史の底流の1つをなすものと言える。たとえば天理教である。今も奈良県天理市を訪れると、そこここに『ようこそおかえり』の標語が掲げられている。天理教の本部神殿がある場所は人類のふるさとであり、その聖地への参詣は『おぢばがえり』とよばれる」と述べています。
六「罪を贖うスサノオと出口王仁三郎、太宰治」の「スサノオの後裔、出口王仁三郎」では、帰っていくべき「魂のふるさと」への憧れを表出した国文学者で民俗学者の折口信夫は、またふるさとを放逐され寒々とした孤独に苦しみ、呻き声を響かせる詩人・歌人・作家でもあったことが指摘されます。戦中に『死者の書』で死者の呻きを造形した折口は、戦後にはけもののように「泣きおらぶ」スサノオを詩作品に描き出したが、それは自画像にようでもあるとして、著者は「ここで、自らをスサノオになぞらえたもう1人の人物が思い起こされる。それは学者や文学者ではなく、近代日本を代表するといってもよい新宗教の創始者の片割れである。『開祖』出口なおとともに大本教を創始した『聖師』出口王仁三郎(1871―1948)、その人だ」と述べています。
「『帰りたいが受け入れられない』故郷」では、一条真也の読書館『世直しの思想』で紹介した宗教哲学者の鎌田東二氏の著書を参考に、近代日本のスサノオたちは、高天原のアマテラス(あるいは父のイザナギ)にあたる故郷の権威の源泉にすなおに従うことができないことを指摘します。それは駄々っ子のわがままとも見えるものですが、本人にとってはそこに世のあるべき姿が目指されているのであり、世直しの心情が潜んでいます。しかし、それは人々に理解されず、抑えつけられてしまいます。それへの抗議の意思がありますが、抑える側に依存して生きているのも確かで、その権威を尊んでいないわけでもありません。著者は、「権威の源泉であるアマテラス的存在は、出口王仁三郎の場合、一方に天皇、他方に出口なおであり、太宰治の場合、東京帝大を含む社会体制であり、津軽の名家である津島家であり、なかでも長兄である」と述べます。
「痛みすさんだ心が安らぐ場所」では、お迎え火をたいたり、お墓参りをするとき、死後の世界が身近にあるように感じることもあることを指摘。そんな「魂のふるさと」ですが、現実に死後に人がそこに安らぐことができると感じるのは容易でありません。それがたいていの現代人だろうとして、著者は「そんな現代人が、折口信夫の『妣が国へ・常世へ』という文章や、島崎藤村の『椰子の実』や、金子みすゞの『燈籠ながし』に心を動かされる。そこで懐かしく蘇る感覚は、沖縄の民俗文化にも、お盆の行事や季節の祭りにもそれに相通じるものがあり、私たちの身体や精神の奥深いところに今も潜んでいる」と述べます。
「魂のふるさと」の感覚が強いリアリティーをもって浮上する時があります。それは絶望に陥ったり、心の痛みや悲しみに胸がふさがれたように感じる時だったりすると指摘し、著者は「スピリチュアルペインとよばれるような苦難に向き合ってこそ、届かない彼岸的なものを具象化することが恵みのように訪れる。宗教者や芸術家がそのような『魂のふるさと』の現前を伝えてくれる。そのような意味で、『魂のふるさと』は今も私たち自身の死生観の手がかりであり続けている。スサノオは現代人に『魂のふるさと』を伝える媒介者の象徴でもある」と述べるのでした。
第2章「無常を嘆き、受け入れる」の一「弱さを嘆き、いのちのはかなさを知る」の「パンデミックと大地震の時代の流行歌」では、パンデミックと大地震、豪雨等に襲われ多くの人命が失われるとともに、生活が脅かされ希望が見えなくなると感じる人々が増大したことを指摘。失職したり、事業が継続できなくなったり、医療や介護や保育の場でストレスが倍増したり、被災地の第一次産業のように長期にわたって見通しが立たなくなったりしました。著者は、「人のいのちのはかなさを嘆き、人間の無力さを思い知らされるような状況が繰り返しやってくる。13世紀の初頭に鴨長明の『方丈記』が描き出したように、世の無常を痛感する日々が続いた。日本の死生観の深層にあるものが、新たにぬうっと頭をもたげてきたように感じる。2010年代に入って、東日本大震災から新型コロナ感染症へとおよそ10年の間、日本は災厄に見舞われる経験が続いている。それはまた、故郷喪失が強く実感され、望郷の念がよみがえったように感じる時期だった」と述べます。
「暗い歌謡曲『船頭小唄』の流行」では、およそ100年前の大正期、順番は逆でパンデミックから大地震へと推移していった時期があったことが紹介されます。第一次世界大戦の終了を早めたとも言われるスペイン風邪の大流行は1918年から20年にかけてですが、速水融著『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』(藤原書店)によると、死者は世界全体で2000万から4500万、日本では内地だけでも45~48万人になったそうです。その3年後、1923年に関東大震災が発生し、190万人が被災し10万人以上のいのちが失われたとされます。この時期に歌謡曲と童謡が歌われ、大流行しました。スペイン風邪の後に大流行した歌謡曲が野口雨情(1882―1945)作詞、中山晋平(1887―1952)作曲の「船頭小唄」です。著者は、「思わぬ災害や疫病で、多くのいのちが失われた時期、いのちのはかなさと故郷喪失を嘆きつつ受け入れようとする歌が広まったと言える。無常をはかなむ心情がうかがわれる歌である」と説明します。
二「無常――野口雨情の童謡と一茶の『おらが春』」の「野口雨情の童謡と喪失感」では、鈴木三重吉らが『赤い鳥』を立ち上げ、童話・童謡の運動が始まったのが1918年、野口雨情が「新民謡」というジャンルの「船頭小唄」を作詞したのが1919年、雨情の童謡詩「十五夜お月さん」は1920年の作品だということが紹介されます。スペイン風邪の流行期と重なってこれらの作品は作られました。多くの若者や子どものいのちが失われましたが、「枯れすすき」に自らをなぞらえ、「母さんにも一度わたしは逢いたいな」とうたう歌詞に、もろくも失われる「ふるさと」を遠望する心情を読み取ることもできるだろうと、著者は見ています。ちなみに折口信夫が「妣が国へ・常世へ」を発表したのも1920年のことです。著者は、「望郷の念とその背後にある喪失感と脆さ・はかなさの感覚は折口と雨情に共通のものだろう」と推測します。
「個人的な悲嘆と集合的な悲嘆の共有」では、江戸時代後期の小林一茶は長女さとを失った自己の悲しみを「露の世は露の世ながらさりながら」と嘆くとともに、その前に子を失った村の親たちの嘆きをも描いたことが取り上げられます。「露の玉つまんで見たるわらは哉」も切ない句でした。大正期以降に悲しい童謡が愛唱された野口雨情は、子どもとの別れの経験を胸に秘めながら、喪失と望郷のうたを多く作詞し、「こわれて消えた」しゃぼん玉をうたっていました。もろくはかないいのちの表現にこだわりをもった詩人と言えますが、「産まれてすぐに こわれて消えた」という歌詞は、雨情自身の亡き娘のことでした。彼は、自分の愛娘のはかない命を、すぐ消えてしまうしゃぼん玉に例えたのです。そして、雨情夫婦は、この歌によってわが子を亡くした悲しみを癒したのでした。日本人なら誰でも知っている「しゃぼん玉」とはグリーフケア・ソングだったのです。
四「無常観――芭蕉と李白」の「『野ざらし紀行』と白骨の表象」では、唐代の大詩人であった李白が栄光に恵まれた期間は短く、その後の落魄の時期の作品によってこそ、世の讃嘆を集めることになったことが指摘されます。そして、芭蕉はそのような漂泊の詩人である李白の後を追い、漢字文化圏の隠者文学の伝統に新たな一歩を記そうとしたとして、著者は「この伝統の全体を見渡す力など筆者にはもとより欠けているが、それが仏教の無常観という枠と大いに重なり合いつつも、それをはみ出す領域も大きいことに注意したい。いつ襲うかもしれぬ死に思いを寄せ、その背景の下にこの世の生を見直す。これは、宗教と文芸・芸能の伝統に深く関わっている。その日本的な展開の特徴を確かめるには、死を思い、無常を嘆き、人生の旅のはかなさを思う人類文化の広がりにも目を配る必要がある」と述べています。
第3章「悲嘆の文学の系譜」の一「永遠のいのちの約束とそれ以前・以後」の「無常を超えて永遠のいのちに至る」では、著者は「人は死から逃れることはできない。人のいのちは限りがある。自らの死を強く意識したり、親子きょうだいや親しい人の死に出合い、人のいのちのはかなさ、空しさを痛感する。そして、この世の富や名声や楽しさ、他者からの評価を得ることや自らの欲望を満たすことにとらわれていた自らの人生を省みる。これでよかったのか。異なる何かが見えてくる、あるいは異なる何かに目を向けるべきではないか」と述べています。
また、著者は「おのれの日々の生活を省みれば、なぜこれほどにものごとに執着しているのだろう。いずれは無に帰すものではないか。人は死すべきものだということを直視すれば、何が価値あるものかをあらためて考えざるをえない。これが「無常」を意識するということのわかりやすい始まりだ。そこからこの世のはかないものを超えた無限のものに向かうとする生き方がある。永遠のもの、不死のもの、絶対者、超越者、この世の生死の彼方の次元を信じ、それを軸とした生へと転換するということだ。信仰によって「天国に召される」とか「涅槃に至る」とするキリスト教やイスラームや仏教は、そのような意味で無常を超えていくことを目指す。「永遠のいのち」「大いなるいのち」、あるいは「いのちを超えた絶対的なもの」へと至る道がある。それを信じて新たな生き方へと転ずる。これが伝統的救済宗教の道である」とも述べます。
二「王朝文芸の『はかなし』と死生観」の「権力体制との距離が育む文人」では、社会的に恵まれない、あるいは政治的に不遇の立場にある、あるいはそういう人々に共鳴し、文芸的な表現にその思いを託すということは世界史上に少なくないとして、著者は「陶淵明や杜甫、李白などの漢詩の世界、『ルバイヤート』や『コヘレトの言葉』もそのような文芸の領域に属するものだろう。さらに遡ると『楚辞』や『ギルガメシュ叙事詩』にまで至る。だが、それらにはむしろ男性的な響きを感じるのではないか。自らの政治的な不如意を強く意識するのは、過去の時代には男性が多かったからだ」と述べています。
四「うき世に生きるという自覚」の「平等意識と現世肯定意識」では、無常はすべての人にとっての真実であり、誰もが死を意識する。それが浄土教の拡大の背後にある変化であることが指摘されます。『平家物語』はそのような無常観の民衆化を進めるのに大きく寄与しているとして、著者は「無常の平等性が強調され、人々に受け入れられていくという変化が進んでいく。そうすると、『うき世』は出家者や隠遁者こそが典型的に意識するものではなく、多くの町人や農民に関わりが深いものとなってくる。仏教の庶民化とうき世観の変化とは関わりが深い」と述べます。
「うき世」から日本人の死生観を考える著者は、神戸大学の哲学の教授であるとともに、僧侶であり、京都の法然院の第30代貫主でもあった橋本峰雄(1924年~1984年)の著書『「うき世」の思想』(講談社現代新書)を紹介。橋本は圭室諦成の『葬式仏教』(大法輪閣)の論旨をまとめながら、「日本の仏教寺院の現在のような分布は、1467年の応仁の乱から江戸初期の1665年までの約200年間(荘園村落が崩壊して郷村制が確立するまで)にできあがってきたものである。葬祭宗教としてすぐれていた(つまり、一般庶民の要求に合った)浄土教と禅宗とが伸張したのであった」と述べています。
圭室が親しんだ曹洞宗は禅宗であって庶民的な死生観を掲げる宗派ではありませんが、葬祭に重きを置く体制をとって庶民への浸透に成功しました。こうした仏教の庶民化に伴い、無常を自覚し極楽往生を願うとともに、この世の安楽や享受をも肯定するような意識が広がっていきました。橋本は「このような葬式仏教の庶民化・土着化ということと、『うき世』が『憂世』から『浮世』へと移行するということとは、顕著に時間が重なっている。おそらく、これは偶然の一致ではないであろう」と述べています。著者は、「あるがままの現実を否定的に捉えるのではなく、庶民の生活感覚にそって肯定的にも捉えることは、仏教的な無常観という点からは新たな展開である」と分析します。
五「弱さを抱えて生きる者同士の共感」の「うき世の背後の無常観」では、「うき世」という言葉は平安時代からよく使われており、西行の歌にも度々出てくることが紹介されます。それを漢字で書くと「憂き世」「憂世」ということになりますが、生老病死の苦に満ちたこの世、また、無常を自覚して生きるべきこの世を「憂き世」と見たものだとして、著者は「そこでは、この世を超えた浄土や月が象徴するような仏の澄んだ悟りの境地や解脱の成就が強く意識されている。彼岸に渡るということ、つまりは究極の救いの次元を信じるにもかかわらず、なおこの世の桜の美、そしてそれを歌う和歌に執着する自己を厳しく凝視する、これが西行の世界だった」と述べます。
「『うき世』と『魂のふるさと』」では、死後の救済や永遠の生命といった信仰を前提とせずに、しかし「魂のふるさとに帰ることを思う」「向こう側の何か、あるいは目に見えない大いなる何かによる安らぎを念じる」といったことがありうると指摘します。宗教的救済理念を全国的に受け入れるというのではなくて、芸術を通して、あるいは思念を通して、充溢を思い、深い疑いや孤絶に拮抗するものを求めるということがあるとして、著者は「追憶や祈りや詩や物語や音楽や美的体験や瞑想を通して、そのような境地に近づいていくという経験が広く見られる。古代以来の詩歌や物語にそれが見られることもここまでの諸章で見てきたとおりだ。個人的にそのような試みをする人は多いし、音楽療法や芸術療法もそのような方向を目指している。音楽療法の実践家は、あらゆる種類の音楽がそれに貢献する事例を語ってくれる。これはうき世の慰めを通して、死の断絶による痛みを和らげる死生観に至るものと言えるだろう」と述べるのでした。
終章の二「死生観表出の歴史を振り返る――伝統のなかの死生観」では、世界的に見れば、『ギルガメシュ叙事詩』や「コヘレトの言葉」や屈原・陶淵明以来、日本でいえば、万葉集の歌人や紀貫之や菅原道真や西行以来、それぞれ独自の死生観の表出を行って来たことが指摘されます。鴨長明や蓮如のような仏教者もその時代の宗教的死生観にそって独自の表出を行って来ました。しかし、それらはそれぞれの時代、それぞれの地域で広く共有されているものを土台としており、その枠を大きくはみ出してはいないとして、著者は「とりわけ宗教文化・大伝統(Great Tradition)の文化(大伝統は文書伝統に多くを負い長い歴史をもつ伝統を指し、キリスト教・仏教・イスラームなどの歴史的な救済宗教のほかに、儒教、道教、ヒンドゥー、ユダヤの伝統なども含まれる)が大枠を定めており、そこから逸脱する死生観の表出はあまりなかったはずだ。日本において、『無常』はその核心にある理念と見てよいだろう」と述べています。
「死をめぐる大伝統・小伝統」では、浄土教に従うなら、永遠のいのちの表象として成仏があり、極楽往生があることが紹介されます。著者は、「要するに目指すべきところという答えは大前提としてあり、共有されている死生観の根幹となっていた。これはキリスト教世界における死後の救い、神のみもとに召されるという死生観の大前提と対応するような救済宗教的死生観だ。他方、小伝統(大伝統・小伝統は文化人類学者のロバート・レッドフィールドが『未開世界の変貌』[染谷臣道・宮本勝訳、みすず書房、1978年]で定式化した用語)とも言える民衆の生活仏教や民俗宗教においては、生活環境からさほど遠くない他界に死者はおり、この世との往来がありうると信じられた。正月や盆にあの世からこの世に帰ってきて、生者とともに死者の祀りが行われるという循環的な永遠のいのちとの交流が信じられていた」と述べています。これは、まさにわたしが『供養には意味がある』(産経新聞出版)で訴えたことでもあります。
すなわち、現世と来世が断絶している救済宗教的死生観と、現世と来世が連続している民俗宗教的死生観が合体・併存していたわけです。この世と断絶し遠い彼方にある他界という死後の表象に対して、近くも遠くもありえて、個々人の内面にあるものと表象される死後の表象は「魂のふるさと」という言葉が指すものと近いだろうとして、著者は「西方極楽浄土は本来、遠い彼方のものであり、そこから死者が帰ってくるような他界ではないはずである。ところが実際には、民俗宗教的な世界と習合しており、死者と生者の交流が容易になされうるような他界として『魂のふるさと』が表象されることが多かった。多くの人々にとって、お盆に帰ってくる先祖、仏壇やお墓にいる死者、西方極楽浄土に往来した念仏者の表象が矛盾するとは意識されずに共存する事態が続いてきたのだった」と述べます。
三「漱石自身の死生観、『夢十夜』――不安と意味喪失」では、明治の文豪・夏目漱石が死の瀬戸際を経験し、『思い出す事など』を書くのは1910年のことで、その少し前の1908年、漱石は『夢十夜』を東京朝日新聞に連載していることを指摘。1913年に連載が終わる『行人』や翌年の『こころ』では、近代文明そのものの病理や鋭敏な知識人の異常心理の表れとして「不安」が描かれています。しかしながら、1908年に書かれた『夢十夜』では、不安がもっと身近で、ふつうの人の経験から縁遠くないものとして描き出されているとして、著者は「ここに表現されているのは『不安』でもあるが、また、『意味喪失』や『徒労』や『絶望』でもある」と述べます。『夢十夜』はわが愛読書ですが、著者の意見には共感できました。
『夢十夜』は漱石が自らの心の奥深くに潜む不安の正体を見定めようとして書かれた作品かもしれないとして、著者は「そこでは死と宗教が度々話題となる。背負わざるをえない過去の罪(第三夜)、報いなき祈り(第六夜、第九夜)、死と引きかえの愛(第一夜、第五夜)、徒労の末に死(第四夜、第十夜)といったふうである。それは死と宗教がともにこの世を超えた次元に関わるものであり、そのような次元が堅固であってこそ、安定した自己意識が成立する。それが欠けていること、つまり超越性が欠落していることが、自己の存在基盤を揺るがし、人を根拠の欠如に由来する深い不安に陥れる。実存的な不安と言ってもよいだろう」と述べます。この見方にも、深く共感しました。 島薗進先生は「人生の師」です!
島薗進先生は「人生の師」です!
「あとがき」では、朝日新聞出版から刊行されている月刊誌『一冊の本』に、著者が「あなた自身の死生観のために」という文章を23回にわたって連載し、それをもとに序章と終章を書き加えてまとめたのが本書であることが説明されます。死生観について書くのはこれで終わりということでもなさそうだとして、著者は「死の床についても、なお死生観を問い続けているような気もする。私自身はすでに高齢であるが、副題に20代でこの世を去った金子みすゞをあげ、終章では40代で死の彼方を意識するようになった夏目漱石をあげているように、心に響く死生観の表現は年齢を超えてなされるもののようだ。だが、『死生観を問う』ことは死に至るまで続く場合が多いだろう。私自身はそうに違いないと思っており、なお確固たる死生観をもつに至ったとは思っていない」と述べるのでした。 島薗先生と対談しました
島薗先生と対談しました
著者は、わたしにとって死生観、グリーフケア、そして人生の師ですが、これまでの著書と同様に本書からも大きな学びを与えていただきました。ブログ「島薗進先生と対談しました」で紹介したように、11月29日、わたしは偉大な師と対談させていただく機会に恵まれました。まことに幸せなことだと思っております。